04認知症コラム
認知症で「言うことを聞かない」際の対応7つ
ー原因やNG対応も解説
2025.10.08

高齢者の方に良かれと思って提案しても、強く反発したり、なぜか急に怒ったりするということがあります。「言うことを聞かない」ことが増えてきたのは、もしかしたら認知症が原因かもしれません。なぜ認知症になると言うことを聞かなくなるのか、また、家族や介護者はどのように対応できるのか解説します。
「言うことを聞かない」のは認知症が原因?
「高齢の家族が言うことを聞かないことが増えてきた」とお悩みの方もいるかもしれませんが、「言うことを聞かない」のは認知症の症状である可能性があります。
認知症では脳の機能が徐々に低下するため、記憶や判断力、理解力に影響を及ぼします。進行具合によってはコミュニケーション能力が低下し、自分の意思をうまく伝えられなくなり、「言うことを聞かない」ように見えることがあります。
コミュニケーションがうまく取れないことは、介護者にとっても大きな負担です。言うことを聞かない理由を知り、適切に対処する必要があります。
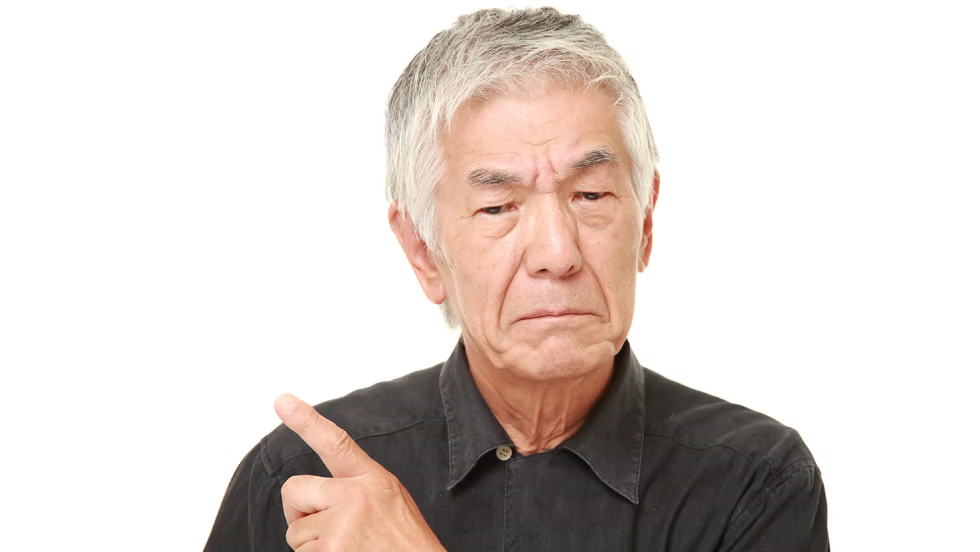
言うことを聞かない原因となる認知症の中核症状
認知症の「中核症状」により、「言うことを聞かない」状況が発生してしまうことがあります。ここでは、「言うことを聞かない」状況につながる中核症状を紹介します。
記憶障害
記憶障害とは、新しいことを覚えることや、ついさっきしたこと・聞いたことを記憶することが難しくなることです。認知症の初期段階から見られ、昔のことはよく覚えているのに、何度も同じことを尋ねたり指示を忘れてしまったりすることがあります。
見当識障害
見当識障害とは、現在の時間や年月日、場所、自分が置かれている状況などが把握できなくなる症状です。日常生活に混乱が生じるため、周囲の指示に従うことが難しくなります。
たとえば、待ち合わせの時間を守れなくなったり、通い慣れた場所に行けなくなったりすることもあるでしょう。
理解・判断能力の低下
認知症が進行すると、理解力や判断力の低下が見られるようになります。情報処理能力も低下し、2つ以上の指示を伝えると、途中で混乱してしまいがちです。複雑な指示やいつもとは異なる指示などを理解できなくなることも少なくありません。
実行機能障害
実行機能障害とは、計画を立てて行動することや効率よく動くことが難しくなる症状です。予想外の出来事への対応も難しくなるため、日常生活に支障が生じます。たとえば、外出前にどのような順序で準備をすればよいのかわからなくなり、約束の時間に遅れることがあるかもしれません。
失語
失語とは言語障害の症状の一つで、言葉を使ったコミュニケーションが困難になる症状です。思うことがあっても言葉が出てこない、言葉が出てきても相手に伝わらないといった影響が生じることがあります。失語状態になると、指示を理解しても、適切に反応できなくなることも少なくありません。
失認
失認とは、自分の身体、自分と物・相手との位置関係、目の前の物が何かなどを認識することが難しくなる症状です。物の名前や使い方、知人の顔などを認識できなくなることもあります。失認状態では指示に対する理解が困難です。また、片側空間失認では、左側もしくは右側だけが認識できないこともあります。
失行
失行とは、今までできていたことが、運動機能に問題があるわけでもないのにできなくなることです。たとえば、ケガをしているわけでもないのに服を着る・ご飯を食べるといった動作ができなくなることがあります。
中核症状以外でとくに注意すべき認知症の症状
認知症には全ての患者に見られる中核症状と、中核症状に伴って発症する周辺症状があります。周辺症状にも「言うことを聞かない」状態につながる可能性があるため、介護者は症状を熟知しておくことが必要です。
上記のような症状は、介護のしづらさにつながることがあるだけでなく、認知症の方の生活に支障をきたすこともあり、適切な支援が求められます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
暴言・暴力 徘徊 異食 介護拒否
認知症による暴力・暴言行為について詳しくはこちら
認知症による徘徊について詳しくはこちら
認知症の周辺症状(BPSD)について詳しくはこちら
認知症の方が言うことを聞かない場合に
やってはいけないこと5つ
認知症の様々な症状により、「言うことを聞かない」ように見えることがあります。症状を理解した対応を心がけることで、認知症の方に寄り添った介護を実践しましょう。まずは認知症の方にやってはいけない対応の例を紹介します。
大声で叱る
認知症の方に大声で叱ることは控えましょう。恐怖心をあおり、混乱を招くだけでなく、何に対して叱られているのか理解できず、かえって不安を増幅させる恐れがあります。
また、介護者を「怖い人」と認識することで、今後のコミュニケーションにも支障が生じるかもしれません。認知症の方を安心させるように、穏やかな話し方を心がけましょう。
失敗を責める
頭ごなしに認知症の方の失敗を責めるのもよくありません。認知症の方の自尊心を傷つけ、自発的に行動しないようになってしまう可能性があります。
介護者からは失敗のように見えても、本人には何らかの理由があり、やるべきことをしたと考えている可能性もあります。まずは優しく受け入れ、認知症の方の気持ちを理解するようにしましょう。
間違いを細かく指摘する
間違いを細かく指摘するのも避けるべきです。認知症の方にストレスを与え、パニックを起こす恐れもあります。
また、物事を正確に理解・記憶することが難しくなっているため、指摘されても改善できないケースが少なくありません。落ち着いた状態でコミュニケーションが取れるように、認知症の方の意見や行動を受け入れ、共感を示しましょう。
行動を急かす・制限する
高齢になると素早い行動が難しくなることがあります。認知症の方も例外ではありません。運動機能の低下を理解し、行動を急かすことがないようにしましょう。
また、行動を制限することも控えましょう。認知症の方のストレスを増大させ、焦りや不安感を高め、かえって失敗が増える可能性もあります。まずは介護者自身が、「自分が同じような対応をされたらどうか」を常に考え、人としての尊厳を守った行動を心がけましょう。
無視・放置する
同じ間違いを何度も繰り返しても、無視したり放置したりしないようにしましょう。認知症の方の孤独感や不安感を強め、自己肯定感が低下する原因となります。また、子ども扱いするのもよくありません。認知症の方の尊厳を傷つけないように、年齢や立場に応じた対応を心がけましょう。
その他のやってはいけないことについては、次の記事で詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。
認知症の方が言うことを聞かない場合の対応7つ
認知症の方が言うことを聞いてくれないときは、認知症の症状や特徴に配慮した対応を心がけましょう。ここでは、実践したい対応を7つ紹介します。
正面から近づいて視界に入る
認知症の方の介護は、「驚かせない」ことに注意が必要です。正面から近づいてゆっくりと視界に入ることを心がけましょう。
認知症の方は視野が狭くなりがちです。側面や背後からアプローチすると驚かせてしまうだけでなく、パニックを招くかもしれません。安心感を与えるためにも、視界への入り方に注意しましょう。
目を見て話す
信頼関係を築くためにも、目をしっかりと見て話すことが必要です。しかし、上から見下ろすと、威圧感を与えてしまいます。認知症の方の目の高さに合わせて腰をかがめ、対等な関係を築くようにしましょう。
目を見て話すことで、認知症の方が意識を集中するため、話を理解しやすくなるという効果も期待できます。また、表情などから言葉だけでは伝わりにくいニュアンスも伝わるかもしれません。
耳元ではっきり・ゆっくりと話す
加齢により聞こえにくくなっている方もいるため、耳元ではっきり、ゆっくりと話すように意識しましょう。
また、ゆっくりと話すことで、認知症の方は話の内容について時間をかけて理解するようになります。誤解が減り、会話がスムーズに進む効果も期待できるでしょう。
短く、わかりやすく話す
認知症の方は認知機能だけでなく聴力も衰えていることがあるため、できるだけ簡潔にわかりやすく話すことが大切です。一度に2つ以上の質問や情報を伝えず、1つのポイントだけに焦点を当てて話すようにしましょう。
また、「どうしたいですか?」ではなく「今から食事をしたいですか?」のように、「はい」か「いいえ」で答えられる質問をすると、認知症の方の負担を減らせます。
相槌をわかりやすく打つ
認知症の方が話しているときは、「あなたの話をしっかりと聞いています」と伝えるためにもわかりやすく相槌を打つようにしましょう。認知症の方が安心して話し続けることができ、会話がよりスムーズになります。
また、会話が途切れたときも、急かしてはいけません。認知症の方の反応をうかがい、自分のペースで話せるようにサポートしましょう。
できたことを褒める
認知症の方とのコミュニケーションは、「驚かせない」「急かせない」に加え、「自尊心を傷つけない」ことが大切です。
失敗を責めるのではなく、できたことを積極的に褒め、前向きな声がけを心がけましょう。自尊心を傷つけないように配慮することで、認知症の方は安心して発言し、行動できるようになります。
言動だけでなく表情をよく見て判断する
認知症の方の言動だけでなく、表情をよく観察しましょう。表情から意図や感情を読み取れることがあります。たとえば、攻撃的な発言や態度は、悲しさや不安を抱えているのかもしれません。
また、スキンシップを取ることも大切です。言葉以外から介護者の感情を伝えられることもあります。ただし、認知症の方が嫌がる素振りを見せたときは、無理に触れないようにしましょう。

認知症の方とのコミュニケーションでよくある悩み
同じことを繰り返し言う 会話がかみ合わない 言うことがコロコロ変わる 支離滅裂なことを言う 作り話をする
認知症の方とのコミュニケーションは、スムーズにいかないことも珍しくありません。話に矛盾が生じたり、会話がかみ合わなかったり、また、急に怒り出したり、泣き出したりすることもあるでしょう。
どのように対応すればよいのかわからないことは、介護者にとって大きなストレスです。次の章では、認知症の方との基本的な接し方のポイントについて解説します。
押さえておくべき認知症の人との接し方のポイント
認知症の方とのコミュニケーションの基本ポイントを紹介します。ただし、個人差があるため、相手をしっかりと観察し、状況に応じた適切な対応を探すようにしましょう。

本人のペースに合わせる
認知症の方と接するときには、まずは本人のペースに合わせることが重要です。急かしたり、無理に言うことを聞かせようとしたりすると、ストレスを与えることになりかねません。
焦らず合わせることを意識して接することで、認知症の方が心を開き、コミュニケーションを取りやすくなります。時間をかけて認知症の方が安心できる環境を構築しましょう。
本人の尊厳を傷つけない
ちょっとした言葉や行動が、認知症の方の自尊心を傷つけてしまうことがあります。たとえば、子ども扱いしたり、命令口調で話したりするのは相手を傷つける行為です。言動に注意し、傷つける行為は避けましょう。
認知症の方ができることを自分でするように促すことも重要です。かえって手間や時間がかかることになっても、尊厳を守る接し方を心がけましょう。
よい感情を大切にする
ポジティブな感情を持って接することも大切です。優しい言葉や笑顔を意識するなら、認知症の方に安心感を与え、信頼と絆が強まるでしょう。
また、認知症の方が楽しいと感じる活動を一緒に行うことも効果的です。音楽を聴いたり、散歩をしたりといった活動を共有し、ポジティブな感情も共有しましょう。
孤独にならないよう見守る
孤独感は不安を引き起こし、認知症の症状を悪化させることがあります。こまめに声をかけ、話し相手になることで、孤独感を和らげるようにしましょう。また、地域のサポートグループやイベントに参加し、社会的なつながりを持つようにサポートするのもよいかもしれません。
腕や背中をさするといったスキンシップも大切です。認知症の方の反応を見ながら、不快にならない程度のスキンシップを取ってみるとよいでしょう。
一人で抱え込まない
一般的に認知症の方とのコミュニケーションは難しく、介護者は心身ともに大きな負担を抱えがちです。ストレスを適度に発散し、家族や友人、専門家のサポートを受けて、介護者自身の健康を維持するようにしましょう。
認知症の方や家族が集まる「認知症カフェ」の利用もおすすめです。介護や福祉の専門家、家族を介護する人々なども参加しているため、役立つ情報を得られるだけでなく、地域との関わりを持つ場としても活用できます。
認知症の特性・症状を理解して介護に役立てよう
認知症の方が「言うことを聞かない」のは、認知症特有の症状や加齢などが原因となっていることが多いです。なぜ言うことを聞かないのか理解すると、認知症の方をサポートするヒントにもなるでしょう。
また、認知症の研究から最新情報を入手することも、認知症の方の介護に役立ちます。ぜひ以下から認知機能障害の改善についての情報をチェックしてみてください。



