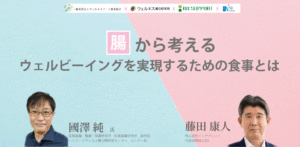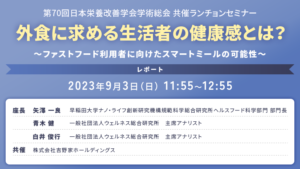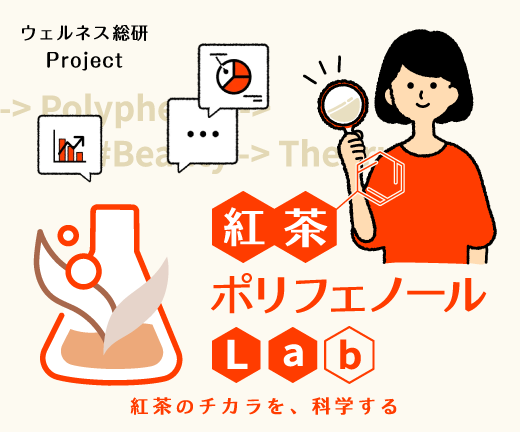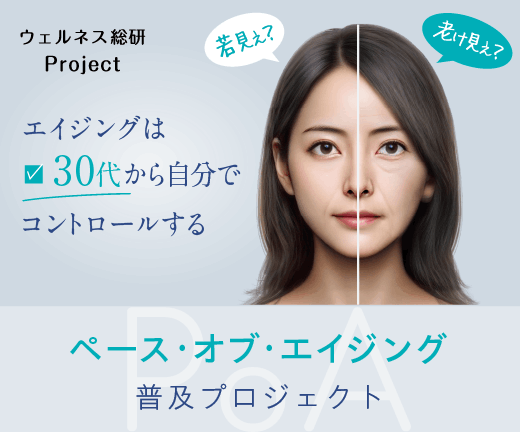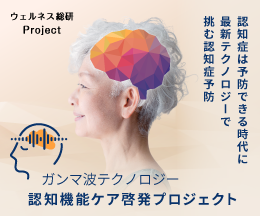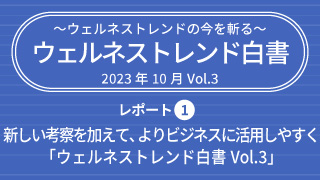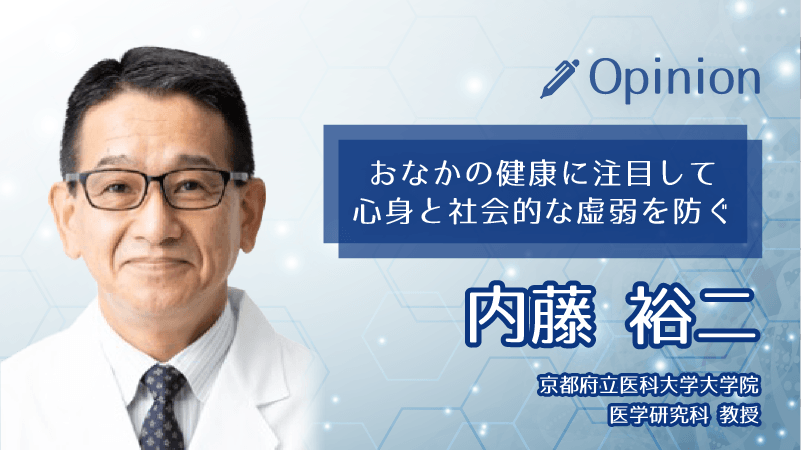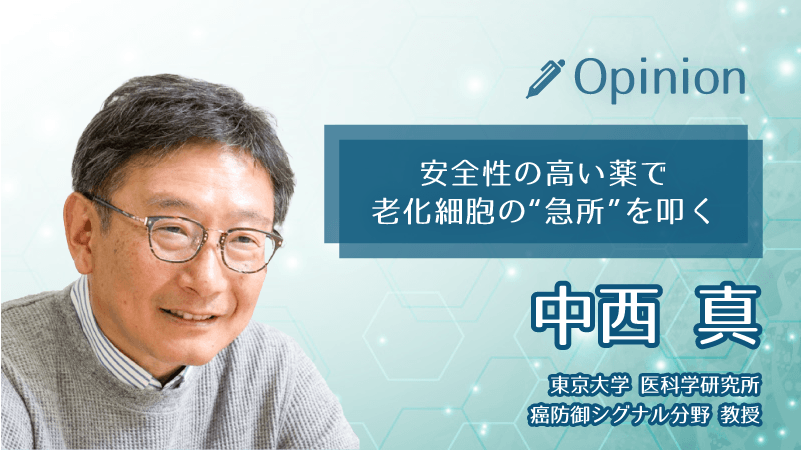【知っておくべき!学会レポート】フードサイエンスの最前線「日本農芸化学会2022年度大会」①

機能性を含む“食”の作用は様々な領域の知識と技術を持つ研究者たちによって立証され、数値化することが可能になってきました。フードサイエンス(食品科学)の研究で進展を見せる複合的アプローチについて、日本農芸化学会2022年度大会で発表された中からレポートします。フードサイエンスの研究成果を知れば、身近な食品への見方が変わってくるかもしれません。
「生命・食・環境」複合的アプローチで拓く新規フードサイエンスとは
今回、レポートするのはフードサイエンス(食品科学)に関して基礎研究から産業化まで幅広い発表と情報交換が行われる日本農芸化学会についてです。年に一度、開催されているこの大会は「生命・食・環境」をテーマとして3月16日㈬~18日㈮にオンラインで行われました。
登壇者には植物学や動物学、農学、工学、理学、社会科学、医学分野など様々な領域から専門家が集まり、異分野の知識や技術を共有して互いに研究を進展させることも目的の一つだと言います。そうした研究者たちが行う研究成果の発表や産学官での情報交換、質疑応答を聴くことで研究の一端を幅広く知ることが出来ました。
たくさんの興味深い演題の中から、熊谷 日登美氏(日本大学 生物資源科学部 生命科学科)が世話人代表を務めた「複合的アプローチで拓く新規フードサイエンス」の内容についてご紹介します。
幅広い演題の中から、身近な食への視点をリニューアルする2つをご紹介
「複合的アプローチで拓く新規フードサイエンス」というテーマで合計6名の研究者が、各々の研究成果や活動について発表されました。中には基礎知識がないとイメージしにくい部分がありつつも、その研究目的や研究ステップについてはその専門分野以外の人にも分かり易く示していたのが印象に残っています。
幅広い分野における演題の中で今回、食品メーカーやその開発担当者がとくに関心を高く寄せる部分であろう、次の2つの演題について紹介します。
○飯嶋 益巳氏(東京農業大学 応用生物科学部 食品安全健康学科)
「フードナノバイオサイエンスで拓く食の安全の可視化」
○大田 ゆかり氏(群馬大学 食健康科学教育研究センター)
「植物由来芳香族化合物を分解する酵素と微生物の解析:農業加工残渣の高付加価値化に向けて」
飯嶋 益巳氏による「フードナノバイオサイエンスで拓く食の安全の可視化」
飯嶋氏は食品の加工や安全性などに対する科学的根拠を示し食品技術の発展に寄与するため、研究対象を“ナノバイオ”(1ナノメートル=10億分の1メートル)として、その科学的根拠を高感度に可視化できることを目指し研究していると言います。
ここで、食品の安全性に加えて機能性についてもナノレベルで評価する技術の研究成果を発表。これには既知の情報として、紅茶ポリフェノールがインフルエンザウイルスに対する感染伝播阻止効果があることを示した上で、吸光度計※とAFM※を用いた抗インフルエンザウイルス活性におけるメカニズムの解明について解説しました。アッサムやスリランカ、ダージリンといった馴染みのある素材を使った研究に、さらなる解明と簡便な測定キットの製品化が待ち遠しいかぎりです。

さらに、食品品質の管理における指標となる新規低分子マーカーを探索する研究について解説。これには、食べるのに最も適切な頃合いを示す“食べ頃”やその食品のデッドラインを表す賞味期限が主観的に決定されがちな“熟成肉”を例に挙げました。経験や知識がないと最大限に美味しく食べることが難しいばかりでなく、安全性でも判断が難しい食品の評価方法があると知れば、一般の生活者における食のリテラシーも向上するかもしれません。
※吸光度計:特定の波長の光(単色光)を溶液試料に当てたときに通過した光の量を測定し、試料が吸収した光(吸光度)を分析する装置のこと。
※AFM(Atomic Force Microscope):原子間力顕微鏡。個体表面の原子層という非常に浅く薄い領域の化学構造を明らかにする表面分析法に用いられる測定機器の一つ。
大田 ゆかり氏による「群馬大・食健康センターにおける地域連携研究」
大田氏は有機化学や微生物学を始め、県産農畜産物の強みを判別しプラットフォームを構築するといった地域連携研究にも取り組んでいると言います。
「群馬県はいいものを出しているのに、あまり世間に周知されてない。」そのような背景から上州地鶏の“GアナライズPRチーム”※を作り、加熱による機能性成分の変化や咀嚼によるテクスチャー変化などを分析し、さらにこれを活かせる調理方法を考え企業に対し情報を提供しています。これをチームのリーダーである群馬県知事が、「温泉×上州地鶏」としてアピール。まさにフードサイエンスが農畜産業および企業に活気を与え、群馬県を盛り上げる産学官一体となった地域連携と言えるでしょう。
さらに地鶏のほか、レタスやきのこといった様々な農畜産物で研究を積み重ねていると言います。私たちは今後、その土地ならではの“食”を見るときにエビデンスを持ってニーズを満たせるかどうか判断していくことになるのかもしれません。

※GアナライズPRチーム:群馬県農畜産物を分析し成果を掲載することで、群馬の食が世界を目指し、群馬大学の新しい地域貢献のかたちを示すチーム。健康科学、食品開発、食品機能解析、食マネジメントの4つのユニットから構成され、参画機関には群馬大学と高崎健康福祉大学に加え群馬県、産業技術センター、農業技術センターが参画。
フードサイエンスを知ると、“食”が持つアプローチの複合性が見えてくる
最後に登壇者の裏出 令子氏は、“食”を複合的なアプローチとして捉えるフードサイエンスは研究者の立場から見ても非常に複雑で難しい分野であるとまとめました。
“食”の持つ可能性をひも解くには素材や機能性の知識に満足することなく、測定機器や食品工学などの幅広い“農芸化学分野”に関する研究について知ることも必要かもしれません。
とはいえ、バイオサイエンスやバイオテクノロジー領域は専門家でないと難しく感じる印象も。しかし、これらを駆使したフードサイエンスは私たちの“食”に直結するもので、その目的は多くの研究で共通し、人が“食”でより良い人生100年時代を迎えるということを願うものでしょう。
今回、様々な領域の研究者たちによる研究成果と産学官連携によるフードサイエンス研究の社会実装について学ぶことが出来ました。こうした異分野どうしの研究が横でつながって進展し、イノベーションを生み出していくのでしょう。
近い将来、私たちは食を通じてそれらと当たり前のように接する時代になるのかもしれない、そう感じさせた学会でした。