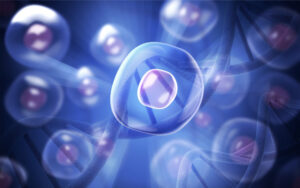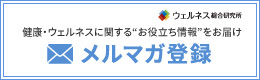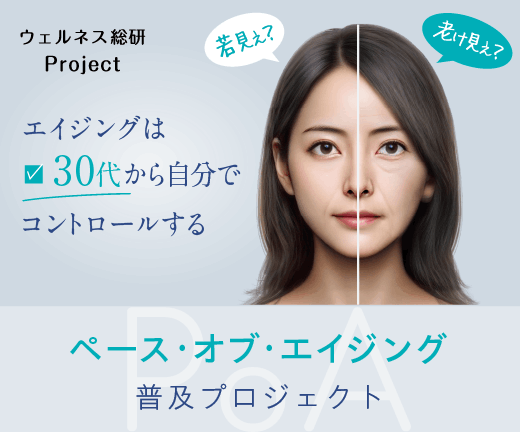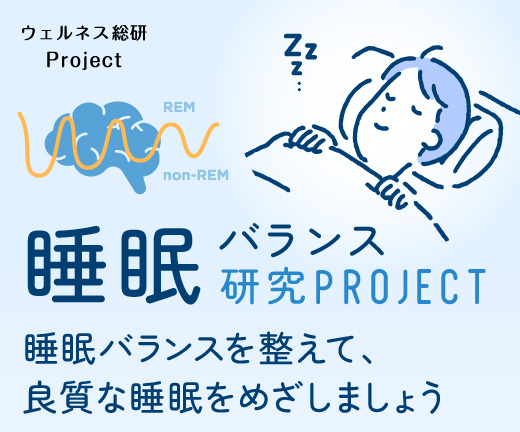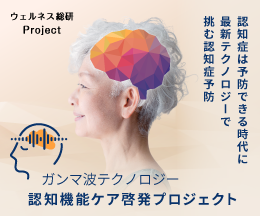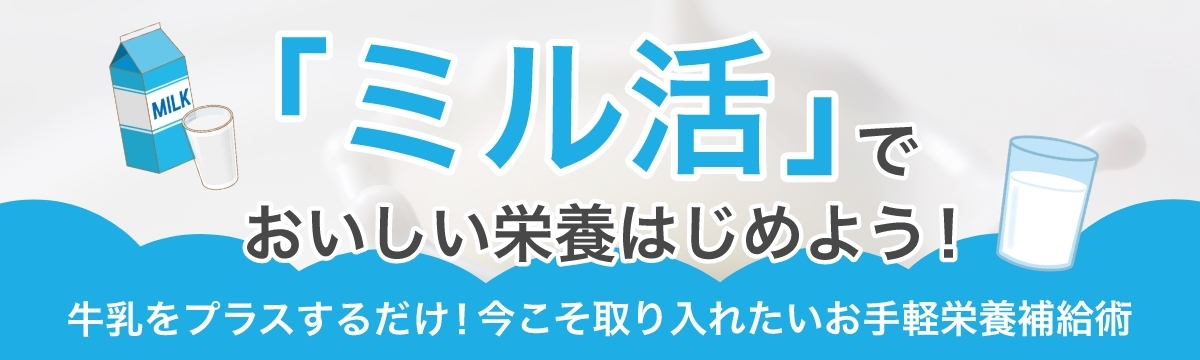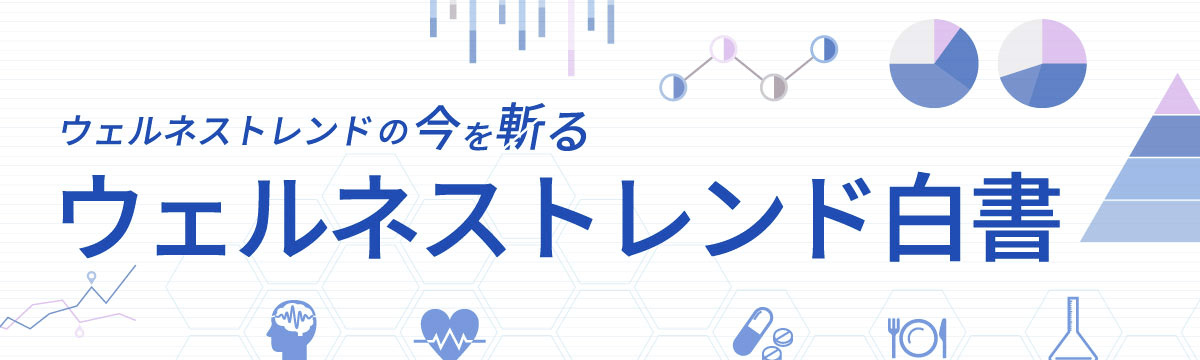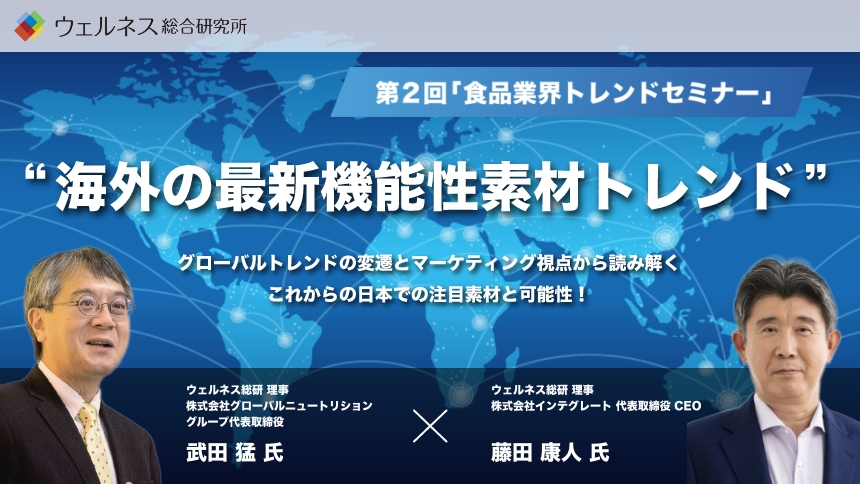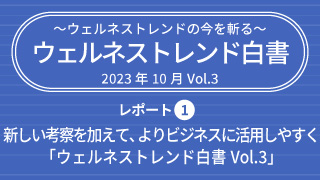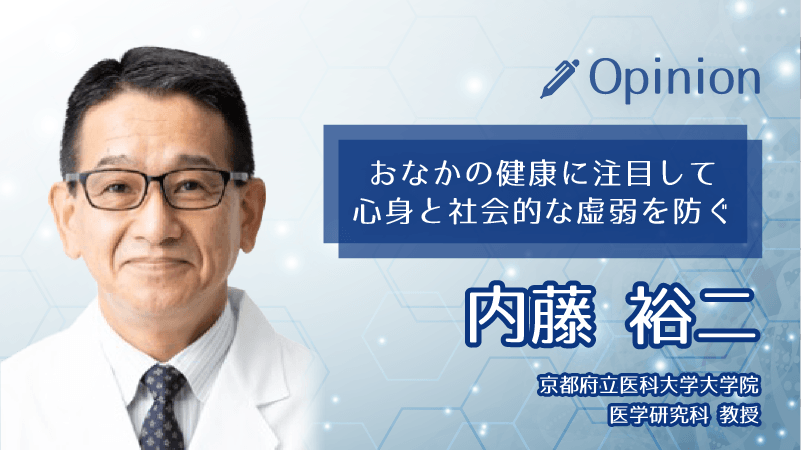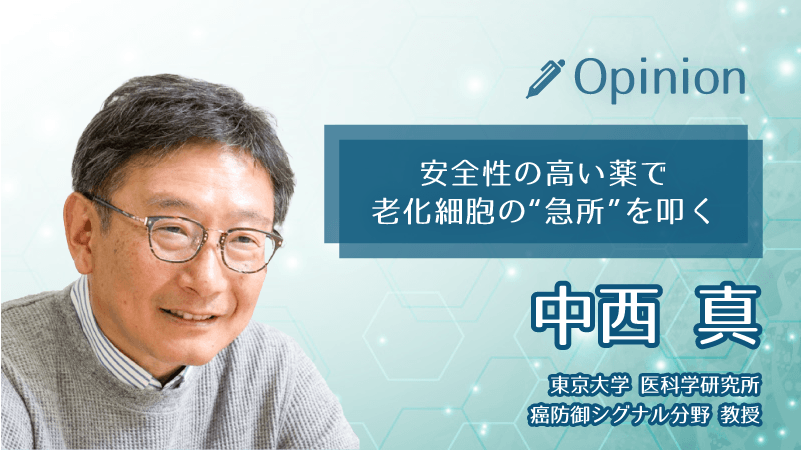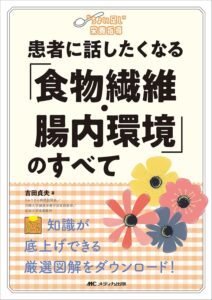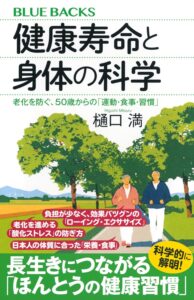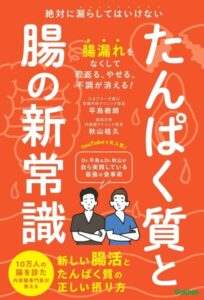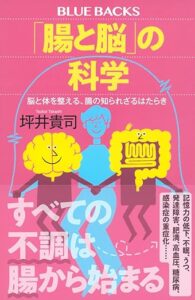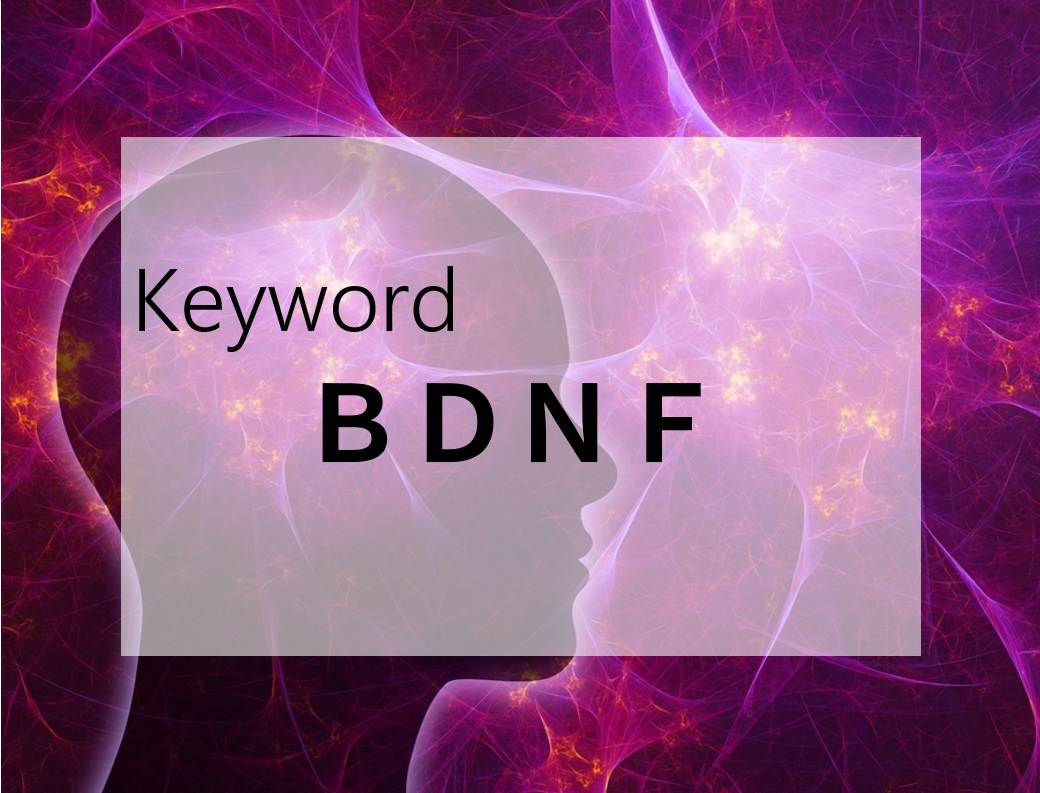
【注目書籍】「腸」と全身の臓器はおしゃべりをしている?

「脳腸相関」あるいは「腸脳相関」という言葉をよく聞くようになりました。「脳腸相関」は脳から腸へ情報を伝達する仕組み、「腸脳相関」は腸から脳へ情報を伝える仕組みだそうです。「腸から脳へ情報を伝達?」と、不思議に思った方も多いはず。腸は栄養を吸収し、残ったカスを排出する場所と長い間考えられてきたからです。
ところが、腸は全身のさまざまな臓器と情報のやりとりをしており、そのやりとりの結果が脳へ伝達されているとわかってきています。
また、マイクロバイオータ(腸内細菌)が私たちの体に及ぼす影響について、日々新しい研究結果が出ています。
本書『「腸と脳」の科学』(坪井貴司著/講談社ブルーバックス)の第1部では、なぜ腸と脳が連絡を取り合っていることがわかったのか、第2部では、腸と睡眠や記憶、精神疾患、発達障害、食欲、肥満などの関係が紹介されます。第3部では、著者の専門である生理学、神経科学の最新研究で明らかになってきた「脳腸相関の仕組み」や「腸と臓器との情報のやり取り」が示されています。
脳腸相関に興味のある方だけでなく、いつまでも健康でいたいと考えている方々へおすすめの1冊です。
腸は、生命機能の維持に欠かせない「第二の脳」

緊張したりストレスを感じている時、便が緩くなったことはありませんか? その原因の一つとして、ストレスなどを感じると、脳の視床下部からホルモンが分泌され、それが副交感神経に作用することで腸の動きが活発になり、下痢を引き起こすという、脳腸相関が考えられます。
腸の蠕動運動は腸管神経系によって独立して調整されており、私たちが自分の意思で自由に止めたり動かしたりはできません。そこで腸の機能を調整するために、脳は迷走神経を介して腸管神経系に指令を与え、腸の機能を促進するシグナルを、交感神経を介して腸の機能を抑制するシグナルを伝達しているのです。
その腸管神経系は、腸管壁に網目状にあり、脳からの命令を受けなくても機能できる独自の神経ネットワーク(神経回路)を築いています。そして複雑な腸の運動、腸内分泌細胞からのホルモンの分泌、腸管の血流調整などを行います。そのため腸は「第二の脳」とも呼ばれるのです。
また、お腹が空いた、満腹だといった腸から脳への伝達は、求心性迷走神経(内臓感覚神経)や腸内分泌細胞が分泌する消化管ホルモンによって行われます。
つまり、脳は視床下部から分泌するホルモンや遠心性迷走神経を介して腸の機能を調整し、腸は腸内分泌細胞から分泌する消化管ホルモンや、腸から脳へつながっている求心性迷走神経を介して脳へ情報を伝えているわけです。
遠心性とは、脳から離れる方向に情報が伝達するため、求心性とは、中枢である脳へ情報が向かうためにこう呼ばれるそうです。
腸と脳の間の情報伝達を担うものとして、現在わかっているものは、
① 脳から腸へ情報を伝達する遠心性迷走神経
② 腸から脳へ情報を伝達する求心性迷走神経
③ 脳の視床下部から分泌される各種ホルモンや、腸内分泌細胞が分泌する消化管ホルモン
④ 腸内マイクロバイオータ(腸内細菌)
があるそうです。
腸から脳への情報伝達には腸内マイクロバイオータ(腸内細菌)が活躍
近年の研究で、腸内マイクロバイオータ(腸内細菌)が産生する多様な代謝物が、脳と双方向の情報のやり取りを行なっていることが明らかになりつつあります。そしてこのような経路は「腸内マクロバイオータ━腸━脳相関」と呼ばれ、腸内マクロバイオータは、脳腸相関を調整する隠れた臓器とも考えられます。
また、腸内マイクロバイオータの組成が変化することで、全身の代謝や免疫、さらに行動なども変化するのではないかという研究が行われているのだとか。
私たちが毎日口にしている食事やおやつなどには、たくさんの栄養素や食物繊維など、多様な種類の物質が含まれています。それらは腸で吸収され、私たちの体を作り、エネルギーとなり、生体活動を続けることができます。その食事の内容やストレス、睡眠などの生活習慣が、腸内マイクロバイオータの組成に関わり、私たちの健康に大きく影響しているのです。
本書では、腸と睡眠の関係、腸と記憶力の関係、腸と神経疾患の関係、腸と発達障害・精神疾患の関係、腸と食欲・肥満の関係などについての研究が紹介され、それぞれのメカニズムが説明されています。
マイクロバイオータ(腸内細菌)が産生する代謝物の「短鎖脂肪酸」は、食欲を調節したり肥満を予防したりするのはよく知られていますが、認知症やパーキンソン病、うつ病などとの関係も研究中とか。近年では、長鎖脂肪酸も脳腸相関を介して、食欲や肥満に関与していることがわかってきたそうです。
マイクロバイオータ(腸内細菌)が産生する代謝物は、腸から中枢神経や視床下部に作用し、私たちの健康や長寿などにも関わってくるわけです。
腸からのメッセージは他臓器へも伝わる

消化管には、消化管ホルモンを産生して分泌する腸内分泌細胞があります。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授である著者の研究室では、その腸内分泌細胞に、腸内の物質を感知する味覚受容体や、リゾリン脂質を感知する受容体、塩基性アミノ酸を感知する受容体など、さまざまな受容体が発現しているとわかっているそうです。
まるで、舌の味蕾が腐った食べ物を見分けて吐き出すように、腸内代謝物や食事に含まれる物質が毒であった場合、それらの受容体が感じた“味”の情報は素早く脳へ伝達され、下痢が起こります。腸内分泌細胞にあるそれらの受容体は、腸内に入ってきた物質を見極める働きがあるのです。
驚いたことに、肺の線毛上皮細胞にも、腸内分泌細胞と同様に“味”を感じる味覚受容体が発現しているそうです。それらは空気中に無数に存在するウイルスや細菌、真菌などを感知し、飲み込まれるか痰として体外へ吐き出されます。
肺にある別の情報伝達経路を発見した研究もあります。まず、肺炎を起こすウイルスに感染させたマウスに、食物繊維を多く含む食事や酢酸を経口投与します。すると上皮細胞において、肺炎の症状が軽減しました。次に、短鎖脂肪酸受容体の一つが欠損したマウスに、同様に食物繊維を多く含む食事や酢酸を経口投与しましたが、肺炎の症状は軽減されなかったそうです。
そのように、腸と肺の「腸肺相関」、腸と肝臓の「腸肝相関」、腸と肝臓と脳と腸の「腸肝脳腸相関」、腸と腎臓の「腸腎相関」などがあることがどんどんわかってきています。
驚くのが、腸と筋肉の「腸筋相関」もあることです。走る、呼吸をする、話すなどの自分の意思で動かすことができる骨格筋は、さまざまな生理活性を持った物質「マイオカイン」を分泌し、それによって腸や脳、全身の臓器や組織と情報をやり取りしているそうです。
そのマイオカインの中のSPARC(secreted protein acidic and rich in cysteine)は、骨格筋から分泌された後、大腸で発生したがん細胞に作用して、がん細胞を自死(アポトーシス)に導いていることが報告されています。
ヒポクラテスは、「すべての病気は腸から始まる」「病気は食事療法と運動によって治療できる」という言葉を残していますが、紀元前5世紀に発せられたこの言葉が、いまやどんどん立証されていっているのです。
腸の最新研究を紐解きながら、腸と全身にある臓器や組織とのおしゃべりを紹介している本書。ちょっとのぞいてみませんか?

【書籍情報】
『「腸と脳」の科学』(坪井貴司著/講談社ブルーバックス)