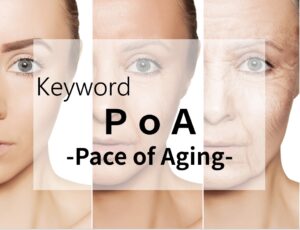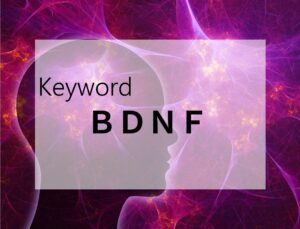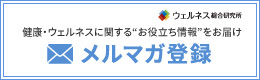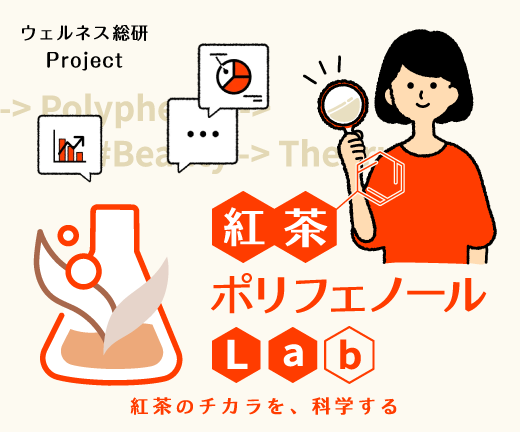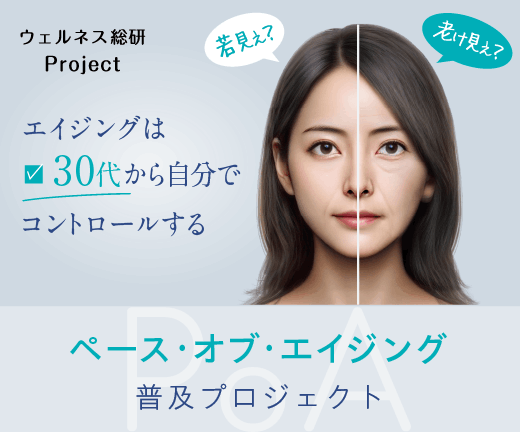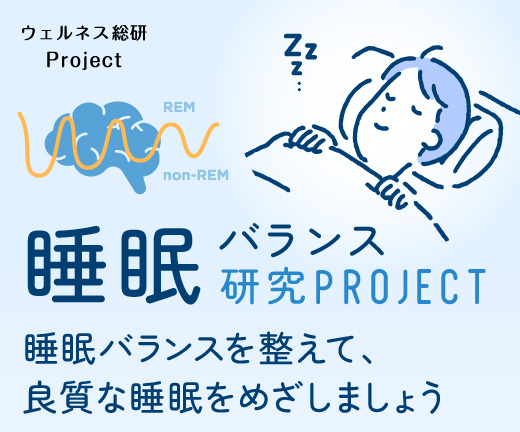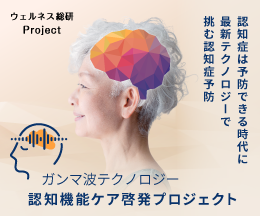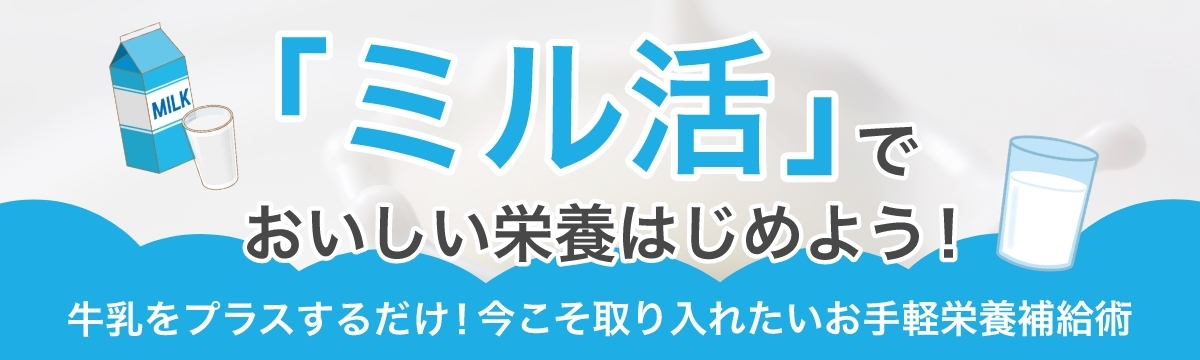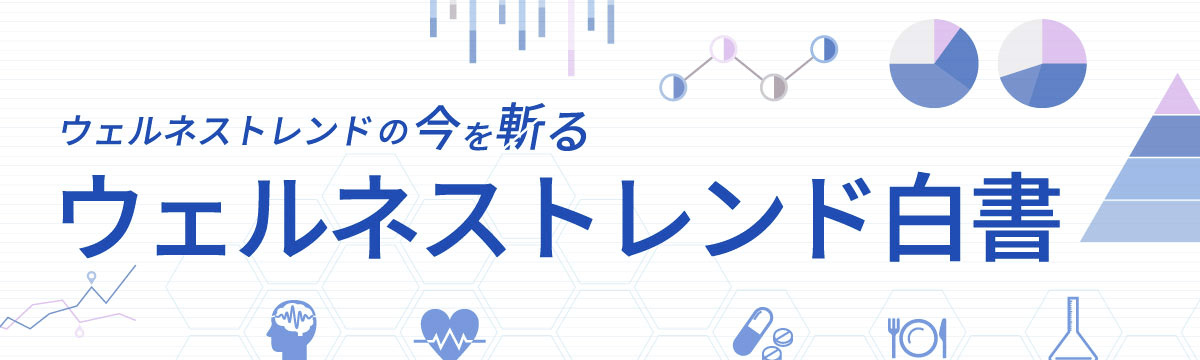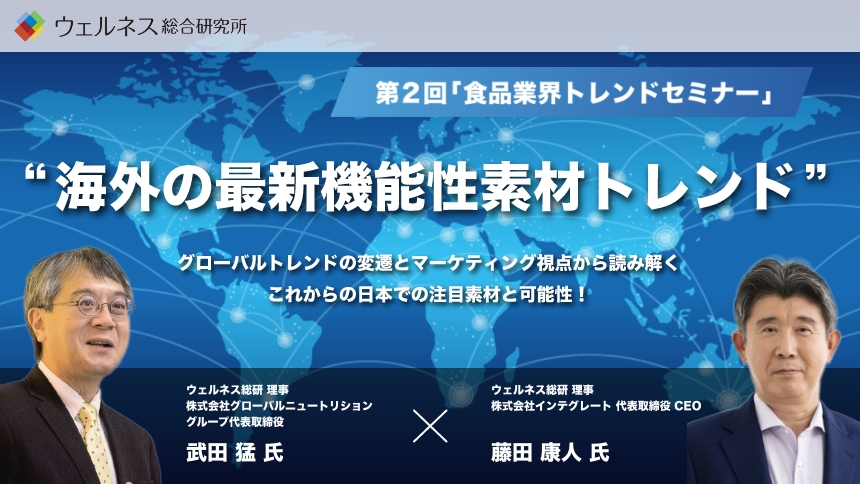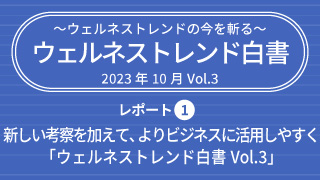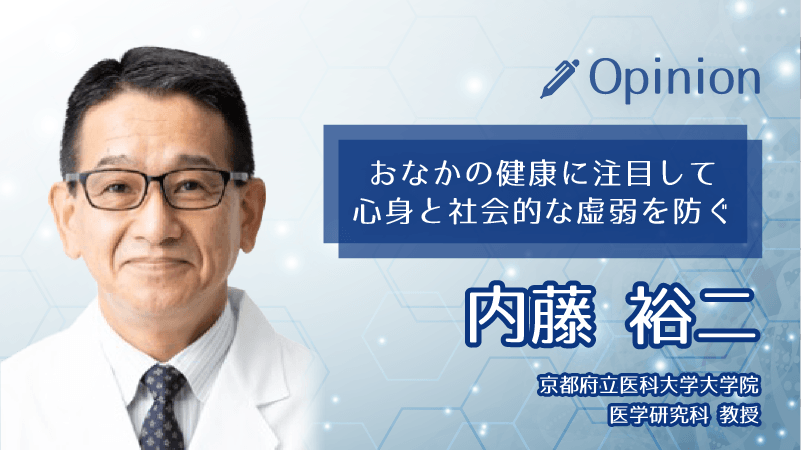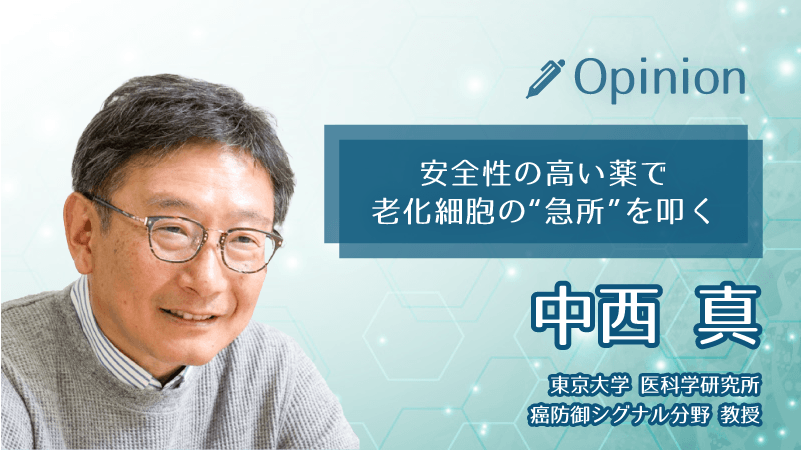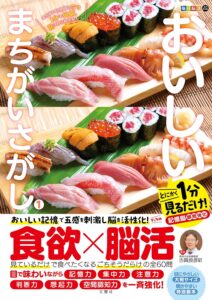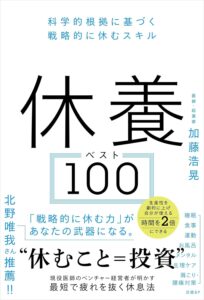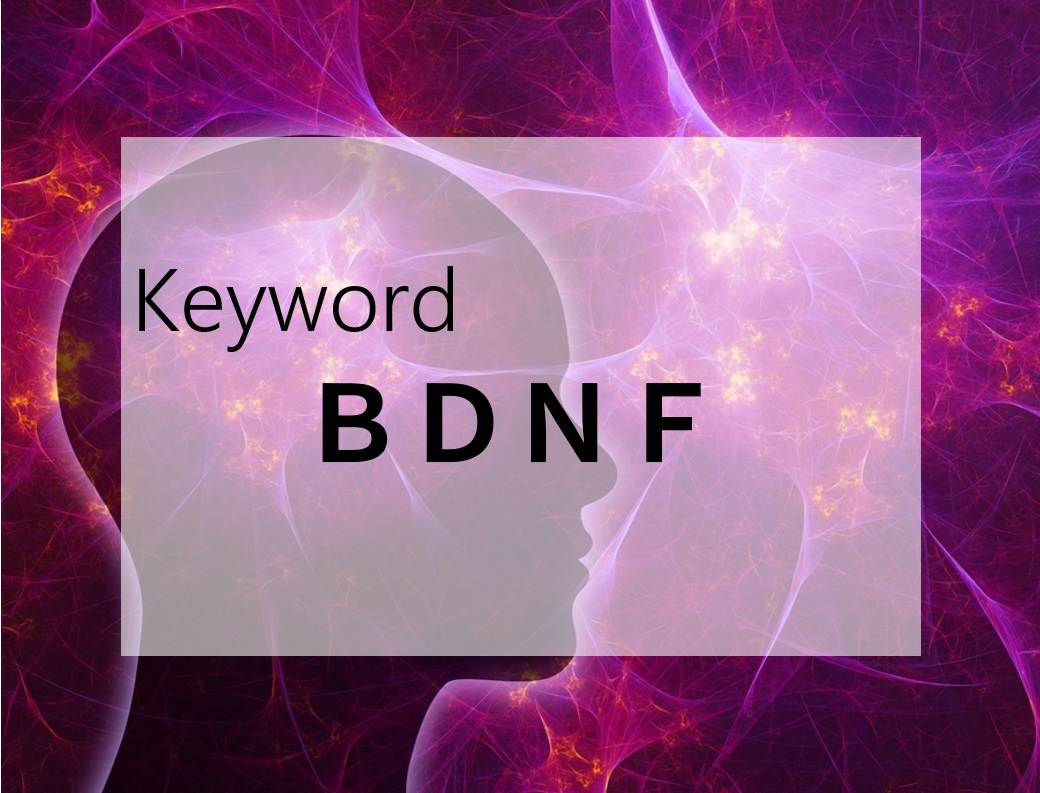
“老け顔”の真因「カルバミル化」 老化指標として期待が高まる
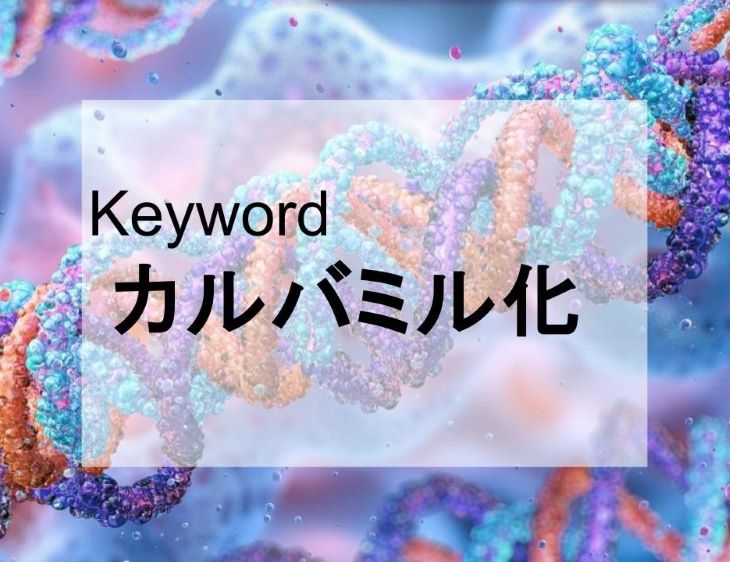
皮膚がたるむ真の原因としても話題になっているカルバミル化は、多くの分野で注目されています。カルバミル化が注目される理由や、カルバミル化の原因、そして防ぎ方について解説します。
カルバミル化とは? いま注目される理由
カルバミル化とは、体内の尿素が分解されて生じるイソシアン酸(シアン酸の一形態)がタンパク質と結合し、タンパク質を劣化させる反応です。
その発見は1960年代、George R. Starkら(米国)による研究に始まります。その後、1970年代には鎌状赤血球症※の治療を受けた患者で、カルバミル化された水晶体タンパク質が見つかり、白内障との関連が示されたことから、その有害性が明らかになりました。
※鎌状赤血球症:先天性疾患のひとつで、ヘモグロビンの遺伝子異常から生じる、鎌状(三日月形)の赤血球と赤血球の過剰な破壊による慢性貧血が特徴。
カルバミル化されたタンパク質の機能は変化し、分子レベルでの老化が進行します。特に、寿命の長い細胞外マトリックスタンパク質※に蓄積しやすく、皮膚の真皮にあるコラーゲンやエラスチンはその代表例です。これらタンパク質の機能低下は、シワやたるみとして見た目に現れるため、エイジングケアの分野では「酸化」「糖化」に続く、第3の“老け顔”につながる老化マーカーとして注目を集めています。
※細胞外マトリックスタンパク質:細胞の周りに形成される線維状または網目状の構造体の総称で、細胞間や組織間の隙間を埋める構造物であるほか、細胞機能制御因子としての役割なども担う。
カルバミル化したコラーゲンでは分子同士をつなぎとめる架橋の形成が阻害され、柔らかく崩れたゲルになってしまうことから、「酸化=サビる」「糖化=コゲる」と並んで、カルバミル化は「溶ける」と表現されることもあります。
さらには皮膚だけでなく、血管石灰化を増悪させることも明らかになり、その濃度は生命予後に影響する可能性があると報告されています。これには、ミトコンドリアタンパクの酵素(ATP合成酵素)におけるカルバミル化が関与し、ミトコンドリア酸化ストレスによって血管の石灰化を防ぐ因子の発現が間接的に抑制されるために引き起こされます。このように、カルバミル化は現在、多岐にわたる分野で注目を集めている化学反応の一種です。
カルバミル化が新たな老化指標に
カルバミル化されたタンパク質の蓄積速度と寿命は、逆相関することが分かっています。皮膚でカルバミル化が起こっているということは、血管や脳、心臓などほかの組織にも生じている可能性が否定できません。
一方、糖化はこれまで十分に解明されており、加齢による組織へのAGEs(終末糖化産物)蓄積のプロセスに加え、糖尿病の合併症への寄与なども明らかになっています。糖化率が年齢の関数として増加することが示されている中で、カルバミル化も今後、こうした加齢関連疾患の特徴の一つとして捉えられるようになる可能性は十分にあります。
カルバミル化の原因と防ぎ方
一般に、生体内におけるシアン酸塩の量は多くないため、生理的条件下でカルバミル化が進行することはありません。一方、炎症部位ではカルバミル化が起こりやすくなります。特に、喫煙者ではこのチオシアン酸塩が高い傾向です。そのほか、環境中の大気に含まれる窒素も一因と考えられています。
したがってカルバミル化は、病気により二次的に生じる場合を除き、炎症、酸化ストレス、喫煙、大気中の窒素量、通常量を上回る尿素源(タンパク質)の摂取などが原因となって起こりやすくなると言えるでしょう。
排泄を担う腎臓や代謝を担う肝臓の機能が低下している場合や、高タンパク食の摂取後、激しい運動後では血液中の尿素が高くなります。
しかし、現状ではカルバミル化の視点を含め、タンパク質の摂取制限をすることは推奨されていません。これは、許容上限量を設定し得る明確な根拠となる報告がないからです。一方で、タンパク質を十分に摂取することは、フレイル予防や血圧の低下など多くのメリットが報告されています。
健康な人がカルバミル化を防ぐには、喫煙を控え、適度な水分補給によって尿素を体外に排出すること。また、タンパク質の過剰摂取を避けたい場合は、1日における推定エネルギー必要量の20%くらいまでを目安にしましょう。
これは、30歳から49歳の身体活動レベルⅡに該当する男性で考えると、1日あたり135gまでのタンパク質を摂取しても差し支えないということになります。
1日あたり135gのタンパク質は、肉や魚にするとおよそ600〜700gに相当しますので、食事から摂る分にはそれほど注意しなくても問題ありませんが、プロテインパウダーなどで補う場合は気を付けるとよいでしょう。
化粧品分野ではすでに「抗カルバミル化成分」を訴求した製品が市場に出ており、食品領域での展開も期待されます。