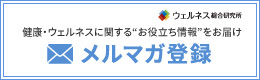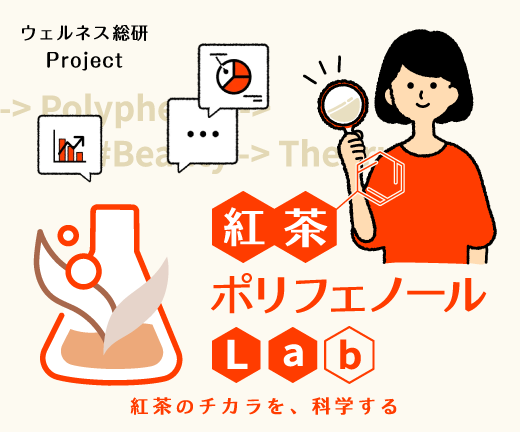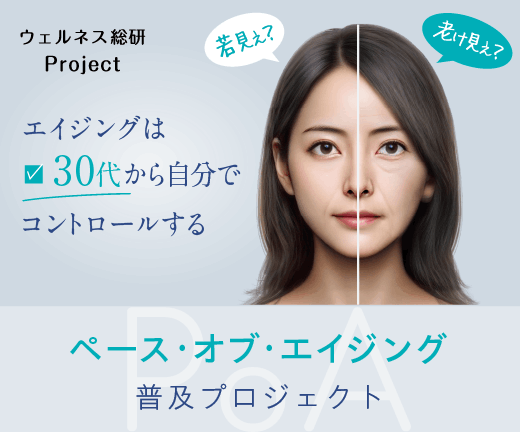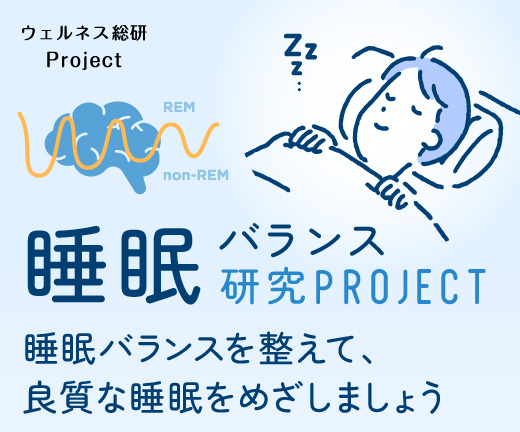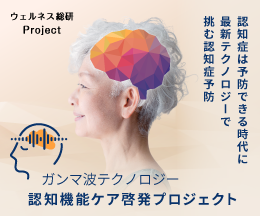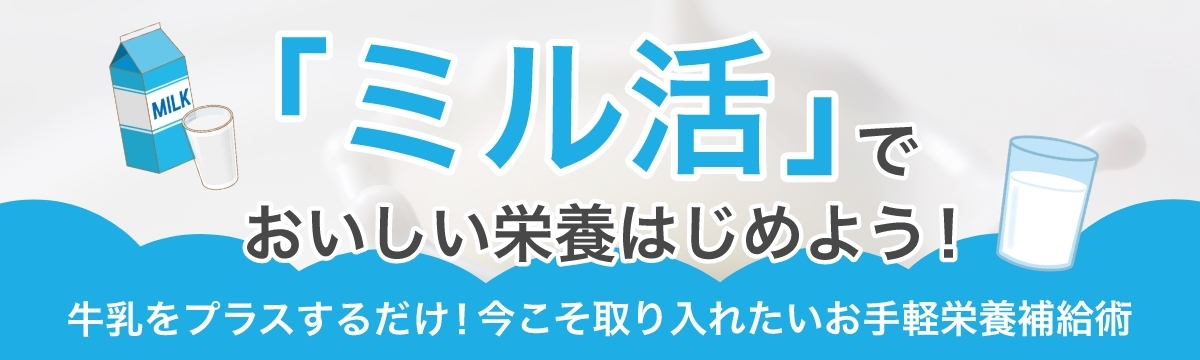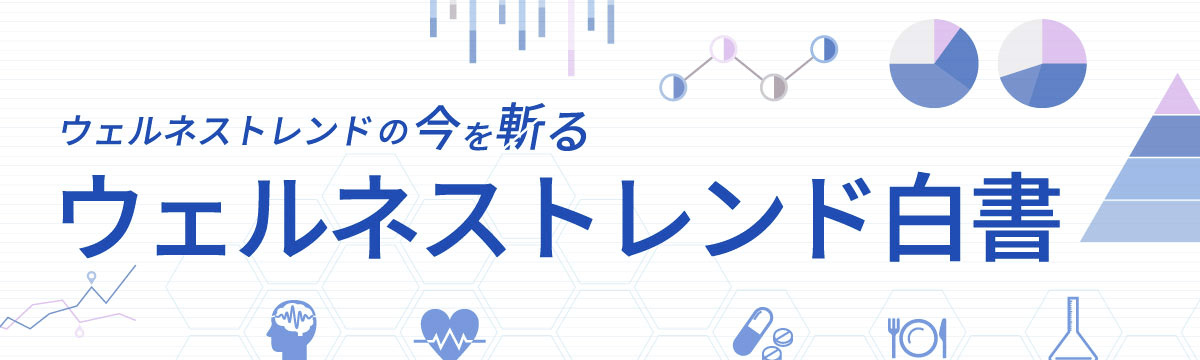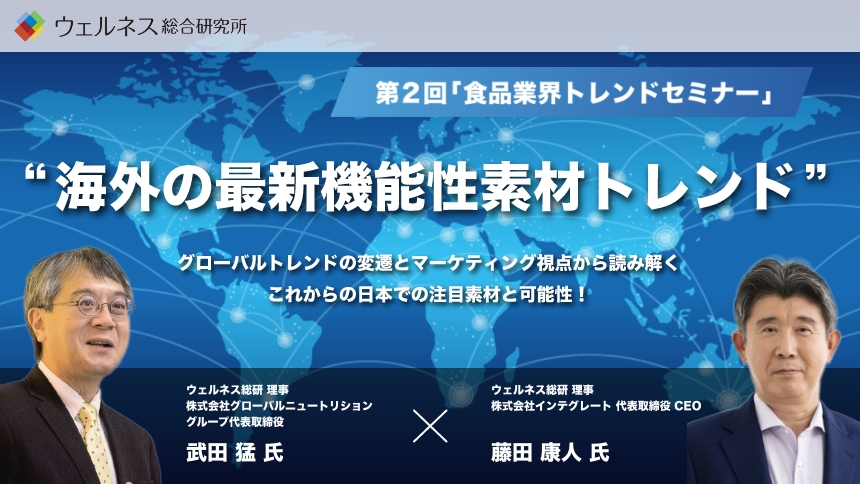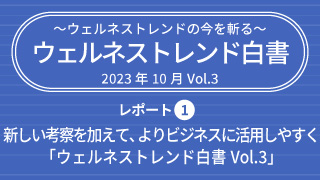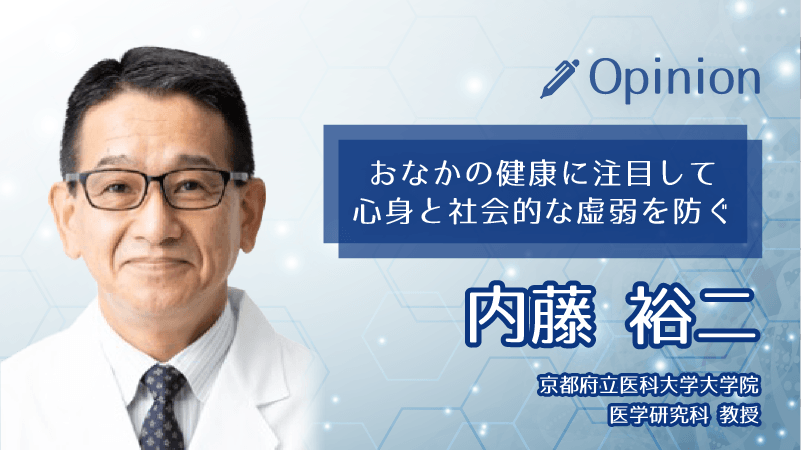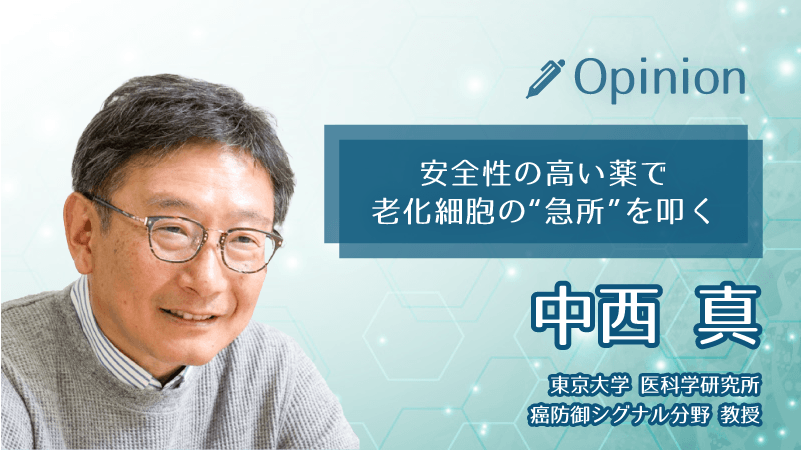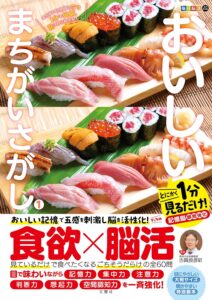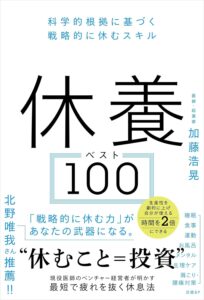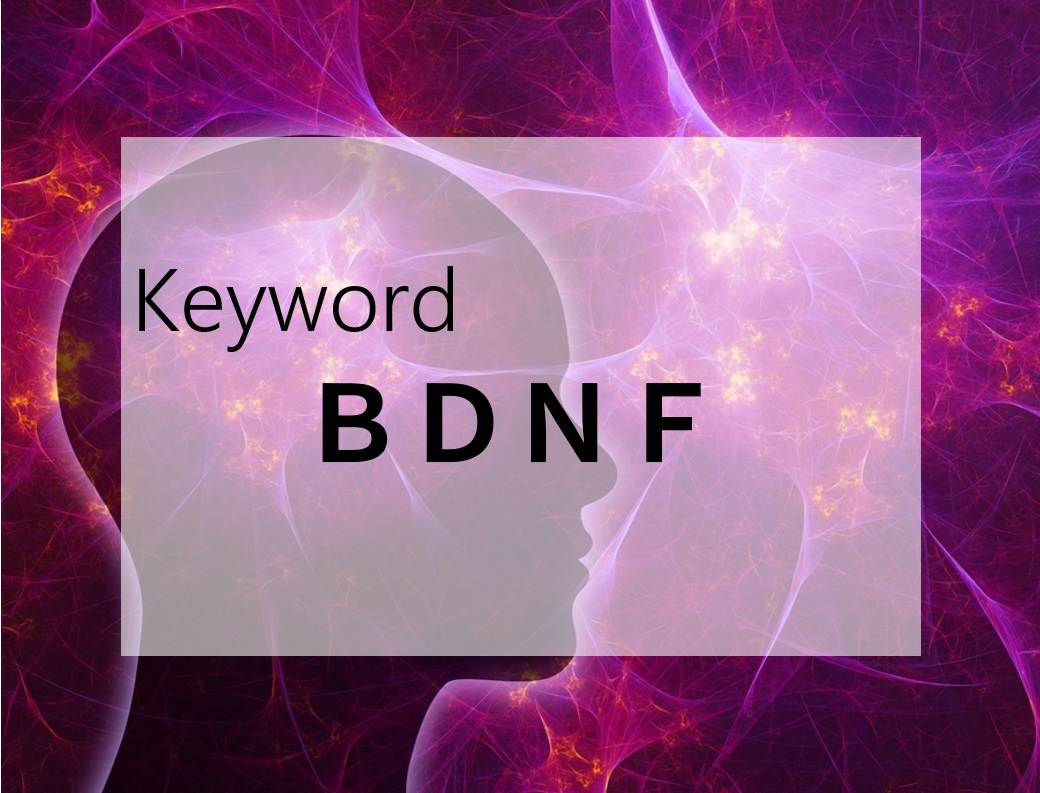
第18回セラミド研究会学術集会を開催
セラミド研究会(木原章雄会長・北海道大学大学院)は、9月4日、5日の2日間にわたり、北海道大学学術交流会館において、第18回セラミド研究会を開催し、約60名が参集した。プログラムは、台湾からの招待講演1題、国内招待講演5題、一般講演15題で構成され、活発な討議が繰り広げられた。Young Investigator Awardには小嶋あゆみ氏(北海道大学薬学部)、秋山史成氏(大正製薬)が受賞した。
国内招待講演では、東京都医学総合研究所の平林哲也氏が「アシルセラミド代謝を基盤とした皮膚バリア形成と炎症応答」と題し、アシルセラミド代謝経路に関わるこれまでの研究成果を紹介。皮膚の最外層である角質層は、外界からの異物侵入や体内水分の喪失を防ぐバリア機能を備え、この機能が障害されると先天性魚鱗癬やアトピー性皮膚炎などの原因となる。透過性バリア機能には、ラメラ構造をもつ角質細胞間脂質と、それを角化細胞の周辺帯(CE)の表面に共有結合する一層の脂質層「CLE(corneocyte lipid envelope)」が不可欠である。研究チームは、ω-O-アシルセラミドの生合成とCLE形成に関わる2つの酵素PNPLA1とSDR9C7の 機能を明らかにする過程で前者の欠損マウスでのみ炎症応答が生じることを見出し、この違いが生じる分子機序の解明を進める。
また佐賀大学の光武進氏は「スフィンゴ脂質の摂取が生体に与える影響」について、スフィンゴ脂質と受容体の相互作用に焦点を当て、スフィンゴ脂質が生理機能を発揮する可能性のあるメカニズムについて解説。生体内でスフィンゴ脂質が生理機能を発揮する可能性のあるメカニズムとして、フィトスフィンゴシン(PHS)と長鎖脂肪酸受容体FFAR4の相互作用、米ぬか由来の新規糖脂質(6-アシルグルコシルセラミド)とマクロファージ誘導性C型レクチン受容体Mincleの相互作用を示し、またマウスの小腸内分泌細胞株STC-1を用いた試験から、PHSの摂取が血糖値制御や肥満予防に役立つ可能性を示唆した。
続いて長崎大学熱帯医学研究所の見市文香氏が「腸管寄生虫 “赤痢アメーバ” が合成する超長鎖ジヒドロセラミドの役割」について講演。同研究チームは、赤痢アメーバのシスト形成モデルであるEntamoebainvadensを用い、シスト形成過程で変動する脂質の網羅解析を実施。シスト形成に伴い、セラミド量が増加し、特に他種生物ではほとんど検出されない超長鎖(炭素数26-30)ジヒドロセラミド量が増大することを確認した。さらに超長鎖ジヒドロセラミドがもつ超長鎖アシル基は、赤痢アメーバ自身が脂肪酸伸長サイクルによって合成することも突き止めた。現在超長鎖ジヒドロセラミドの成熟シストにおける局在について解析を進めており、これまでに得られた知見について紹介した。
明治の森藤雅史氏は、「スフィンゴミエリン含有食品の実用化とその評価マーカーの臨床への応用」、東北医科薬科大学分子生体膜研究所の稲森啓一郎氏が「セラミド構造の多様性に基づくスフィンゴ糖脂質によるTLR4活性化制御」について講演を行った。また2024年、同研究会功労賞を受賞した大阪大学大学院理学研究科附属フォアフロント研究センターの井ノ口仁一氏は、「ガングリオシドGM3の生物学 過去・現在・未来」と題し、ガングリオシドGM3に関連するこれまでの研究成果を紹介。ガングリオシドGM3の生理活性がアシル鎖構造によって制御され、その分子種多様性の中に自然免疫受容体TLR4などの活性化を正負両方に制御する機能を持つことなどを示した。次回の第19回学術集会は、2026年9月に甲南大学(神戸)での開催を予定している。
「FOOD STYLE 21」2025年10月号 F’s eyeより