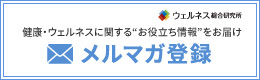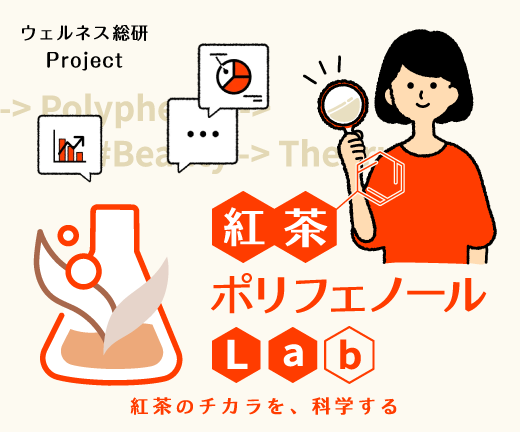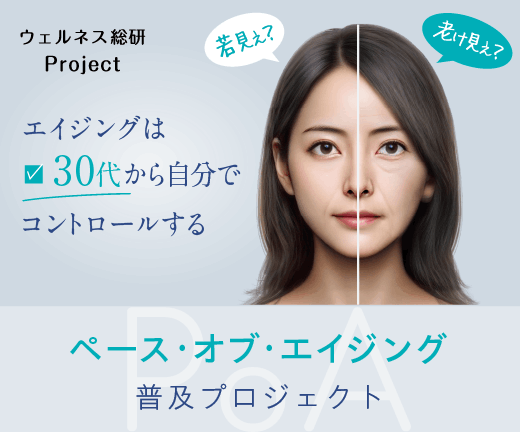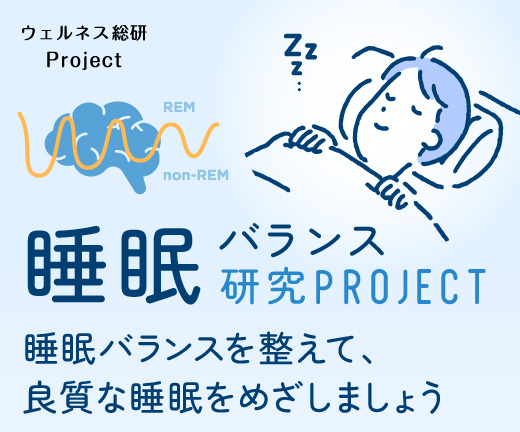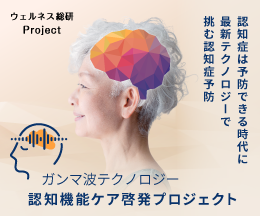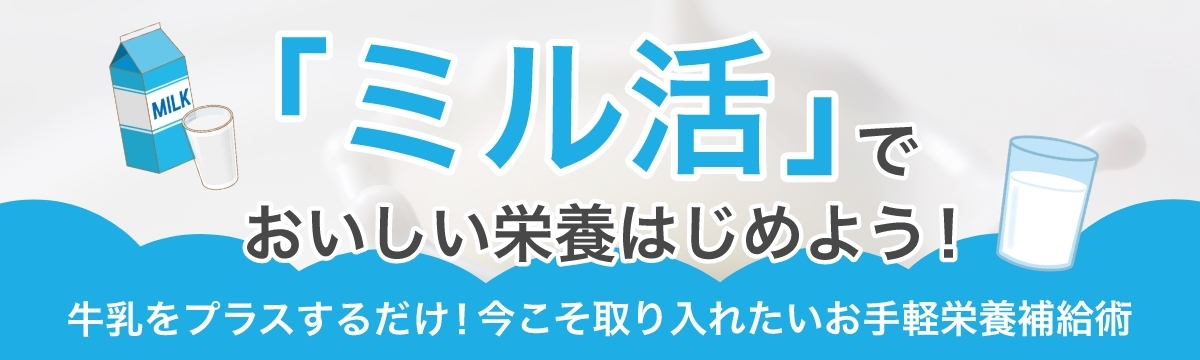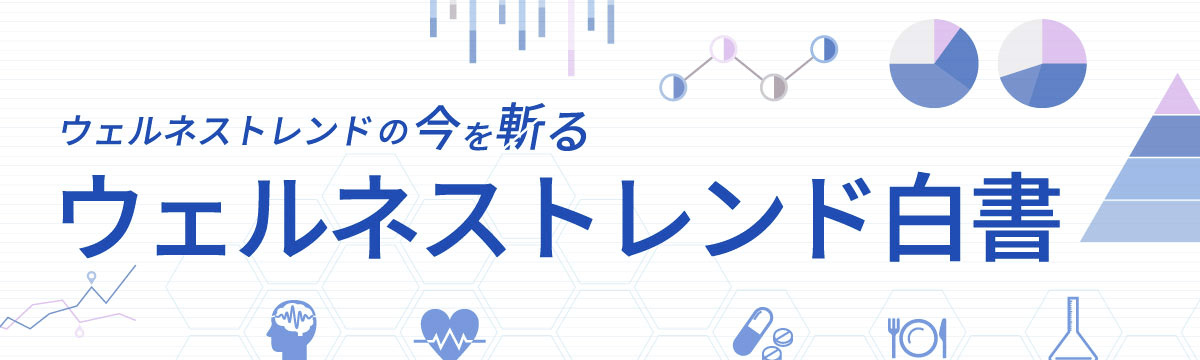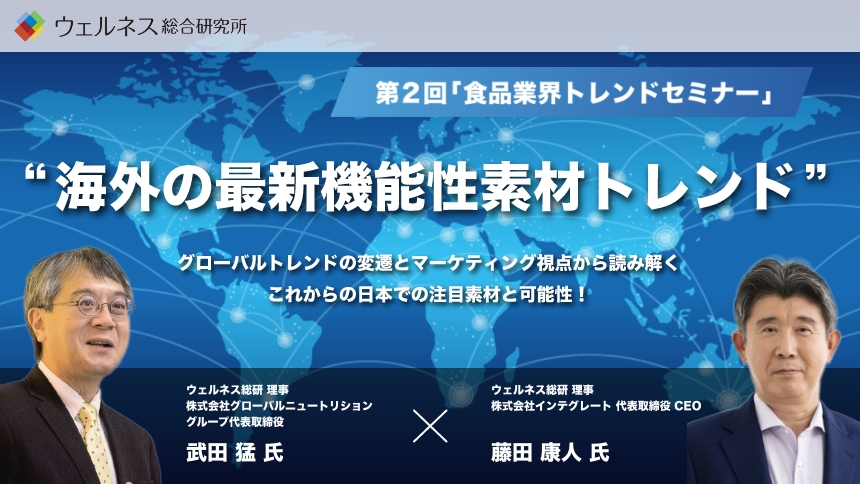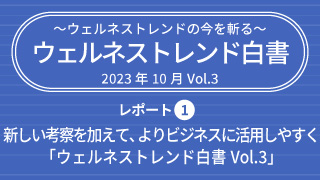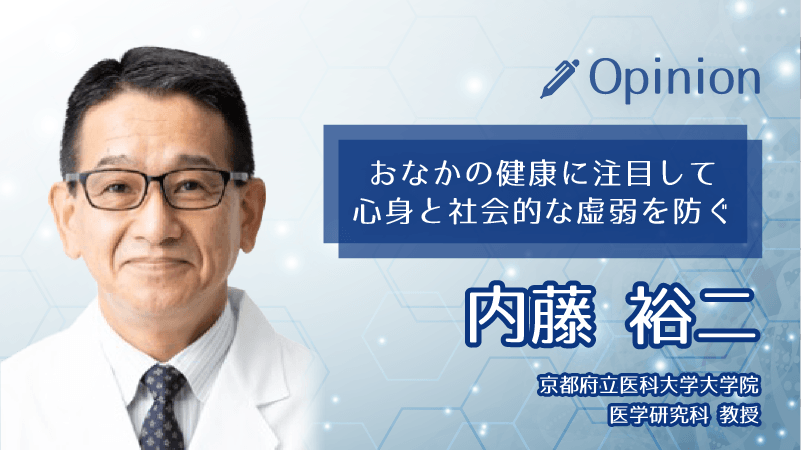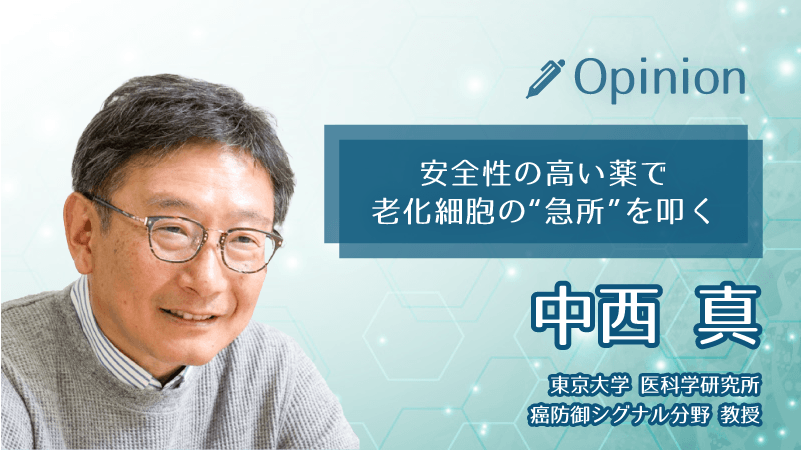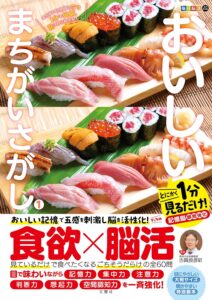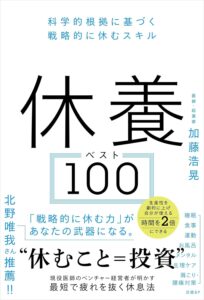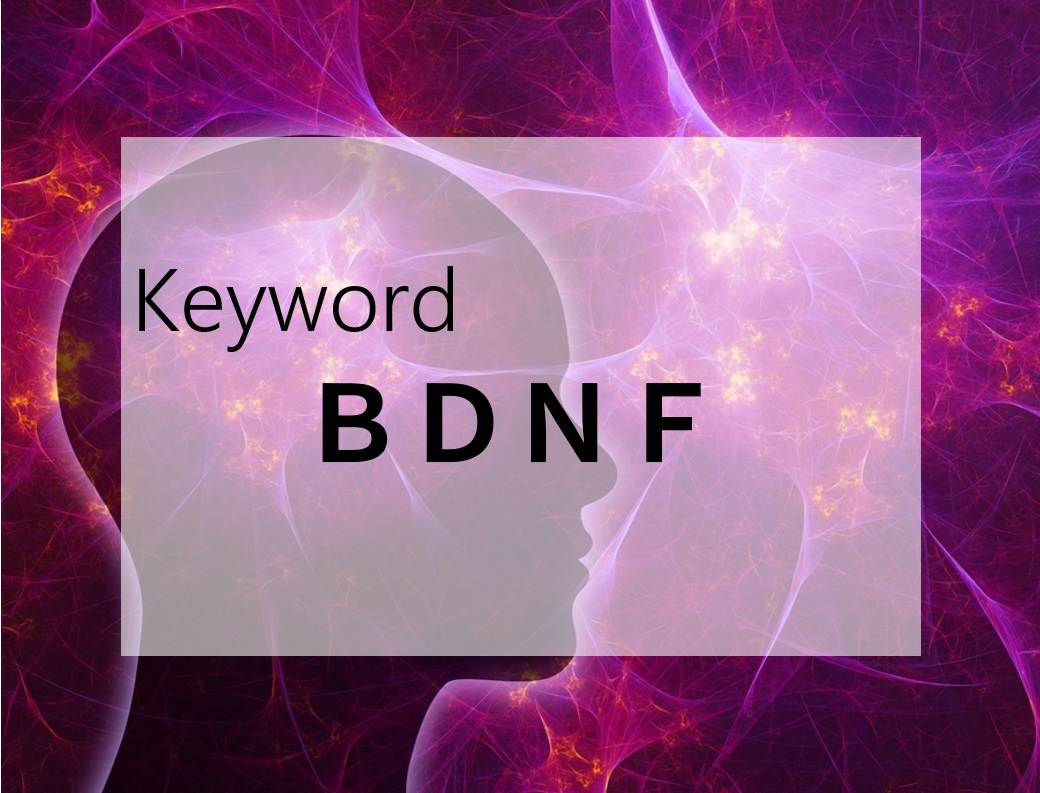
サプリ法の制定と機能性表示制度の廃止
最近、日本弁護士連合会がサプリメント法の制定を提唱する一方で、関東弁護士会連合会は、機能性表示食品制度を廃止する意見書を発表し、健食業界に波紋を広げている。
日本弁護士連合会は7月17日、「サプリメント食品に関する法規制の早急な整備を求める意見」を取りまとめ、18日には福岡資麿厚労大臣、伊東良孝内閣特命大臣(消費者および食品安全)、堀井奈津子消費者庁長官に提出した。意見書の趣旨は、サプリメント食品の製造、販売、品質管理および広告を規制する法律を制定すべきとし、①サプリメント食品の製造を業として行う場合およびサプリメント食品の原材料の製造を業として行う場合は、営業許可を要するものとすること②サプリメント食品および同食品の原材料の製造については、監督官庁が定める最新のGMP基準に適合していることを義務付けること③サプリメント食品を販売に供する場合は、当該製品に係る表示内容についての許可を要することにすること④サプリメント食品の表示許可を得た業者に対して、当該サプリメント食品に係る健康被害情報の提供および公表を義務付けること⑤サプリメント食品について、何人もその効果または機能に関して、明示的か暗示的かを問わず、虚偽または誇大広告をしてはならないことを明記すること⑥サプリメント食品の過剰摂取等を防止し、健康的な食生活等の健康維持・増進に関する知識の向上を図るための注意喚起および啓発活動の充実を関連省庁および地方公共団体に求めることと6項目を挙げて要求している。意見書は、それぞれ要求事項の理由や意見も述べられており、新しくサプリメント法を制定してさらに規制強化をしようという内容である。リスク管理重視のしすぎや消費者の選択を軽視しているなどの声が聞こえる。サプリメント法の新たな制定は、機能性表示食品制度が存在しない時代(2015年4月以前)であれば、業界がサプリメント法を渇望していた時期があるが、機能性表示食品制度が存在する現時点では、業界でも賛否両論が存在し、一概には言えないところがある。
一方、関東弁護士会連合会は7月22日、「機能性表示食品に関する意見書」を発表、厚労大臣や消費者委員会委員長に提出した。機能性表示食品制度の廃止を主張する意見書で、同連合会は2019年3月にも同様の意見書を提出しており、今回で二度目。今回の内容は、意見の趣旨として①機能性表示食品制度については、廃止すべきである②仮に機能性表示食品の制度を廃止できない場合であっても、食品の安全性を確保し、機能性の科学的根拠が十分合理的と評価できるものに限定するように必要な措置を講じるほか、機能性表示食品の表示についても、適格消費者団体の差止請求権の対象とすべきである、と記述されている。意見の理由には、さくらフォレスト問題の科学的根拠のことや買上調査による製品不備の指摘、小林製薬事案の健康被害と安全性、消費者の認知度が低いままという課題、食品表示基準を改正しても問題点が解消されてないこと等々を取り上げて廃止の理由を述べるとともに、廃止しない場合の措置も提言している。
機能性表示食品制度は2015年4月にスタートしてから2025年4月で10周年を迎えた。当初の消費者庁の通知ガイドラインによる運用から、今では法令化され運用のレベルアップが図られている。最近はPRISMA2020の準拠、GMP義務化(2026年9月の施行)、健康被害情報収集のシステム化等々を行うことで、10年前とは比べられないほど科学的根拠も製造ラインも進化を成し遂げている。機能性表示食品制度が総じて健食の質の向上に寄与していることは誰にも否定できないだろう。
「FOOD STYLE 21」2025年9月号 F’s eyeより