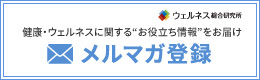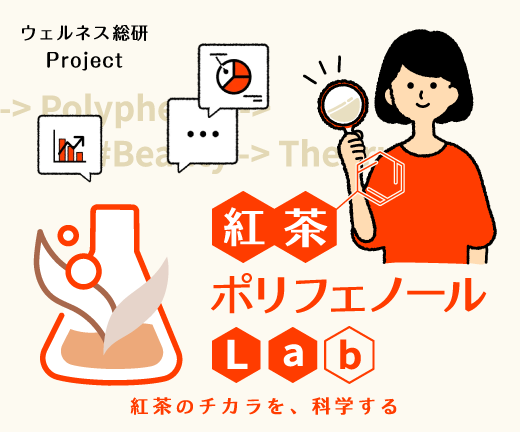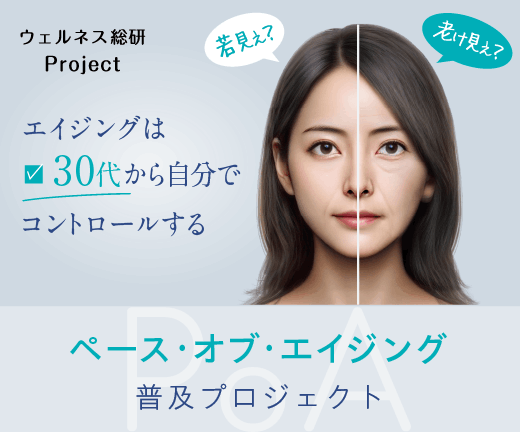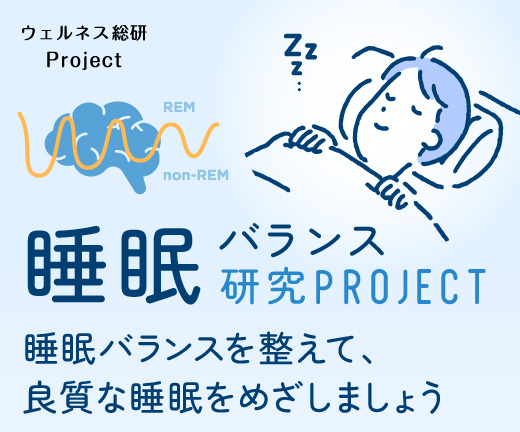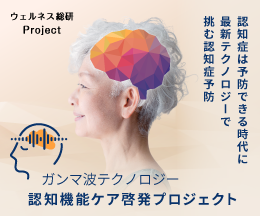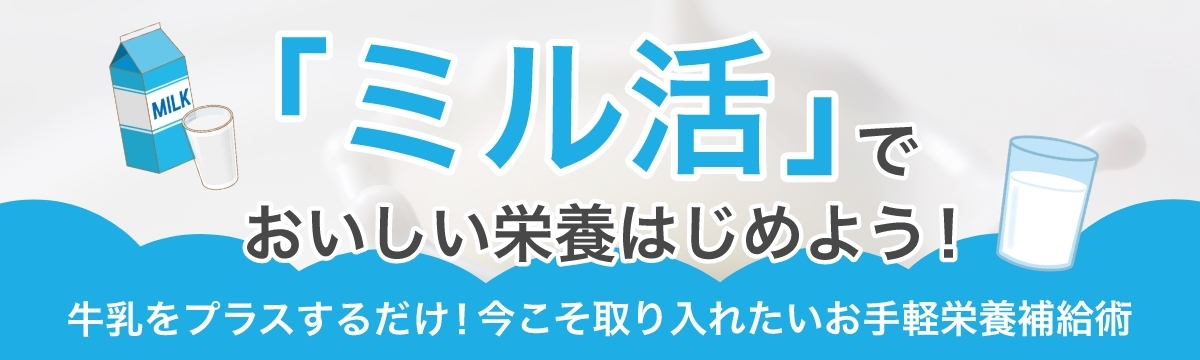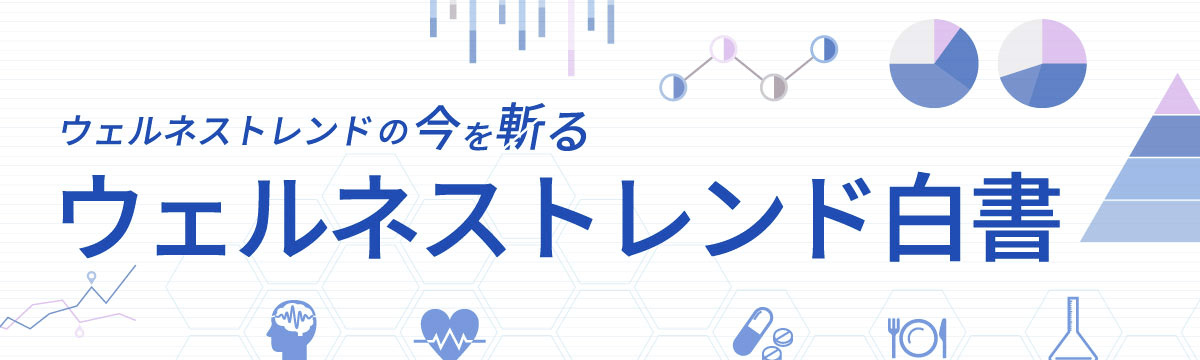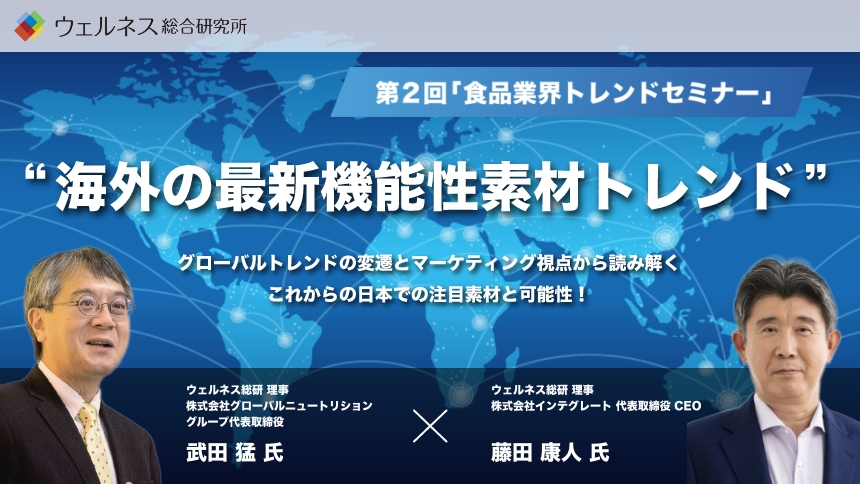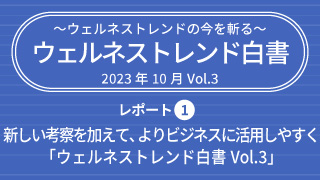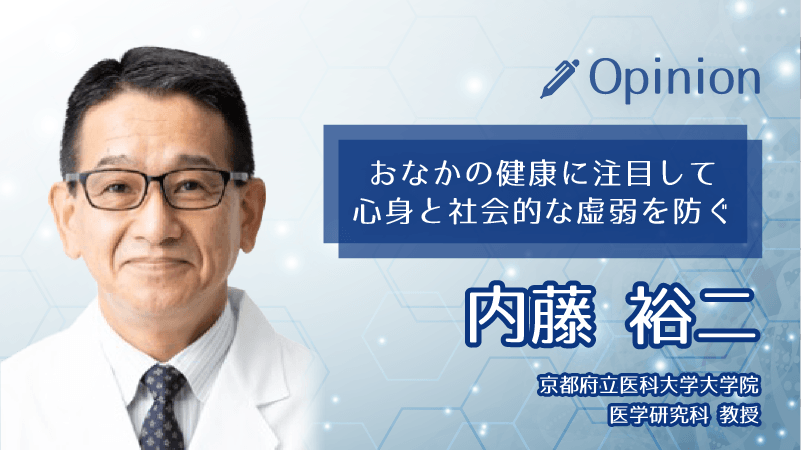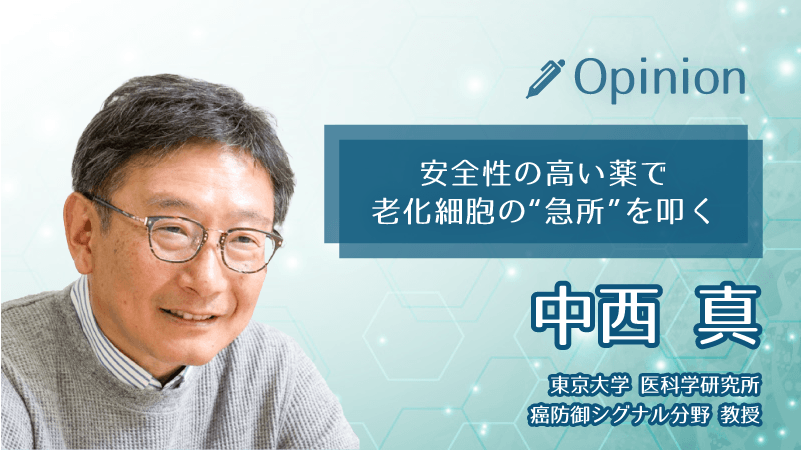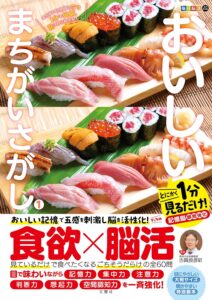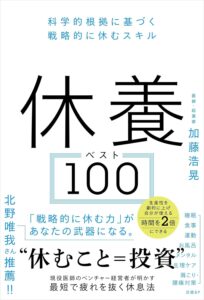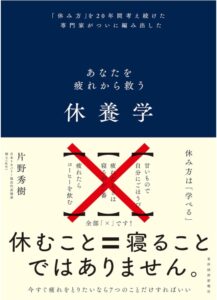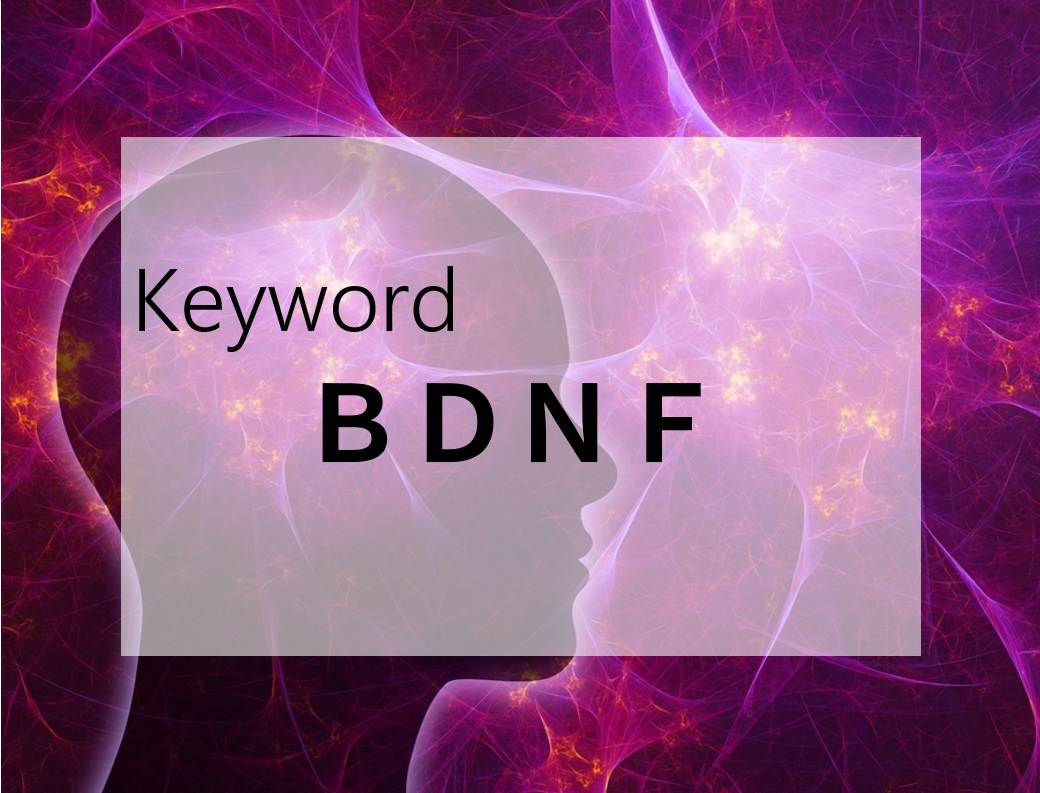
消費者のヘルスリテラシー等の調査
健康食品産業協議会(JAOHFA)は7月3日、第4回事業者向けアンケート「機能性表示食品等・消費者のヘルスリテラシーに関する事業者の実態調査」報告書を公表した。調査結果から、多くの事業者が消費者のヘルスリテラシー向上のための情報提供に問題を抱えており、それを解決するために情報の質と伝達方法の改善が必要と考えていることが判明した。機能性表示食品制度については、PRISMA2020対応や安全性情報の収集に課題を抱えている企業が多く、業界として対応していく必要があるとまとめた。
機能性表示食品制度に関わる事業者アンケートは今回で4回目。2016年度、2019年度、2021年度に実施してきた。今回は前回のアンケートを引き継いだ定点観測を基本に、小林製薬事案関連の健康被害に関する影響、健康被害情報収集に関する課題、国立健康・栄養研究所の安全性情報削除の影響、PRISMA2020対応等制度改正に対する課題と懸念点について把握するべく質問を追加し、各業界団体の所属する事業者を対象にしたアンケートである。回答数は80社(前回比67.2%)とやや低かった。今回は店頭の状況に関する設問を除いたため、日本チェーンドラッグストア協会に依頼を行わなかった。
まず、「消費者のヘルスリテラシー向上のための販売活動や商品に対する情報提供に関して課題を感じているか」の設問に対して「よく感じている」が47%、「時々/たまに感じている」が49%、合計96%とほとんどの企業が課題と感じていることがわかった。その中から、「消費者のヘルスリテラシーが向上しづらい原因」についての設問では、「事業から発信する情報だけでは消費者の理解を得ることが難しいから(業界団体や行政等の発信不足)」が66%と高く、次いで「消費者庁の機能性表示食品の届出情報にて情報公開しているが、想定以上に活用が進まないから」が33%であった。「消費者庁で公開されている機能性表示食品の商品ごとの届出情報へのリンク、もしくは機能性表示食品届出情報の検索画面へのリンクを、自社のWebサイトや通信販売サイト内に表示していますか」という問いに対して、「はい」が45%、「いいえ」が55%であった。「消費者庁の機能性表示食品届出情報検索、商品ごとの届出情報ページについて、消費者のさらなる活用促進のために改善した方が良い点を教えてください」という問いについて、「消費者が期待する機能別にカテゴリー別検索機能を作成」が56%、「スマートフォン表示に対応する」が55%と高かった。また、「消費者用「検索窓を減らしたシンプル検索機能」ページを新たに作成し、事業者用「詳細検索機能」(現状のままの検索機能)と入口を分けて設置することについての賛否について」では「賛成する」が89%と高く、事業者側として強い要望であることがわかった。
製品の安全性についてでは「小林製薬の紅麹関連製品による健康被害に関する報道を受けて事業や業務に影響がありましたか」では87%が「はい」と答えた。「国立健康・栄養研究所のデータベースを機能性表示食品の届出に再び利用できるようになれば、利用したいですか」では、「はい」が91%と高く、同研究所の2023年の閲覧休止は大きな影響があったことがわかった。最近、復活している。 制度改正・更新関連では、「PRISMA2020に課題を感じているか」に対して、95%が「はい」で、「前回差戻しコメントになかった箇所に対して新たに差し戻されることがよくある」が45%、次に「受理実績のあるものと同様に記載しても差し戻される」が39%、「マニュアルの内容が複雑で理解が難しい」が38%とあり、実際に今年4月から2020申請で受理・公開の件数が非常に少なく、今後大きな問題になりそうだ。
「FOOD STYLE 21」2025年8月号 F’s eyeより