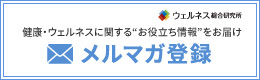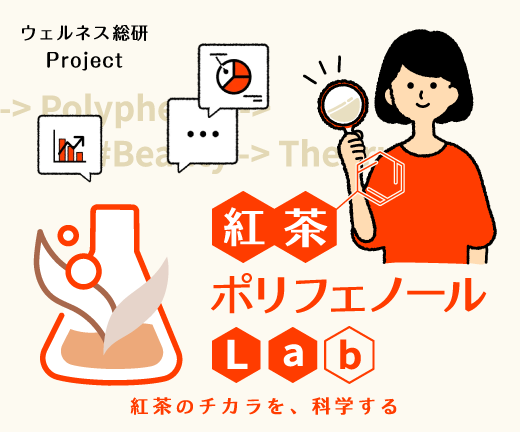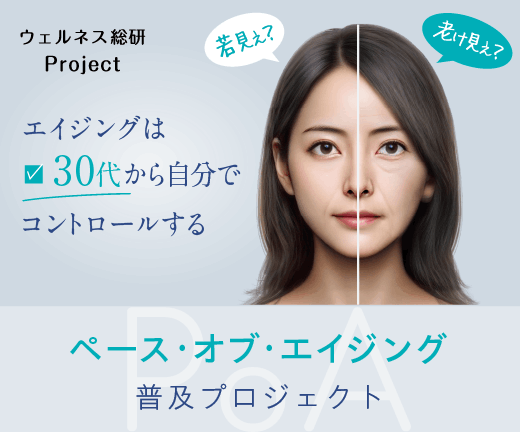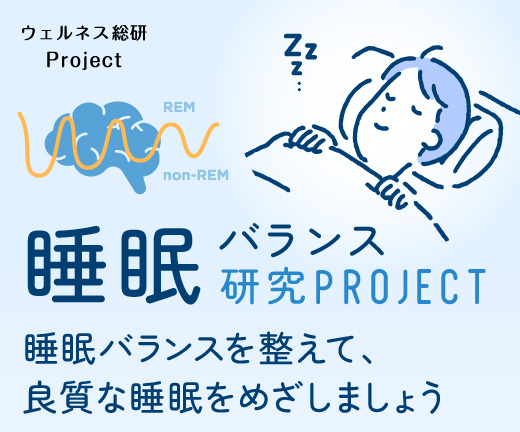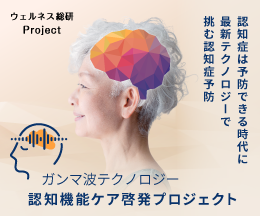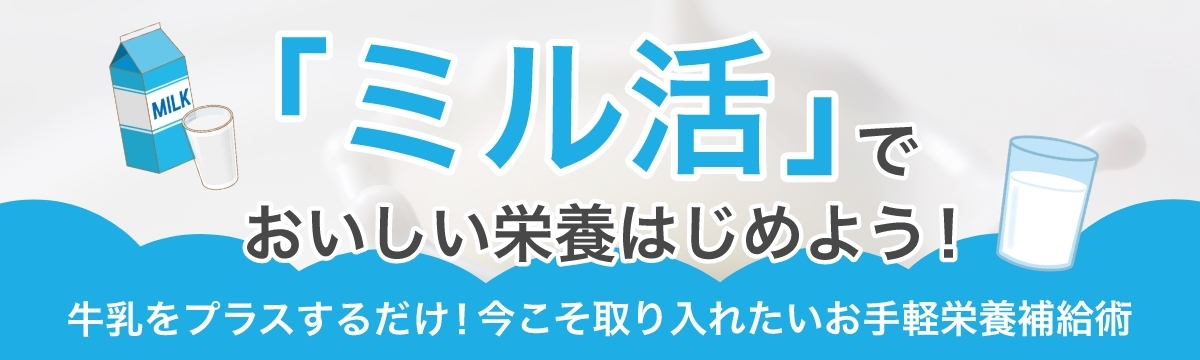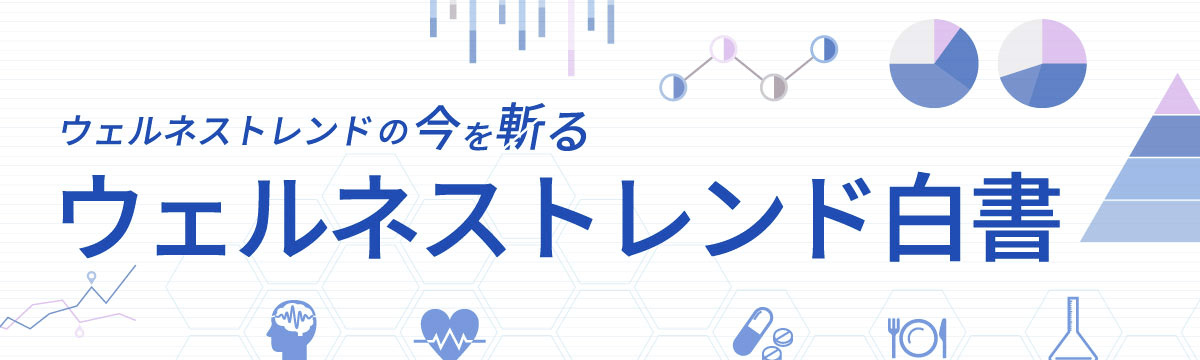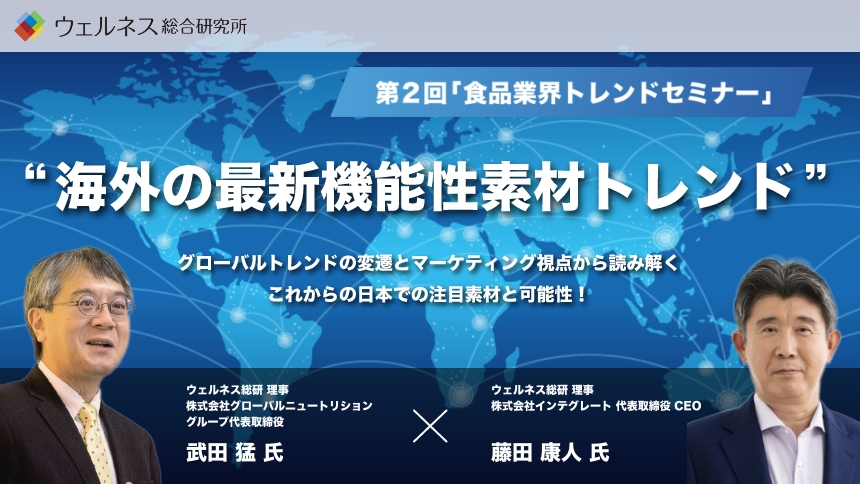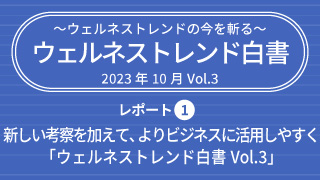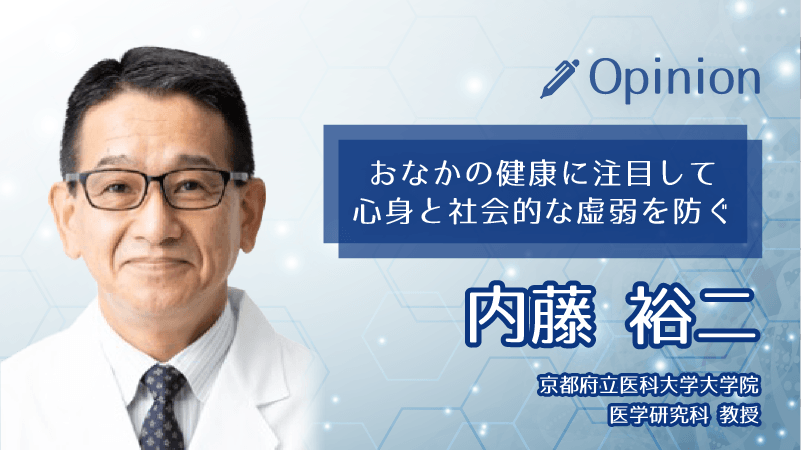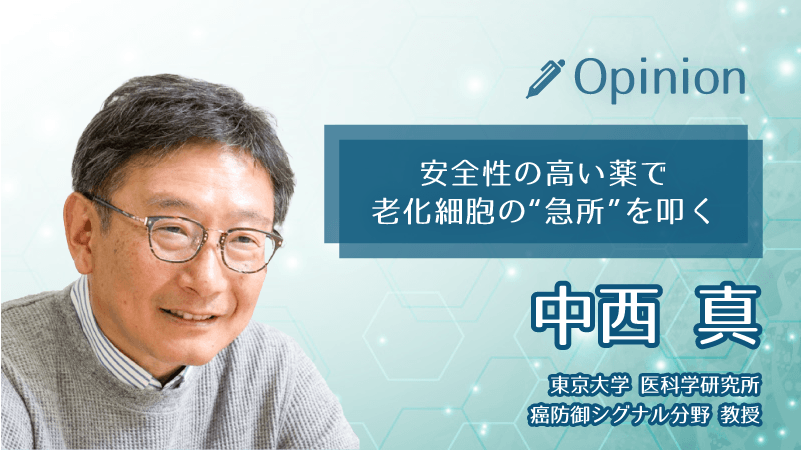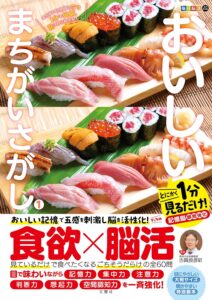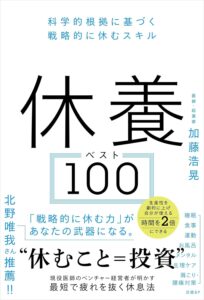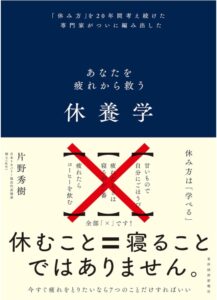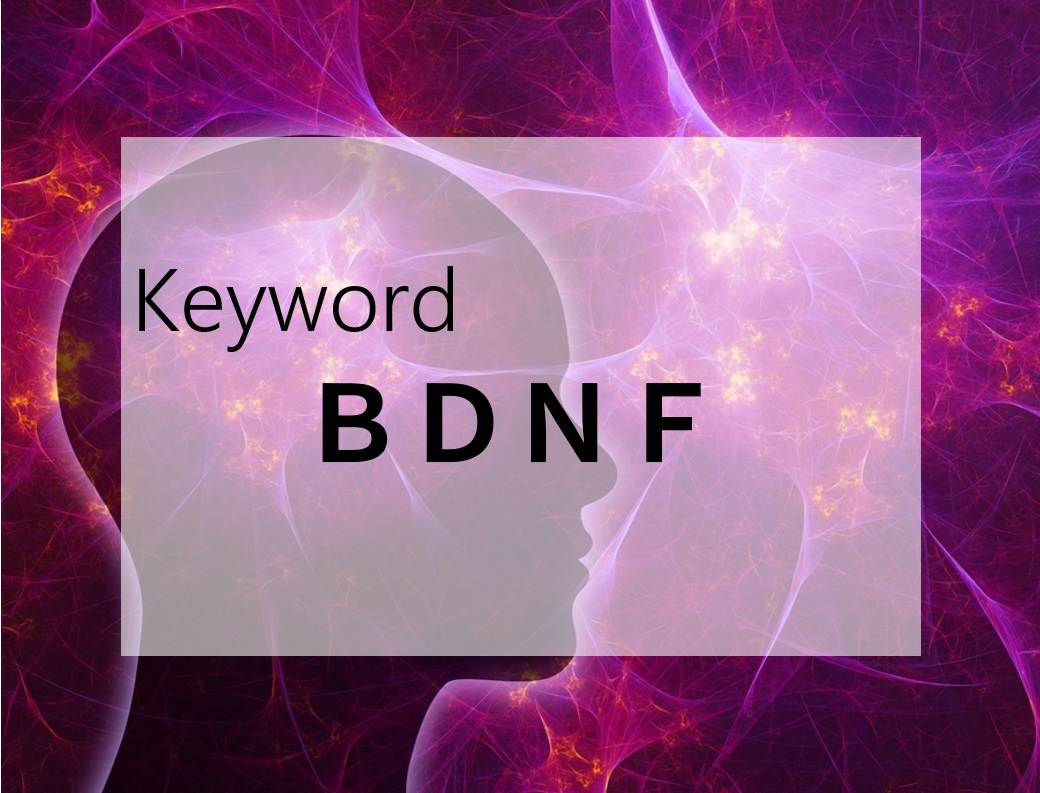
食を豊かにするカロテノイドの展望
日本カロテノイド懇話会は5 月22日、東京ビッグサイトにおいて、17回目となる「カロテノイドフォーラム」を開いた。
同会の会長を務める三栄源エフ・エフ・アイの西野雅之氏は冒頭挨拶し、同会が設立19年を迎えたことに触れ、カロテノイドの有用性などさらなる研究開発に向けた支援を進め、認知度の向上を図ると述べた。
今回の招待講演では、関西学院大学生命環境学部専任講師の浦上千藍紗氏が「ラマンプローブの軽量・小型化による、ラマン分光測定の汎用性の拡大」と題し、カロテノイドの構造解析にも使用される「ラマン分光法」を紹介した。同氏は散乱光が集合する部分を改良し、軽量・小型化したラマン分光測定装置を開発。共鳴ラマン分光法は、ラマン散乱が強くなることで吸収がある分子の振動によりラマン線の振動が強くなる。またそれにより、試料濃度が薄くても測定でき、共鳴しない部分の散乱や、吸収を持たない分子に関するラマン散乱においても、共鳴ラマン効果で強度を高めることができる。複雑な成分組織を持つ生体組織の観察にも適し、目的物質を抽出せずに非破壊のまま周辺環境の相互作用の情報を含む色素光度を選択的に観測できると話した。
次に名城大学准教授である本田真己氏は「次世代シス型カロテノイドの実用化に向けた取り組み」と題し、シス型カロテノイドの有用性について解説。近年の技術進展により、オールトランス型よりシス型カロテノイドは、高い健康効果を享受できる。また溶解性に優れ、結晶性が低いため高い加工適正を有するとして、シス型カロテノイドの最新研究や実用化に向けた取り組み、課題を紹介した。
また理研ビタミンの高橋伶仁氏は、「パプリカ由来カロテノイドと骨の健康」について講演。パプリカには「カプサンチン」「β-カロテン」「ゼアキサンチン」「β-クリプトキサンチン」など 4 つのカロテノイドが含まれ、同社ではこれらで構成されるパプリカ由来カロテノイドの健康効果に関する研究に取り組む。特に同社が注目するβ-クリプトキサンチンを用いた日本の研究として三ヶ日町研究を紹介。閉経後の日本人女性を対象にした同疫学研究では、血中β-クリプトキサンチン濃度が高いグループにおいて骨密度が高いことが報告されている。また同社で実施したヒト試験では、パプリカ由来カロテノイドを摂取した人がプラセボを摂取している人より破骨細胞の分化を抑制し、骨吸収が穏やかになったことを報告した。
またハリマ化成の中村健人氏は、「持続可能な未来を目指して:高吸収型カロテノイドとバイオものづくり」と題し、スマートセルを活用した持続可能なカロテノイド生産システムの開発と事業実装に向けた取り組みについて紹介。同社では有効な機能性成分を安定供給することを目的としたシス型カロテノイドのバイオモノづくり技術による製造方法を開発している。微生物や植物を利用したサステナブルなものづくりを目指し、コリネ型細菌を用いた「オールトランス型リコペン」の効率的な製造方法の開発などにも触れた。
また三栄源エフ・エフ・アイの中田健介氏は、「食を豊かにするカロテノイド ─ 着色料としての展望─」と題し、カロテノイドが世界の天然着色料市場において44%と最も多く使用され、利用されている現状について説明。また、食品で美しく発色させるカロテノイドの色調を付与する技術を示し、着色料として使用されるカロテノイドの魅力について、目で見て美味しさを楽しむことができる「食を豊かにする」可能性を展望した。
「FOOD STYLE 21」2025年7月号 F’s eyeより