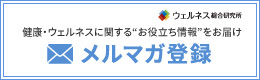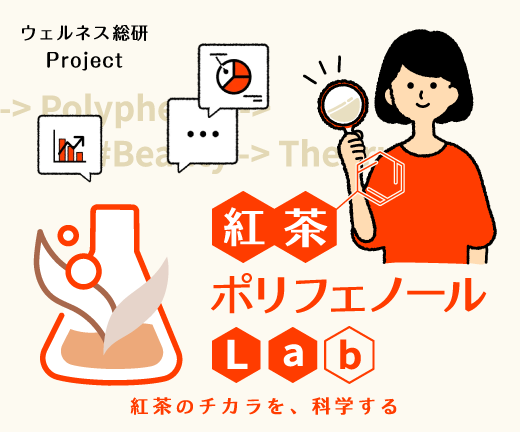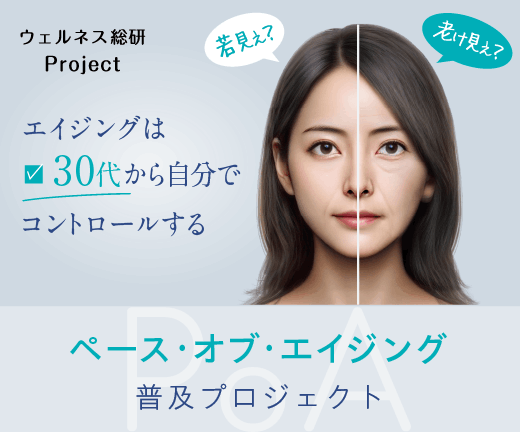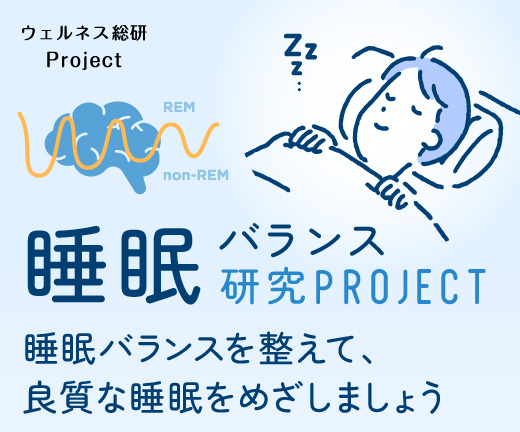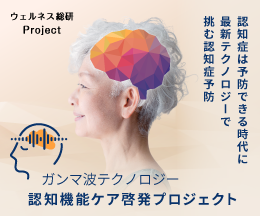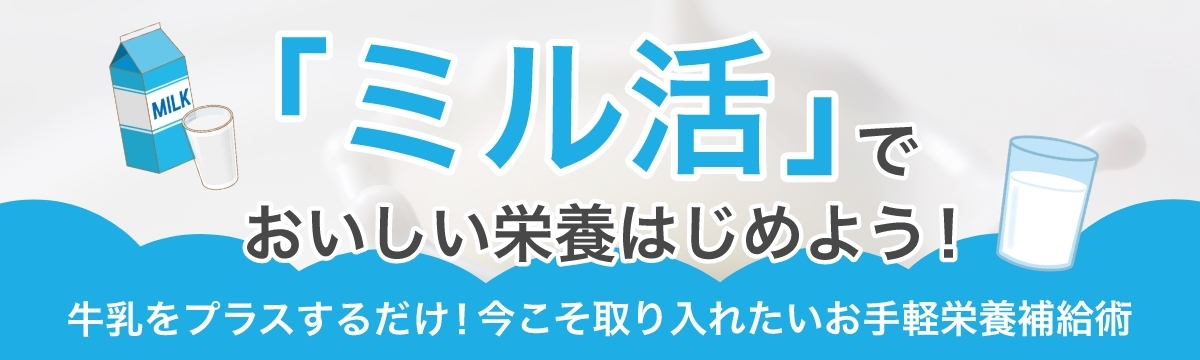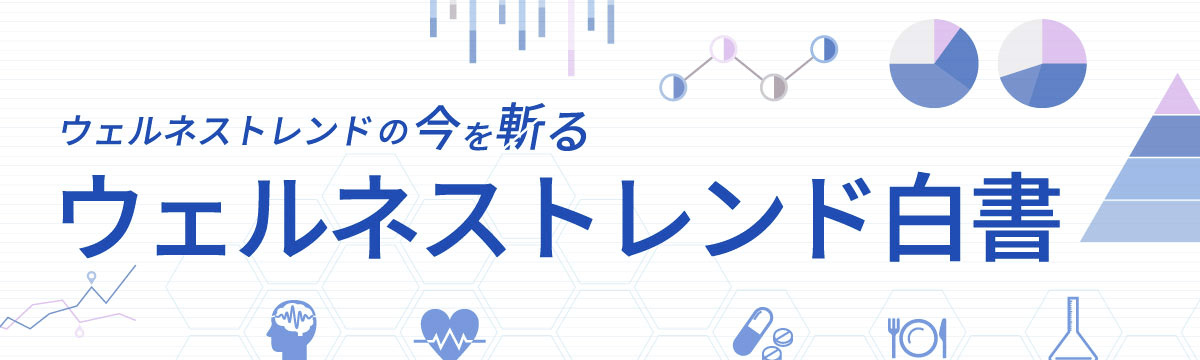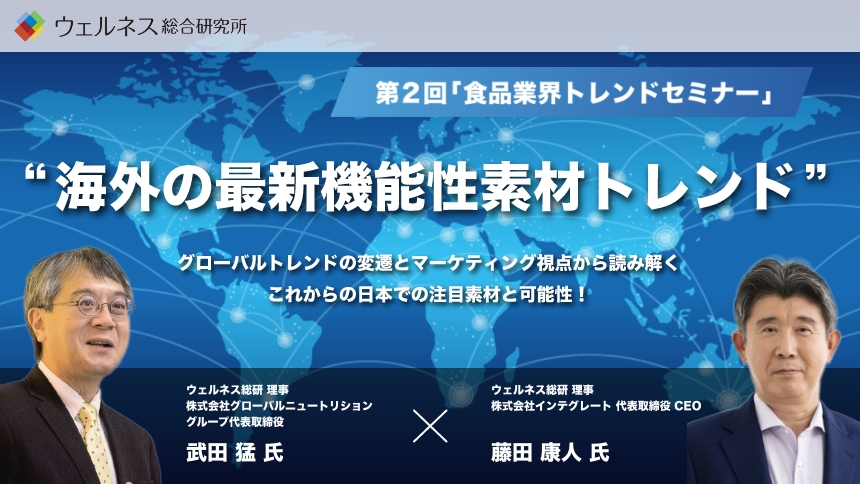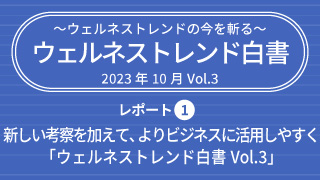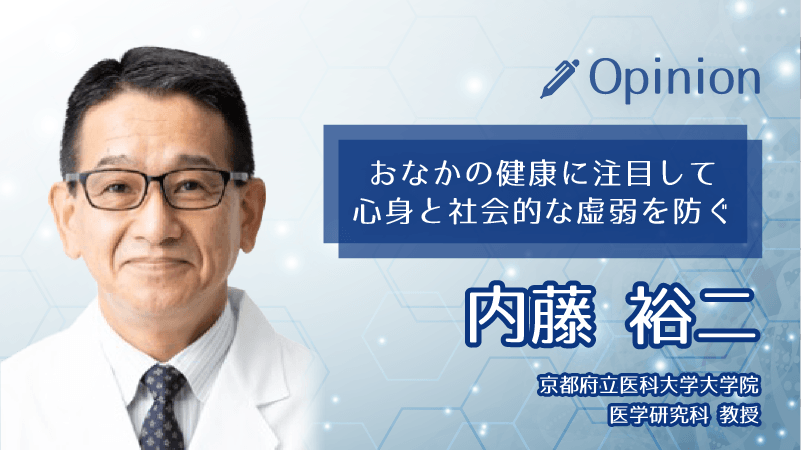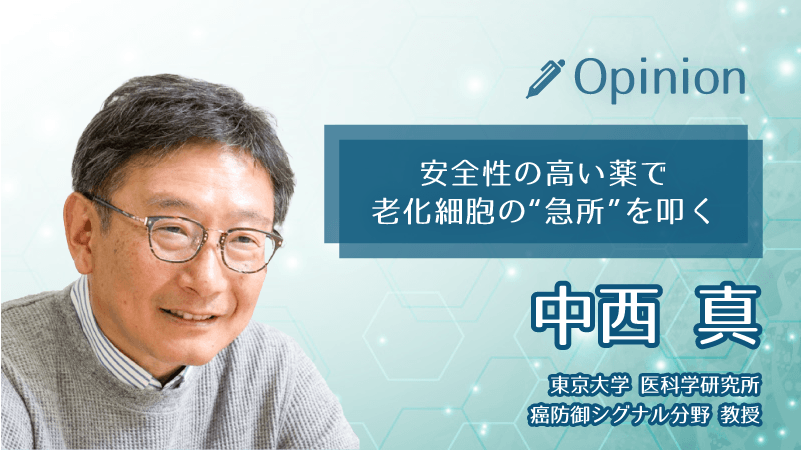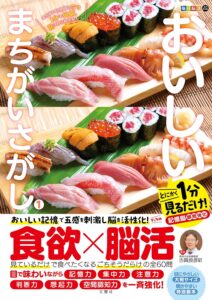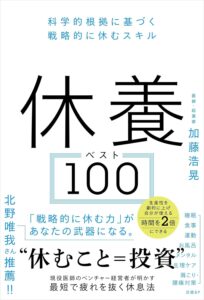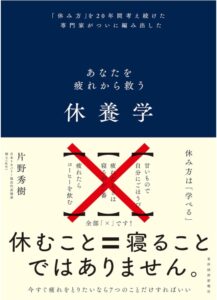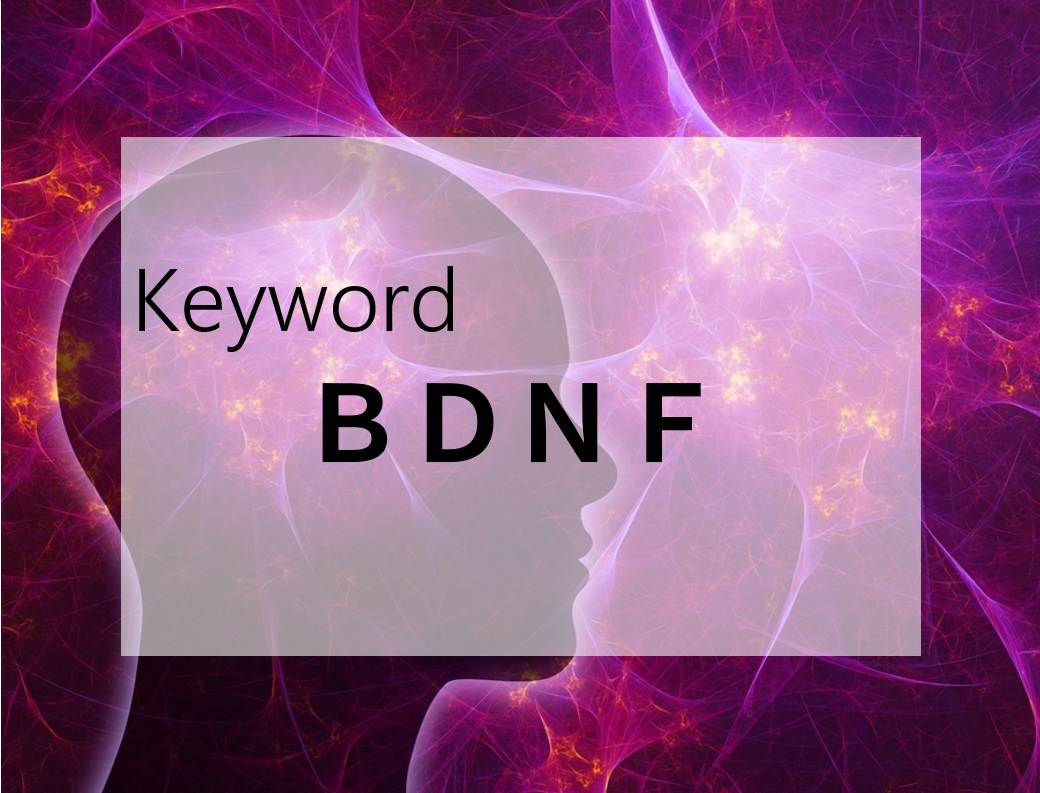
GMP義務化前に消費者庁が確認等を実施
来年9月から始まる機能性表示食品のGMP義務化に対応して、消費者庁が311通知のGMP指針に関連する事務連絡通知を発出し、業界の注目を集めている。
消費者庁食品衛生基準審査課は5月2日、事務連絡通知「『錠剤、カプセル剤等食品の製造管理および品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)』に係る項目解説および自己点検表について」を全国の都道府県・保健所配置市等に発出し、GMP指針の実効性をより高めるため、項目解説と自己点検表の活用を周知指導するよう要請した。消費者庁はその後、機能性表示食品の届出者にも今回の自己点検表等を示し、来年8月までのGMP義務化の経過措置期間までの間に確認・助言を実施していくこととなった。
消費者庁は昨年8月23日に食品表示法の食品表示基準を改正する内閣府令および告示改正を公布しており、機能性表示食品の届出者は錠剤・カプセル剤等食品についてGMPに基づく製造管理を行うことを遵守事項として規定(2年間の経過措置:令和8年8月31日まで)しており、GMPの遵守を届出者が確保することを義務化している。消費者庁は今回の事務連絡により、製造施設におけるGMP遵守が円滑に進められるように消費者庁自らがGMP実施状況の確認・助言を実施していくことにしたもの。具体的には来年8月末までに経過措置期間中に製造等施設に消費者庁のGMP担当職員が訪問し、製造管理・品質管理等のGMP実施状況の確認・助言の実施するほか、書面(製造等の体制に係る資料等)の確認等も実施する。これらの確認の前に、事前に自己点検の要請をする予定だ。複数品目を製造する製造等施設については、一部の品目のみとなるが、必要に応じて当該施設で製造する機能性表示食品がGMPに基づいて製造・加工されるよう助言を行う。
届出者は製造等施設と連携の上、GMP遵守の確保に向けて対応する必要がある。今後は製造など施設に対し、消費者庁が直接連絡し、日程を調節する。また、GMP状況を確認した結果、追加の確認が必要であると判断した場合は、フォローアップとして再度の確認等の検討も行っていく予定である。事務連絡の項目解説には、指針が規定する「総括責任者等」「製品標準書等」について活用する際の考え方や留意点、「自己点検表」(A4で33P)には点検項目ごとに点検結果や順守状況が判断できる客観的根拠のチェック欄が設けられている。
この動きに関連して、先日開催された健康と食品懇話会総会の懇親会で登壇した、消費者庁の中山智紀食品衛生・技術審議官が「昨年8月から今年3月にかけて機能性表示食品制度の改正に向けてさまざまな法令化や通知の改正が行われました。その中で制度変更の趣旨をご理解いただいて、官民で取組み、機能性表示食品制度の信頼回復にしっかり取り組んでいくこと、また併せて消費者庁にGMP義務化を指導するGMP経験者を新たに採用し、来年秋からGMPを監視指導していく立場として、来年秋までの1年半は業界のGMP向上のための指導を進めていき、品質確保の取組みを官民でしっかり進めていきます。また、機能性表示食品に限らず、いわゆる健康食品についても昨年5月の関係閣僚会議でも触れられているのですが、制度の在り方について検討しなければならい。これは本年6月で前回の食品衛生法改正の平成30年の施行後5年を経て、法の全体像の見直しをしていく中で、いわゆる健康食品もどうしていくか議論されていくことになります」と述べ、消費者庁の決意表明であった。今回の事務連絡のGMP遵守の方向性や今後検討する健康食品の “法制化?” の議論の行方を見守りたい。
「FOOD STYLE 21」2025年6月号 F’s eyeより