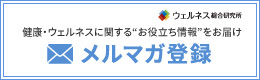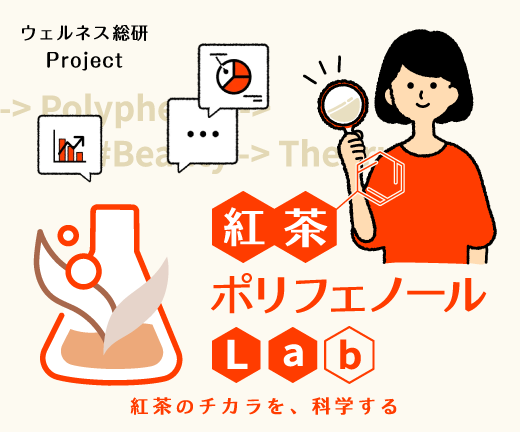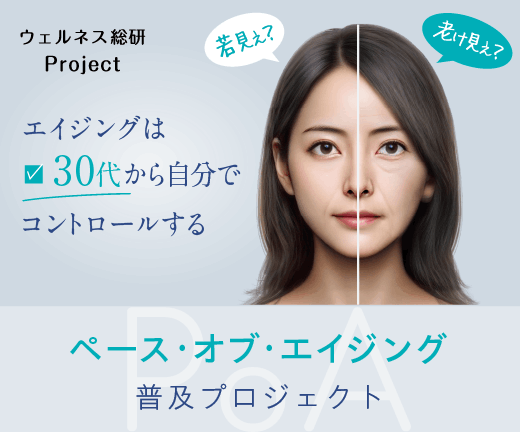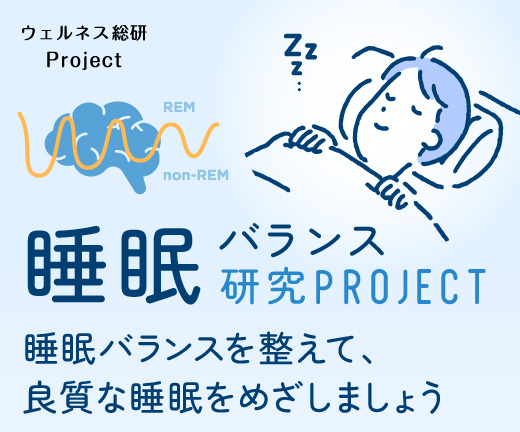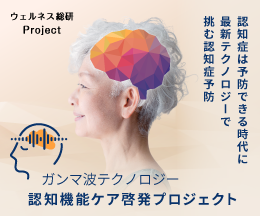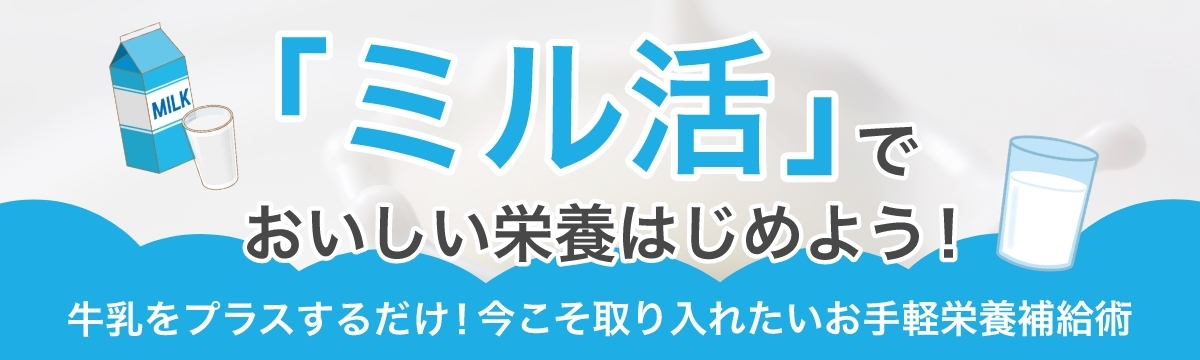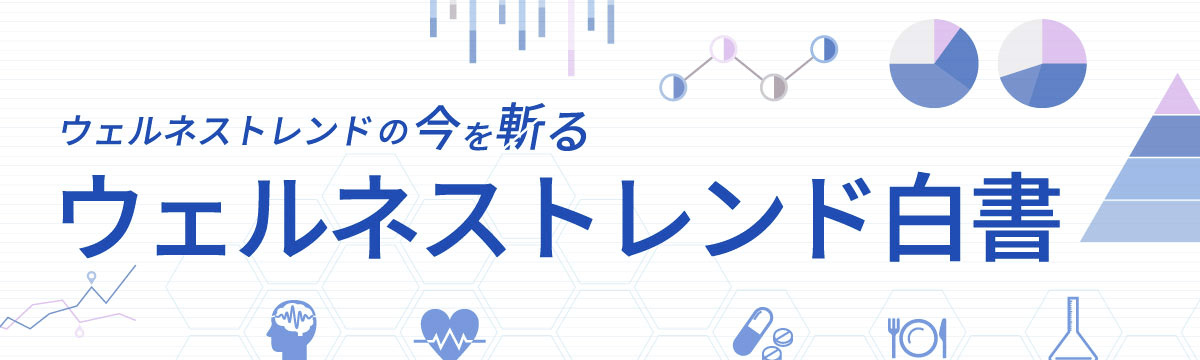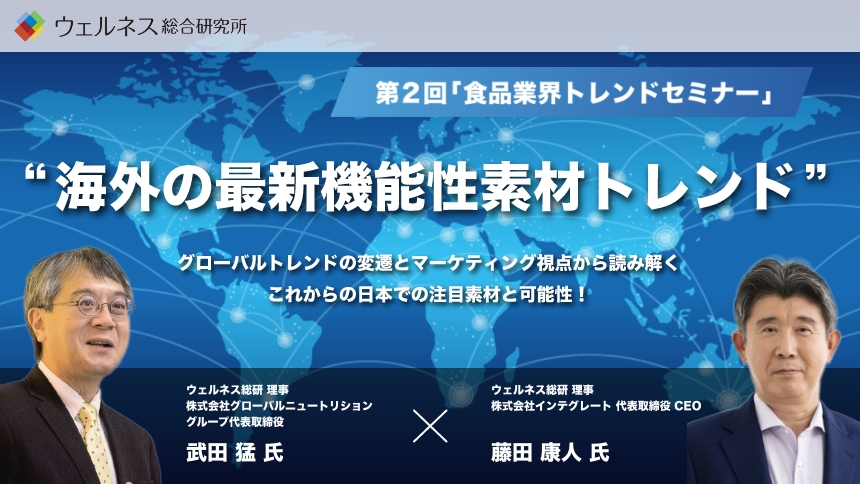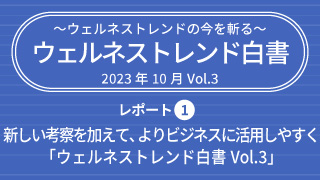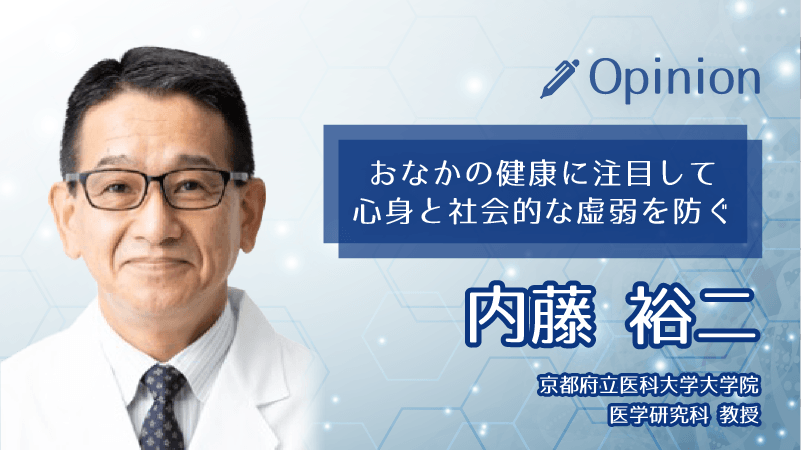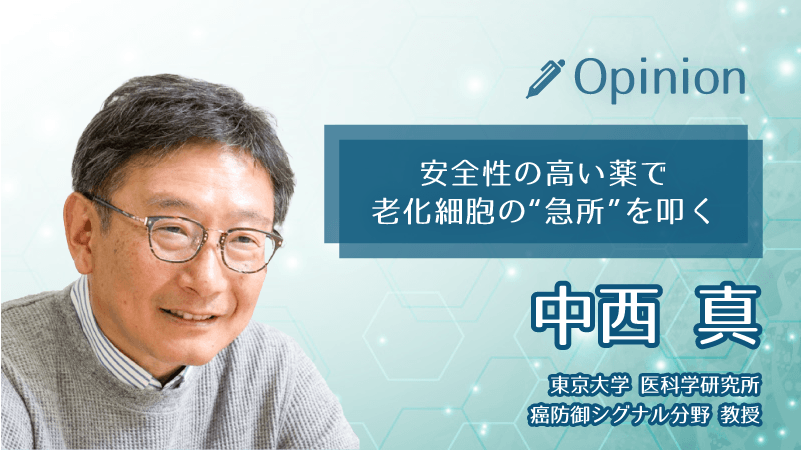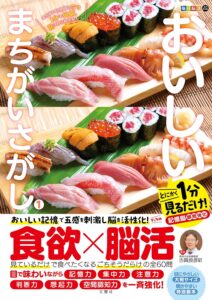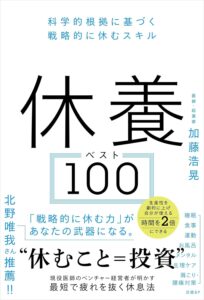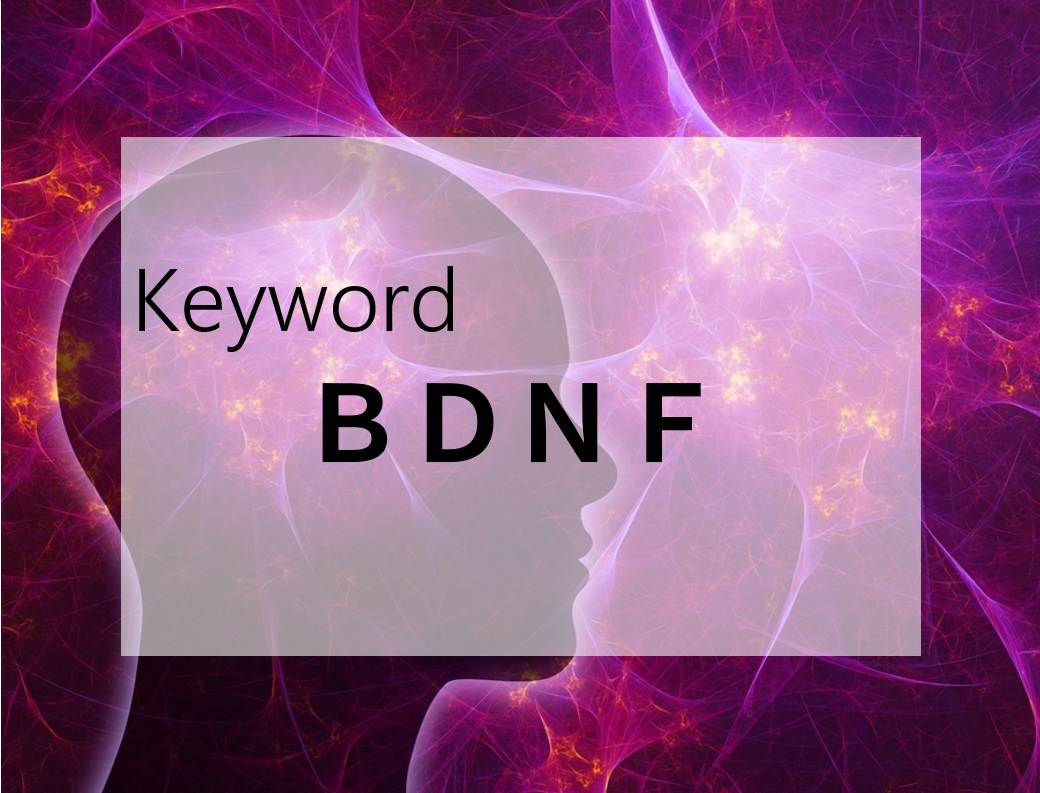
【注目書籍】「老化時計」の進み方を大きく変えるライフスタイルのすすめ

運動・身体活動と健康との関わりの研究は、1950年代に英国で始まったそうです。ロンドンの2階建てバスの運伝手と、バス内を移動しながら切符を売る車掌の健康状態を比較したところ、ずっと座り続けている運転手は、虚血性心疾患になる確率が高いことが明らかになったのだとか。
そこから「運動疫学」という学問がスタートし、欧米を中心に、生活習慣とさまざまな慢性疾患との関係が明らかになっていきます。日本でも1990年代から大規模コホート研究が実施されています。
日本人と欧米人では遺伝素因も生活習慣も異なることから、自ずと内容や結果も変わります。『健康寿命と身体の科学』(樋口 満 著/講談社 ブルーバックス)の著者は、日本人を対象としたプロジェクト「WASEDA’S Health Study」の立ち上げから関わった人物。「老化時計は、個々のライフスタイルで遅らせることができる」と言い、本書ではその根拠と方法が紹介されています。
「アンチエイジング(抗老化)」よりも「サクセスフル・エイジング(幸老化)」

昨今では、自らの「健康寿命を伸ばそう」と頑張っている方も多く、厚生労働省が出している統計の年次推移を見ると、確かに20年前に比べて健康寿命は伸びました。しかし、平均寿命も同じように伸び、その差である「日常生活に制限のある“不健康な約10年間”」は縮まっていないのです。
健康増進に関する運動生理・生化学、スポーツ栄養学を専門に研究する著者は、その10年間を「自立し、楽しくからだを動かせる“動楽寿命” “元気寿命”としてキープできたら」と考えます。それには、「アンチエイジング(抗老化)よりもサクセスフル・エイジング(幸老化)を目指すべきだ」と言います。
幸老化を目指すためには、「なぜ老化が起きるのか」「防ぐ方法はないのか」という問いが立ち塞がります。そこで、世界中で研究されてきた代表的な老化の概念として、「生涯代謝量一定理論」「フリーラジカル理論」「アポトーシス理論」「サーチュイン理論」「テロメア理論」「免疫機能低下理論」などが紹介されています。
こうした概念はいずれも、老化のスピードに個々人のライフスタイルが関わっているというもの。それらを受けて著者は、「習慣的な運動トレーニングや抗酸化栄養素の摂取は、酸化ストレスを抑制して、身体機能の向上や病気の発症率を下げる」とまとめています。
老化をなくすための治療法の模索

では、どうすれば老化を遅らせ、「幸老化」を体現することができるのか。まず、50歳からの日本人の体質に合った栄養や食事について紹介しています。
加齢による老化が多くの疾病や死亡率の危険因子ではありますが、近年では食事パターンの介入によって、老化を抑制することが重要であると考えられるようになってきたそうです。地中海沿岸に住む人々の伝統料理「地中海食」は、生物学的老化を遅延させる可能性が示唆されています。
また、「WASEDA’S Health Study」に参加したシニア男性を対象にした研究では、魚、野菜、きのこ、いも、海藻、大豆製品などを使った副菜重視の日本食を続けることによって、生物学的老化やテロメア長の短縮を遅らせることができ、メタボやロコモを予防する働きがあることも示唆したそうです。
そこで着目したいのが、ミドル層とシニア層の健康課題は同一ではないということ。ミドル層は過食と運動不足による肥満が課題ですが、シニア層は筋量や筋力の低下が課題。それぞれを分けて紹介されています。
基本は、どちらも主食・副菜・主菜・牛乳や乳製品・果物を基本に摂取することです。厚生労働省と農林水産省が合同で決定した「食事バランスガイド」がその見本。駒の形をしたもので、見たことがある方も多いのではないでしょうか。
そこには、水分補給の重要性も示されています。成人の体の約60%が水分ということはよく知られていますが、特に体温調節機能が低下してくるシニア層は、熱中症予防のためにも水分補給が推奨されています。
また、アメリカの疫学研究では、習慣的に高たんぱく質摂取をしているミドル層は、全死亡率や生活習慣病、がんなどによる死亡率が高いことが指摘されているそうです。それに対して、シニア層はたんぱく質の摂取エネルギー比率が高いほうが、がんなどにかかりにくく、逆に、低たんぱく質摂取では健康に悪い影響があるという報告があるそうです。
効率の良い運動法「タバタ・トレーニング」
次に、運動法が紹介されています。無酸素性エネルギー供給システムのスポーツはハイパワー系に、有酸素性エネルギー供給システムのスポーツがローパワー系に、その両エネルギー供給システムを併用してパワーを発揮するスポーツがミドルパワー系に相当するといいます。
つまり、砲丸投げや100m走、ゴルフ、テニスなどはハイパワー系、200m走、400m走、800m走、1500m走、スピードスケート、体操競技、ボクシング、レスリングなどはミドルパワー系、1500m競泳、クロスカントリー、マラソン、ジョギング、ローイングなどはローパワー系に相当するスポーツになります。
それらのエネルギー源が体内でどのように代謝されているかといった比較をした上で、有酸素運動の心肺体力(ローパワー)を高める効果と、無酸素運動の能力(ハイパワー)を高める効果をあわせもった効率の良いトレーニング法として「タバタ・トレーニング」を紹介しています。全力運動20秒+10秒の休憩を1セットとして、それを8回繰り返し、合計4分で終了するというものです。
タバタ・トレーニングは、短時間で有酸素性能力と無酸素性能力の両方を向上させるトレーニングとして、アスリートから一般市民まで実践されているもの。シニアにとってもおすすめのトレーニング方法です(ただし、運動強度が高いので、潜在的な疾患リスクを確認してから行うべきとしています)。
本書で紹介されたすべての健康習慣を実践するのは難しくても、「幸老化」を目指す上でのパートナーとして、そばに置いて繰り返し読みたい1冊です。
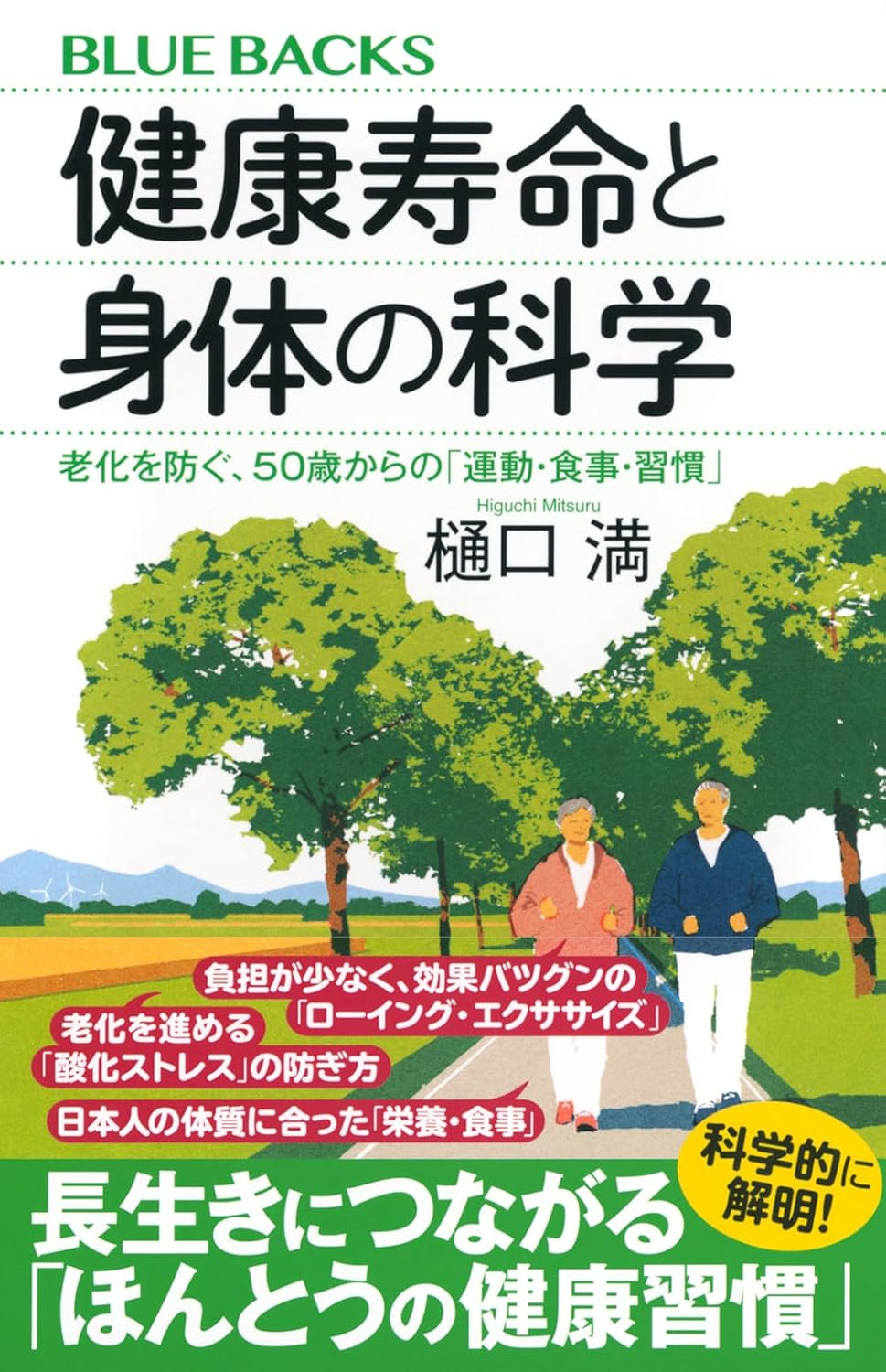
【書籍情報】
『健康寿命と身体の科学』(樋口 満 著/講談社 ブルーバックス)