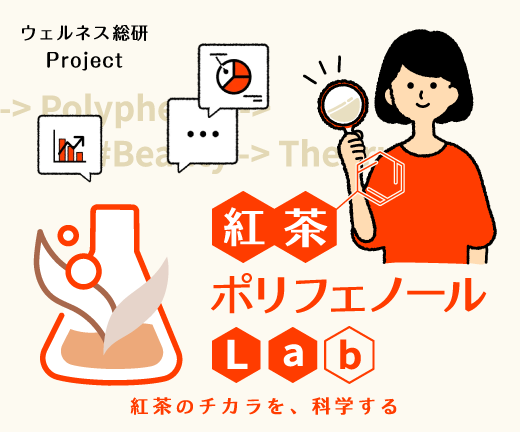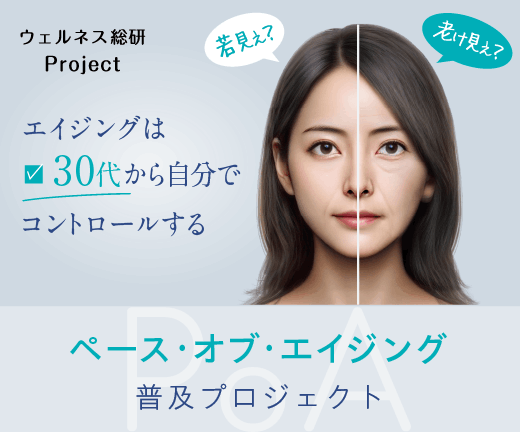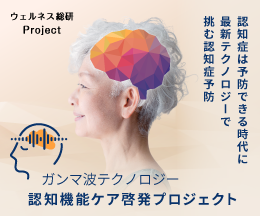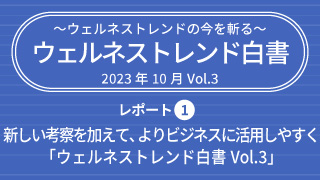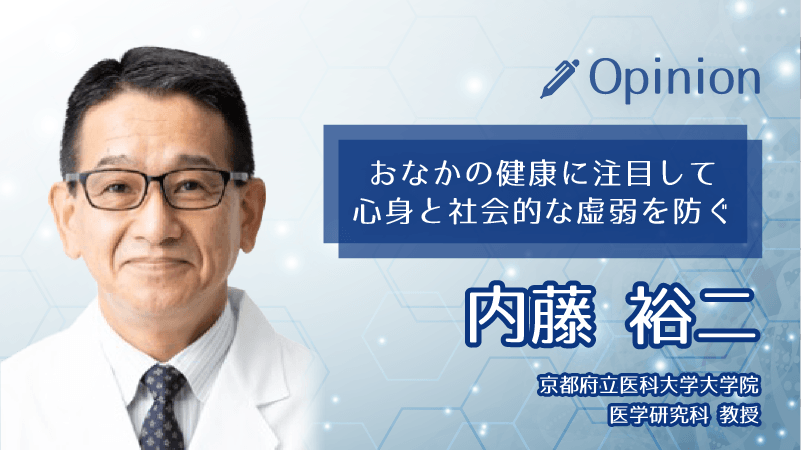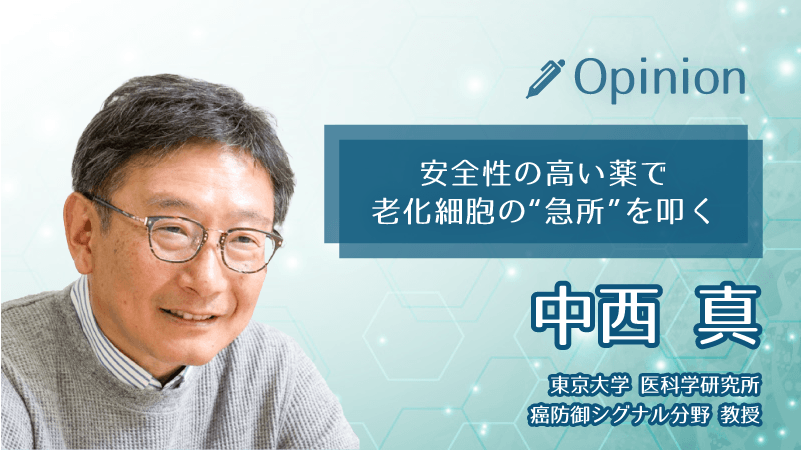【注目書籍】機械的生命観から動的平衡へ 分子生物学が迫る「生命の本質」とは

ここに一つの問いがあります。人の生活をかくまで変えてしまうウイルスという存在は、果たして生物なのか、それとも無生物なのでしょうか。
「生命とは何か」という問いに20世紀の生命科学が出した代表的な答えは、「生命とは自己複製を行うシステムである」というものでした。この考え方に基づくなら、自己複製能力がずば抜けたウイルスはまぎれもない生命体です。一方、ウイルスは栄養を摂取することもなく、呼吸もせず、二酸化炭素を出すことも、老廃物を出すこともしません。宿主となる細胞に付着し、そのシステムをのっとることで自らをせっせと複製するのです。
ウイルスを生物とするか、無生物とするかは長らく論争の種であり、いまだ決着がついていないとしながらも、代謝を行わないウイルスには「生命の律動」がないと感じ、「私は、ウイルスを生物とは定義しない。つまり、生命とは自己複製するシステムである、との定義は不十分だと考えるのである」という立場から生命の秘密に迫ったのが『生物と無生物のあいだ』(福岡伸一著/講談社現代新書)です。
絶え間なく変わり続けながら同一性を保ち続けているタンパク質が私たちの身体
著者の福岡伸一氏は分子生物学を専門とする生物学者。2007年に刊行された本書はサントリー学芸賞を受賞し、87万部のロング・ベストセラーとなりました。最先端の分子生物学がたどりついた地平を、自らの研究生活や、福岡氏が「アンサングヒーロー」と呼ぶ歴史に沈んでいった無名の天才科学者たちの思考も紹介しながらひもといていきます。
本書は15年前に書かれた本ですが、今読んでもその内容は新鮮で、むしろ今だからこそ、より身近に感じたり理解が深まったりする記述が増えたともいえます。たとえば新型コロナウイルスのPCR検査でおなじみになったPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)の仕組みや誕生秘話に関するくだりは、15年前に読んでもおそらくこれほど興味をかき立てられなかったことでしょう。また、福岡氏が「世界にまだ『地図』がなかったとき」と書いているのはヒトゲノムが解読される前の生物学界のことですが、その後さらに不明な部分の解読が進み、今年3月にはゲノムの完全解読が発表されました。しかし、ゲノムが完全に解読されたからといって、果たして人類は「生命とは何か」という問いに近づいたのでしょうか。そう感じる2022年の読者にとって、福岡氏がたどりついた結論──生命は遺伝子というパーツで構成された機械ではなく、パーツ自体のダイナミックな流れの中に成り立っているという考察は、より深く理解できるものになったのかもしれません。
福岡氏が「動的平衡」と呼ぶこの生命観にたどりついたきっかけは、膵臓に存在するGP2という重要なタンパク質が全身の細胞から失われたノックアウトマウスを誕生させ、どこに異常が発生するかを観察するという自らが取り組んだ実験の“失敗”でした。ノックアウトマウスには何一つ異常が起きなかったのです。検証の結果、実験に不備はなく、生命の適応力と復元力により、GP2の欠落が見事に埋め合わせられたということがわかりました。「私たちは遺伝子をひとつ失ったマウスに何事も起こらなかったことに落胆するのではなく、何事も起こらなかったことに驚愕すべきなのである」と福岡氏は述べています。
私たちの体は絶え間ない分解と合成にさらされているタンパク質であり、生命を構成するタンパク質は作られる際から壊されていきます。それなのにもとの形を保つことができているのは、タンパク質の相補性によって、あたかもジグソーパズルのピースのように納まる位置をあらかじめ決められているから。パズルのピースはぴったりと合うものの、がっしりとは結合せず、くっついたり離れたりの「かすかな口づけ」を繰り返しているという福岡氏の描写は、極めて専門的でありつつ見事な比喩によって生命の豊かなイメージを私たちに伝えてくれます。
部分が入れ替わりながらも全体として恒常性が保たれるという生命の動的平衡モデルは、持続可能性をテーマにしたさまざまな分野にも応用が可能。先が見えない時代といわれる今、改めて読みたい1冊です。

【書籍情報】
『生物と無生物のあいだ』(福岡伸一著/講談社現代新書)