04認知症コラム
【一覧あり】もの忘れがひどいときに考えられる病気は?
加齢によるもの忘れとの違いも解説
2025.04.30

もの忘れは単なる加齢現象だけでなく、ADHDやうつ病などさまざまな原因で発生します。20〜40代の若い世代でもの忘れが頻繁に起こるケースもあり、認知症など深刻な病気の可能性もあるため早期対応が重要です。この記事では、もの忘れがひどいときに考えられる病気、加齢によるもの忘れとの違い、適切な対処法について詳しく解説します。
【一覧】もの忘れがひどくなった
ときに疑われる主な病気
もの忘れがひどい場合、右記下記のような病気の可能性があります。考えられる疾患は年齢や症状の特徴によって異なり、高齢者では認知症やMCIが多く、若年層ではうつ病や脳障害を原因とする若年性認知症のおそれもあります。不安な場合は、医療機関を受診しましょう。
| 認知症 |
|
|---|---|
| 脳疾患 (認知症を除く) |
|
| その他の原因 |
|
もの忘れを引き起こす病気①認知症
認知症は、もの忘れを引き起こす代表的な疾患で、さまざまな種類があります。なかでも最も多いのがアルツハイマー型認知症です。認知症による記憶障害は、出来事そのものが抜け落ちるのが特徴で、とくに新しい記憶が失われていきます。もの忘れのほかにも、集中力の低下や、時間や場所の感覚の乱れなどを伴うケースも多く、日常生活や社会生活に大きな支障をきたします。

認知症はもの忘れ以外にも症状がある
| 症状 | 症状の例 | |
|---|---|---|
| 中核症状 |
|
|
| 周辺症状 |
|
|
認知症の症状は、主に中核症状と周辺症状に分けられます。中核症状は、もの忘れをはじめとする記憶障害、判断力・理解力の低下、見当識障害など、脳の機能低下によって直接的に発生する症状です。
一方、周辺症状(BPSD)は中核症状に付随して現れる症状で、不安・抑うつ、徘徊、幻覚・錯覚、暴力・暴言、睡眠障害、物盗られ妄想などがあります。これらの症状が見られた場合は、認知症かもしれません。
以下のチェックリストで認知症の兆候があるかどうか確認できます。もの忘れが気になっている場合は、チェックしてみてください。
認知症と加齢によるもの忘れの違い
| 加齢による もの忘れ |
認知症によるもの忘れ | |
|---|---|---|
| 忘れる対象 | 自分が体験した一部分 | 自分の体験そのもの |
| 忘れる範囲 | 一部のため、指摘があれば思い出せる | 体験そのものを忘れているため、指摘をされても思い出せない |
| 自覚 | ある | ない |
| 例 | 昨日食べた夕食の内容を思い出せない | 夕食を食べたこと自体を忘れる |
認知症と加齢によるもの忘れは、その性質や影響が大きく異なります。加齢によるもの忘れは体験の一部を忘れる程度で、ヒントがあれば思い出せますが、認知症では体験したことそのものを忘れてしまうのが特徴です。
また、加齢によるもの忘れは老化の自然な過程であり、症状自体が悪化することはありません。一方、認知症は症状が進行し、それに伴い記憶障害以外の症状も現れるようになります。
認知症は治療できる?
認知症は一度発症したら根治することは難しい疾患です
現在、認知症を完全に治す方法は確立されていません。しかし、症状の進行を遅らせたり、ある程度まで改善したりすることは可能です。主な治療法には薬物療法と非薬物療法があります。
また、認知症の種類によっては、脳外科手術で原因を除去することで治療できる可能性もあります。
「軽度認知症(MCI)」の段階であれば治る可能性がある
軽度認知障害(MCI=Mild Cognitive Impairment)とは、日常生活に支障がない程度の認知機能や記憶力の低下がみられる認知症の前段階にあたる状態です。MCIによるもの忘れには下記のような特徴があり、この段階で異変に気づいて適切に対処すれば、認知機能が健常に戻る可能性があります。
- MCIによるもの忘れでみられる特徴
-
- もの忘れが増えたことを自覚している
- 出来事自体は覚えているが、詳細を覚えていない
- 習慣になっていることは問題なく遂行できる
- 状況に応じて適切な判断ができる
認知症になる前の予防が大切
認知症は一度発症してしまうと治療が困難なため、日頃から予防に取り組むことが重要です。まずは、生活習慣を見直し、健康的な食生活、適度な運動、十分な睡眠を心がけましょう。また、言葉遊びやパズルなど認知機能を刺激する活動や、社会活動に参加するなど人との交流を増やすことも効果的です。
さらに、定期的な健康診断やMCIスクリーニング検査を受けることで、早期発見・早期対応が可能になり、認知症のリスクを低減できます。
もの忘れを引き起こす病気②脳疾患
頭部外傷(慢性硬膜下血腫など) 脳腫瘍 脳炎、髄膜炎 など
もの忘れはさまざまな脳疾患によって引き起こされる可能性があります。具体的には、頭部外傷による慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、脳炎や髄膜炎などです。これらの疾患は、脳の特定領域に影響を及ぼし、記憶や認知機能に障害をもたらすことがあります。とくに慢性硬膜下血腫は、高齢者に多くみられる脳疾患の一つです。
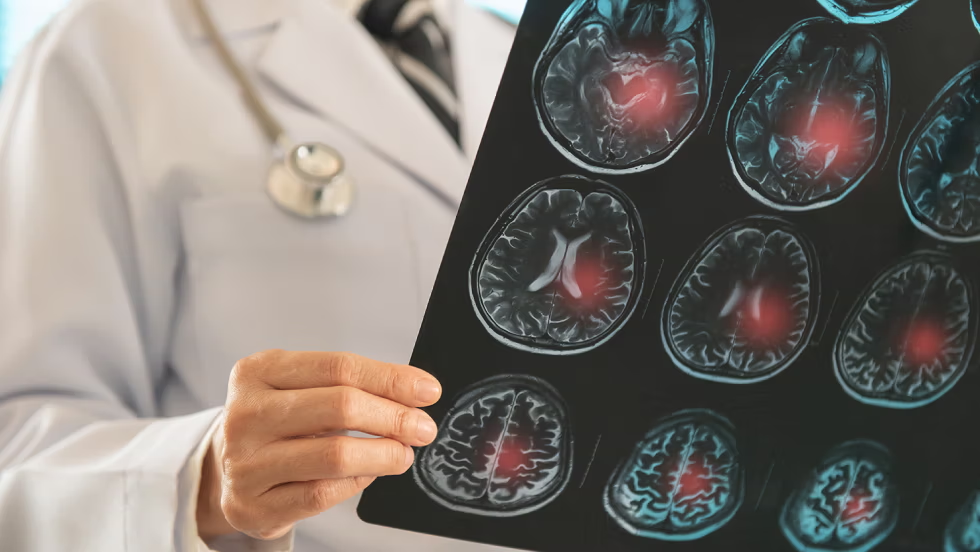
損傷した脳の部位によって症状は異なりますが、共通して頭痛やけいれんなどの症状がみられます。いずれも認知症の原因となる可能性があるため、早期発見と適切な治療が重要です。
- 慢性硬膜下血種とは?
- 頭部打撲などの衝撃で、脳を覆う硬膜と脳の間に血液が徐々にたまる病気です。頭部打撲から数週間〜数ヶ月後に、頭痛や軽い運動麻痺、もの忘れなどの症状が現れます。
- 脳炎/脳髄炎とは?
- 細菌やウイルスが脳に感染して炎症を起こす病気です。発熱、頭痛、嘔吐などの症状を引き起こし、重症化すると意識障害やけいれんを起こす可能性があります。
もの忘れを引き起こす病気③その他の原因
うつ病 せん妄 甲状腺機能低下症 梅毒 ビタミン欠乏症 栄養障害 薬の副作用 など
もの忘れは必ずしも脳の疾患だけが原因ではありません。脳に直接的な異常がなくても、さまざまな要因によってもの忘れが引き起こされる可能性があります。とくに、うつ病とせん妄は認知症と似た症状を示すことがあり、注意が必要です。それぞれ詳しくみていきましょう。
うつ病によるもの忘れ
うつ病による集中力の低下が記憶力の減退を招き、もの忘れの頻度が高まる可能性があります。うつ病のもの忘れは、新しいことを覚えられなくなるのが特徴です。たとえば、本を読んだり、打ち合わせをしたりしても頭に入っておらず、覚えていないことがあります。大きなストレスを感じていた場合、うつ病を疑いましょう。

せん妄によるもの忘れ
せん妄は高齢者によくみられる環境変化などを契機に発生する一時的な精神機能障害です。意識がもうろうとして注意力・集中力が落ち、新しい情報を処理できず、物事を覚えられなくなることがあります。
認知症と症状が似ているため見分けがつきにくいですが、時間と共に環境に慣れて落ち着いてくる場合が多いです。また、せん妄は症状が急激にあらわれるのが特徴です。ただし、認知症を併発しているケースもあるので注意が必要です。
もの忘れがひどくなってきたときの対処法
もの忘れには深刻な疾患が潜んでいる可能性もあるため、症状が気になり始めた段階で適切に対処することが重要です。早期発見・早期対応で、症状の進行を遅らせたり、改善できたりする可能性が高まります。

不安を感じたらすぐに医療機関を受診する
もの忘れの症状がひどくなってきたら、決して放置せず、専門医の診断を受けることが大切です。うつ病やせん妄など、治療によって症状が改善する病気もあります。不安を感じた段階で、すぐに医療機関を受診しましょう。
原因を適切に突き止める
もの忘れの原因は、加齢による自然現象、生活習慣の乱れ、薬物の副作用、脳の疾患など多岐に渡り、その原因によって行うべき対応も変わってきます。原因を正確に把握し、適切な処置を施すことで、もの忘れの進行を防げる可能性も高まるでしょう。その意味でも、早めに医療機関を受診し、専門医に診断をしてもらうことは重要です。
適度な運動を心がける
適度な運動は、脳の健康維持に効果的です。とくに有酸素運動は脳の血流を改善し、認知機能の改善・向上に寄与します。週3回程度を目安にウォーキングやランニングなどの軽い運動を行うことで、もの忘れの改善効果が期待できるので、早速取り入れてみましょう。ただし、無理をせず、体力や健康状態と相談しながら運動強度を決めることが大切です。
認知機能トレーニングを行う
認知機能を鍛える脳トレーニングも、もの忘れの予防や改善に効果があります。新聞や本を読んだり楽器を演奏したりと、本人が続けやすい方法を選ぶことが大切です。以前から取り組んでいることや趣味を取り入れれば、ハリのある生活にもつながり、人との交流が心身の健康においてプラスに働く可能性も高まるでしょう。
もの忘れが伴う病気に関するよくある質問
もの忘れはさまざまな原因で起こる可能性があり、もしかしたら病気の兆候なのではないかと不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、もの忘れに関するよくある質問についてまとめましたので参考にしてみてください。
Qもの忘れとADHDは関係ありますか?
ADHD(注意欠陥多動性障害)の特徴として「忘れものや物をなくすことが多い」「約束を忘れてしまう」といったものがありますが、記憶障害によるもの忘れとは性質が異なります。ADHDのもの忘れは、主に注意力の問題に起因するものです。ただし、認知症などの可能性がゼロというわけではありません。不安に感じた場合は、医療機関を受診しましょう。
Q若いのにもの忘れがひどくなりました。
何の病気を疑うべきでしょうか?
考えられる疾患はさまざまですが、40〜60代の若い世代でも発症する若年性認知症の可能性があります。若年性認知症の原因として多いのが、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によるものです。また事故や頭を打った衝撃などで高次脳機能を引き起こしているケースや、ストレスや睡眠不足によるうつ病ももの忘れの原因となる可能性があります。
原因によって治療法が大きく異なるため、不安な症状がある場合は早めに医療機関を受診することが重要です。
もの忘れの適切な対処で健康な脳を維持しよう
もの忘れには加齢によるものと病気によるものがあり、その違いを理解することが重要です。加齢によるもの忘れは軽度で、体験の一部を忘れる程度ですが、認知症などの病気によるもの忘れは、体験そのものを忘れてしまいます。早期発見・早期治療が重要なため、気になる症状がある場合は迷わず医療機関を受診しましょう。
「ガンマ波テクノロジー 認知機能ケア啓発プロジェクト」では、五感ケアや音刺激、ガンマ波など認知症に関連する最新の研究結果を紹介しています。認知症予防の新たな可能性を探る貴重な情報源となっていますので、認知症予防に関心のある方はぜひご覧ください。



