04認知症コラム
【認知症の在宅介護】限界を感じる前に
知りたい5つの基本ケアと心構え
2025.07.31

認知症の方の在宅介護は長引く傾向にあります。異変を感じてから医療機関を受診するまでに2/3のケースで2年以上かかっていること、アルツハイマー型認知症では罹患から死亡までの期間が約8~10年であることなどを考慮すれば、家族の在宅介護期間も相応に長いと予想されるでしょう。介護者の負担や介護が長引くことのリスクについて解説します。
認知症の方の在宅介護で求められる5つの基本ケア
介護者による認知症の方へのサポートは多方面におよびます。在宅看護に求められる基本的なケアについて見ていきましょう。

健康管理
認知症の方の健康状態を良好に保つことは、認知機能にも影響を与えます。水分補給や排泄ケアなど、認知症の方が自分で管理しにくい部分を見守り、サポートすることが必要です。また、自宅での服薬管理や、定期的な通院による専門的な健康管理も、認知症の進行を遅らせるために必要なことといえるでしょう。
- 具体的な健康管理の例
-
- 食事と水分補給の管理
・栄養バランスの取れた食事を用意する
・こまめに水分補給を促す など
- 服薬と体調のチェック
・ピルケースなどを活用し、薬の飲み忘れや誤飲を防ぐ
・体温・血圧・体重などの変化を見る など
- 生活リズムの管理
・睡眠・起床リズムを整える
・日中の活動量を維持する など
- 清潔・感染症対策
・歯磨きや義歯の洗浄などの口腔ケアを行う
・排泄や入浴を介助する など
- 食事と水分補給の管理
環境変化を最小化する工夫
認知症の方は環境の変化に対して適応しにくい傾向にあります。可能な限り生活環境が一定に保たれるようにサポートしていく必要があるでしょう。
例えば、家具や日用品の置き場所はできるだけ変えず、認知症の方が混乱しにくい空間をつくります。また、カレンダーや時計を見えやすい場所に置き、時間や日付が認識しやすいようにするようにすることも有効です。
社会との繫がりを保つ外出支援
認知症の方が社会との接点を持つことは、脳の活性化やストレス軽減、生活習慣病の予防にもつながります。
また、認知症自体の予防にもつながるため、ボランティア活動や地域活動、デイサービスの利用といった社会と関わる活動に積極的に参加することが大切です。認知症の方の能力や好みに合わせた活動を選び、無理なく社会参加できる環境を整えましょう。
信頼関係の構築
認知症の方が「この人なら頼れる」と思えるように、信頼関係を構築することが在宅介護にとって重要です。
周囲が認知症による問題行為に対してイライラして怒ってしまうと、認知症の方は恐怖心を覚え、抑うつ状態や無気力が見られるようになり、さらに認知機能の低下が見られるようになります。普段から穏やかな口調で話すことを心がけ、急かさず、怒らず、安心感を与えられるように意識していきましょう。
自尊心への配慮
認知症を発症しても、一人の人間であることには変わりありません。相手を尊重し、自尊心を傷つけない言葉かけや態度が重要です。
トイレの失敗や同じ質問の繰り返しなどの問題行為に対しても、叱ることなく、冷静に対応するようにしましょう。また、命令口調や人格を否定するような言葉を使わず、常に経緯を持って対応することも大切です。
在宅介護における認知症行動の対処法
認知症の症状には必ず見られる中核症状と、環境や人間関係などによって見られることがある周辺症状(BPSD)があります。周辺症状の中には介護を妨げるものもあるため注意が必要です。よくある周辺症状と対処法については、以下もご覧ください。
暴言・暴力
周辺症状のひとつとして、暴言・暴力が挙げられます。突然怒り出したり、攻撃的な言動が見られたりすることも少なくありません。
暴言や暴力は、脳の機能が低下し、感情のコントロールが難しくなっていることにより生じます。また、不安や痛み、不安感なども原因です。原因を特定して取り除き、必要に応じて専門医に相談するようにしましょう。
徘徊行動
目的なく歩き回ったり、歩きなれた道に迷ったりする徘徊行動は、認知症の典型的な症状です。過去の記憶を辿り何かを確認したいという気持ちや不安感が原因であるといわれています。
とはいえ行動を極端に制限してしまうと、認知症の方の自尊心を傷つけてしまいかねません。GPSや見守りセンサーなどを活用して安全を確保しつつ、適度な運動として見守ることが大切です。
被害妄想
被害妄想とは、「物を盗まれた」「わたしの悪口を言っている」など、事実ではないことを強く信じ込み、周囲の人を疑うことです。記憶障害によるもの忘れや、不安・孤独などから自分を守ろうとすることから生じることがあります。
妄想の内容を直接否定するのではなく、気持ちに共感することが大切です。また、認知症の方が安心できる環境を整え、必要に応じて専門医に相談するようにしましょう。
介護拒否
介護拒否は、入浴や着替え、服薬といった介護行為を拒否する行為です。認知症の方が自分自身の意思や尊厳を守ろうとするための自然な反応で、「何をされるのかわからない」といった不安感から生じます。
介護拒否が見られる場合は、無理強いするのではなく、認知症の方が落ち着いているタイミングで介護を実施したり、介護行為の目的(「身体が汚れているから入浴しましょう」など)を具体的に伝えたりすることで、介護拒否を回避できるかもしれません。
在宅介護で介護者が直面する3つの大きな負担
精神的負担:ストレス・不安・孤独感など
介護の先が見えずに、不安を感じる介護者も多いでしょう。同じ質問を何度も繰り返したり、被害妄想により悪者扱いをされたりすることも、介護者の精神的な負担となります。また、認知症の症状の進行、自分の時間が持てないこと、社会から切り離されたように感じる孤独感なども、介護者のストレスを増やす原因となるでしょう。
身体的疲労:体力の消耗・睡眠不足・腰痛など
認知症の在宅介護は24時間体制です。介護者が睡眠不足になることや疲労が蓄積することもあるでしょう。
入浴や排泄の介助などの身体的介護は、介護者の足腰に負担をかけるため、筋肉疲労の原因のひとつです。また、夜間の見守りも必要なため、生活が不規則になり、より一層健康状態を悪化させることもあります。
経済的負担:医療費・介護用品代・仕事の調整など
介護と仕事の両立は容易ではありません。介護のために仕事を辞めたり勤務時間を減らしたりすることで、収入が減少することもあります。
また、介護保険が適用されるとしても、介護にかかる費用全額がカバーされるわけではありません。保険適用後の自己負担額や、保険適用範囲を超えた介護サービスの費用、おむつ代や介護用品代などが家計を圧迫することもあります。認知症は介護期間も長期化しやすいため、介護費用もかさみがちです。
在宅介護が限界に近づいたときに
生じうる介護者のリスク
在宅介護が長引くと、介護者の負担も増えます。在宅介護が限界になったときに生じるリスクについて見ていきましょう。
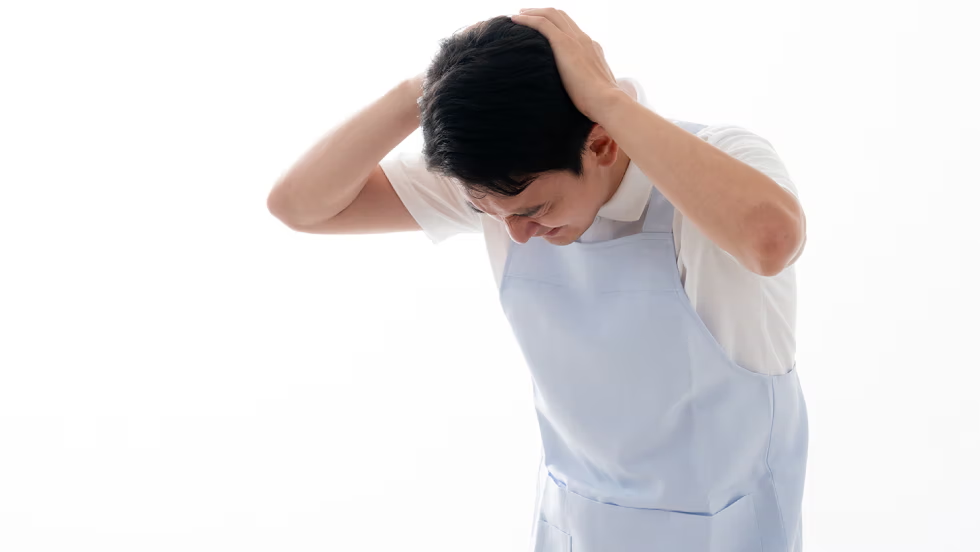
介護離職
介護と仕事の両立が難しくなると、「介護離職」のリスクが高まるでしょう。令和5年雇用動向調査によれば、2023年に介護離職した方は約7.3万人で、2000年は約3.8万人であったことと比べるとおおよそ2倍に増えていることがわかります。
介護離職をした場合、再就職が困難になったり、思うようなキャリアを築けず生涯年収が大幅に低下したりすることも珍しくありません。将来の経済基盤が揺らぐだけでなく、社会とのつながりが希薄になり、介護者自身も孤立する恐れもあります。
介護うつ
責任感が強い人や完璧主義の人は、介護を完璧にしなくてはと思い詰め、「介護うつ」になるケースもあります。意欲の低下や不眠、食欲不振、倦怠感などの症状が見られることも多いです。
介護うつが進行すると、在宅介護の継続が困難になります。早期発見と早期対応が重要といえるでしょう。
虐待や暴力などの突発的行動
介護疲れや経済的な困窮によりストレスが限界を超えると、介護者自身の感情のコントロールが難しくなります。意図せず介護虐待に発展するケースもあるでしょう。
虐待は被介護者だけでなく、介護者自身の尊厳も傷つける行為です。時間をかけて構築してきた信頼関係を破壊することもあり、注意が必要です。
在宅介護を無理なく続けるための3つの心構え
在宅介護を続けるためには、介護者自身に相応の心構えが必要です。無理なく続けていくためにも、押さえておきたいポイントを紹介します。
ストレスを溜め込まない
介護によるストレスが蓄積すると、介護者は心身の健康を損ないます。質の高い介護を長期的に続けるためにも、定期的にストレスを発散することが必要です。
とはいえ、介護をしつつ、ストレスを完全に発散することは容易ではありません。普段から小さな逃げ道を見つけておき、ストレスを溜めすぎないようにしておきましょう。
- 具体的な対応例
-
- 気軽に愚痴を言える相手を見つけ定期的に会話する
- 趣味や運動など自分が楽しめる活動の時間を意識的に確保する
- 介護者の会やカウンセリングなど専門的なサポートを活用する
- 介護の合間に深呼吸や瞑想など短時間でできるリラックス法を取り入れる
自分のペースで介護を続ける
認知症の症状や進行は個人差が大きく、介護環境も異なるため、他の認知症の方と比較できません。まずは他人と比べず、自分に合った介護方法を見つけることが、長期的に介護を継続するための鍵となります。
たとえば、最初から完璧を目指さないこと、できる範囲で介護をすることなどを意識してみることをおすすめします。自分のペースで介護を続けることで、被介護者・介護者にとって心地良い介護を実現しやすくなります。
- 具体的な対応例
-
- 自分と家族の状況に合わせた、無理のない介護計画を立てる
- SNSや周囲の情報に振り回されないように、必要に応じて情報を遮断する
- 小さな成功や改善点を記録し、自分たちの介護の進歩を認める
周囲に上手に頼る
介護を一人で抱えるのは困難です。介護の質を高め、介護者自身の生活の質を維持するためにも、周囲に助けを求めるようにしましょう。
周囲に頼ることが苦手な方も、まずは医師やケアマネジャーなどの信頼できる人に状況を共有してください。適切なアドバイスをもらえることで、心身の負担が軽くなることもあります。
- 具体的な対応例
-
- ケアマネジャーと相談し、必要な介護サービスを積極的に取り入れる
- 家族間で介護タスクを分担し、定期的に話し合いの場を持つ
- 地域の民生委員や地域包括支援センターなど公的支援の窓口を知っておく
- 緊急時に頼れる人のリストを作成し、連絡先を共有しておく
負担軽減に活用したい介護サービス
介護を一人で抱え込むと、早期に介護者の生活が破綻する恐れがあります。介護サービスを活用し、負担を背負いすぎないようにしましょう。
介護保険サービス
介護保険サービスは、公的介護保険制度に基づいて提供される基本的なサービスです。自己負担額は1割~3割で、要介護認定・要支援認定を受けた方のみ、支給限度額の範囲内で利用できます。
- 具体的なサービスの例
-
- 自宅を訪問してもらい、入浴・排泄の介助などの家事援助
- デイサービスで、入浴・食事・レクリエーションなど
- ショートステイでの短期宿泊
介護保険外サービス
全額自己負担とはなりますが、介護保険の対象外となるサービスの利用も可能です。同居家族がいる場合の家事支援など、介護保険対象のサービスよりも幅広いサービスを利用できます。
- 具体的なサービスの例
-
- 通院や買い物など目的を問わない外出同行支援
- 見守りサービスやGPS端末で認知症の方の安全確保
- 契約書の記入補助や金銭管理など事務的支援
行政サービス
自治体によっては、独自に高齢者支援サービスを提供していることがあります。介護者支援や経済的負担の軽減に役立つサービスもあるため、まずは自治体に確認してみましょう。
- 具体的なサービスの例
-
- 紙おむつ支給や購入費の助成
- 認知症サポーターによる見守りや相談
- 徘徊時のSOSネットワーク登録やGPS端末の助成
- 配食サービスや介護タクシー券の発行などの生活支援
一覧認知症の在宅介護に悩んだときの相談先
| 相談先 | 具体的な窓口・連絡先 | 相談内容の例 |
|---|---|---|
| 地域包括 支援 センター |
お住まいの市区町村の窓口 全国の地域包括 支援センターの一覧 |
保健医療・介護に関する相談、関係機関との連携、 適切なサービスの利用支援 |
| 電話相談 |
認知症に関する電話相談 電話番号:0120-294-456(フリーダイヤル) 携帯電話・PHS:050-5358-6578(通話有料) 受付時間:10:00~15:00(祝日を除く平日) |
認知症に関するさまざまな悩み |
| 認知症 疾患医療 センター |
認知症疾患 医療センター のページ |
専門的な医療相談、診断、治療 |
| 医療機関 | ・かかりつけ医 ・認知症学会専門医 ・日本老年精神医学会専門医 |
医療的な相談、診断 |
| 認知症 カフェ |
自治体の高齢者福祉担当課、地域包括支援センターに問い合わせ | 認知症の人や家族の情報交換、交流の場 |
※2025年6月時点の情報
介護する側の健康に目を向けよう
認知症の方の在宅介護は長期化することが多く、介護者の負担も大きくなりがちです。介護を提供する側が健康を維持できなければ、介護の継続も難しくなります。精神的・身体的・経済的な負担を理解し、周囲や行政のサポートを利用することも大切です。
また、認知症についての理解を深めることも、介護の負担軽減に役立ちます。認知症の最新研究から介護の負担軽減のヒントが見つかるかもしれません。下記よりぜひご覧ください。



