04認知症コラム
前頭側頭型認知症の症状と特徴―
原因や治療法、関わり方のポイントを解説
2025.04.30

前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉が萎縮することによって発症する認知症の一種です。一般的な認知症とは異なり、人格変化や行動障害などの特有な症状が現れます。この記事では、前頭側頭型認知症の症状や特徴、原因、診断方法、治療法について解説。また、患者との関わり方や利用できる公的支援制度も紹介します。
前頭側頭型認知症とは?
前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで発症する神経変性疾患です。40〜60代の比較的若い世代で発症することが多く、日本国内の患者数は約12,000人と推定されています。
もの忘れや幻覚、妄想といった一般的な認知症の症状よりも、人格変化や行動障害が顕著な症状として現れるのが特徴です。現在のところ根本的な治療法はなく、症状緩和や環境調整などのケアが中心となります。
前頭側頭型認知症には、発症メカニズムの違いによっていくつかの種類があり、「ピック病」と呼ばれるものが8割を占めています。
- ピック病とは?
- 前頭側頭型認知症の一種。神経細胞内に「ピック球」と呼ばれる変性タンパク質の塊がみられるのが特徴です。患者本人には病識がなく、自分が病気であることを認識できません。

アルツハイマー型認知症との違い
| 比較項目 | 前頭側頭型認知症 | アルツハイマー型認知症 |
|---|---|---|
| 主な 発症年齢 |
40〜60代 | 65歳以上 |
| 脳の 萎縮部位 |
前頭葉と側頭葉 | 海馬から始まり全体に広がる |
| 特徴的な 症状 |
人格変化、行動障害、言語障害 | 記憶障害、見当識障害 |
前頭側頭型認知症とアルツハイマー型認知症の主な違いは、脳の萎縮部位と症状の現れ方にあります。
前頭側頭型は前頭葉と側頭葉が萎縮し、人格変化や行動障害が顕著です。一方、アルツハイマー型は海馬から萎縮が始まり、記憶障害や見当識障害が主な症状として現れます。
前頭側頭型認知症は、社会性の欠如や注意力の低下が初期からみられるようになりますが、時間や場所の認識は保たれ、日常生活の動作はある程度維持できることが多いです。
なお、筋萎縮性側索硬化症(ALS)では約20%の患者が認知症を併発しますが、アルツハイマー型ではなく、多くの場合、前頭側頭型認知症のような症状が現れます。
【関連情報】 アルツハイマー型認知症の基本についての記事はこちら
- ALSとは
- ALSは筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis)の略で、運動神経が徐々に死滅していき、全身の筋肉が衰えていく進行性の神経難病です。
前頭側頭型認知症の原因と発症メカニズム
前頭側頭型認知症の正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、脳内のタンパク質異常と遺伝的要因が関与していることがわかってきています。前頭側頭型認知症の原因と発症メカニズムを詳しくみてみましょう。
タンパク質の変性と蓄積
前頭側頭型認知症は、脳の神経細胞にタウタンパクやTDP-43と呼ばれるタンパク質が異常に蓄積することで、前頭葉や側頭葉の萎縮を引き起こし発症することがわかっています。
これらの異常タンパク質が神経細胞を破壊することで脳の萎縮が進行し、症状が出てくるというメカニズムです。なぜタンパク質が変性・蓄積するのかはまだわかっておらず、現在も研究段階にあります
遺伝的要因の影響
前頭側頭型認知症には、遺伝的要因も関係しています。欧米では3〜5人に1人の割合ともいわれていますが、日本では遺伝による発症例はほとんど報告されていません。ただし、特定の遺伝子変異が関連している可能性もあるため、家族の病歴確認は診断の参考情報となります。
前頭側頭型認知症の主な症状
前頭側頭型認知症では、一般的な認知症の症状である記憶障害や見当識障害はあまり目立ちません。主な症状は「人格・行動の変化」と「言語機能の低下」に大別されます。
人格と行動の変化
前頭側頭型認知症の患者は、社会性の欠如や抑制のきかない行動が顕著になります。たとえば、万引きなどの軽犯罪を起こす、身だしなみに無関心になる、暴力を振るうなどの傾向・行動が特徴で、周囲とトラブルになるケースも少なくありません。
また、同じ行動を繰り返す常同行動や、感情の鈍麻、他人に共感できない、感情移入ができないといった状態がみられ、自発性も低下します。これらの症状が現れるのは、思考、判断、情動のコントロールを行っている脳の前頭葉が萎縮してしまうためです。
言語機能の低下
前頭側頭型認知症のもう一つの大きな症状が言語機能の低下です。脳の側頭葉の機能が低下することで、言葉の理解や表現が徐々に困難になっていきます。初期段階では、日常的な物の名前が出てこなくなったり、単語の意味がわからず会話の文脈を理解できなくなったりする症状が顕著です。
また、流暢に話しているように見えても、その内容が意味をなしていないこともしばしばあります。症状がさらに進行すると、同じ言葉を繰り返すようになり、最終的にはほとんど何も話さなくなってしまいます。
前頭側頭型認知症の進行
前頭側頭型認知症の進行は、初期、中期、後期の3段階に分けられます。初期には衝動的な行動や社会的ルールの無視が目立ち、本人は無自覚な点が特徴です。中期から後期にかけては、人格変化や行動の異常は落ち着いて、無気力・無関心な状態へと移行していきます。
前頭側頭型認知症は、発症してから平均6〜9年程度の経過を辿ることが多いですが、個人差が大きく、必ずしもその限りではありません。後期に、パーキンソン症状や運動ニューロン症状が加わることもあり、その場合、誤嚥性肺炎や呼吸筋麻痺などの合併症リスクが寿命にも影響します。ただし、あくまでも年数については集団的傾向に過ぎず、個人差も大きいため参考程度にして頂ければ幸いです。
| 段階 | 症状 |
|---|---|
| 初期症状 | 人格変化、行動異常、社会性の欠如 |
| 中期から後期 | 無気力・無関心、常同行動 |
| 後期 | パーキンソン症状、運動ニューロン症状 |

前頭側頭型認知症の検査・診断方法
前頭側頭型認知症の診断では、主に問診、画像診断、脳血流検査の3つのステップを通じて総合的に判断が下されます。各プロセスについて詳しくみていきましょう。
問診での確認
まずは専門医が、患者本人と家族から症状や行動の変化について詳しく聞き取りを行います。とくに注目するのが、性格の変化や社会性の低下、常同行動などの特徴的な症状があるかどうかです。患者本人が症状を自覚していない場合もあるため、家族からの情報が重要となります。また、医師は患者の態度や反応も観察し、異常の有無を判断します。
画像診断(CT・MRI検査)
CT・MRI検査では、前頭側頭型認知症の特徴である前頭葉および側頭葉の萎縮の有無を確認します。アルツハイマー型認知症と異なる萎縮パターンがみられるかどうかが重要な確認ポイントです。ただし、初期段階では明確な萎縮がみられないこともあるため、最終的にはほかの検査と併せて総合的な判断を行います。
脳血流検査(SPECT・PET)
SPECT検査やPET検査は、脳の各部位の血流量や代謝を画像化して評価する検査です。前頭側頭型認知症では、前頭葉や側頭葉の血流低下がみられます。MRIで軽度の萎縮しか確認できない初期段階でも、これらの検査で前頭葉・側頭葉の顕著な血流低下が確認できることがあり、診断の重要な手がかりとなります。
脳血流検査の前には、アルコールやカフェインの摂取を控える必要があるため注意しましょう。
前頭側頭型認知症の治療アプローチ
残念ながら、前頭側頭型認知症の発症を直接抑制したり、治癒させたりする根本的な治療薬は現在のところありません。そのため、治療アプローチは主に症状の管理と患者の支援が中心となります。
基本的には非薬物療法を実践する
前頭側頭型認知症の治療は、非薬物療法が基本となります。具体的には、行動療法、アートセラピー、音楽療法、運動療法などです。とくに、患者の行動特性を利用したルーティン化療法が効果的とされています。これは常同行動などの特徴を活かし、問題行動を社会的に許容可能な行動に置き換えることが目的です。
非薬物療法は、作業療法を通じて残存機能の維持を目指す方向性が強く、患者の情緒や行動の安定化、生活の質の向上が期待できます。
薬物療法で症状の緩和を図る場合もある
前頭側頭型認知症に根本的な治療薬はありませんが、特定の症状の緩和を目的として薬物療法が行われることもあります。たとえば、強迫的な行動が問題となる場合には、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やトラゾドンなどの抗うつ薬を投与するケースもあります。
また、アルツハイマー型認知症の治療薬は、前頭側頭型認知症に対する効果は低く、むしろ行動心理症状を悪化させる可能性があるため注意が必要です。薬物療法は個々の患者の症状や状態に応じて慎重に検討する必要があります。
前頭側頭型認知症のケアで
大切な5つのポイント
前頭側頭型認知症のケアは、患者の症状に合わせた個別のアプローチが重要です。ここでは、患者と介護者の双方にとって負担が少なく、よりよいケアを実現するためのポイントをみていきましょう。
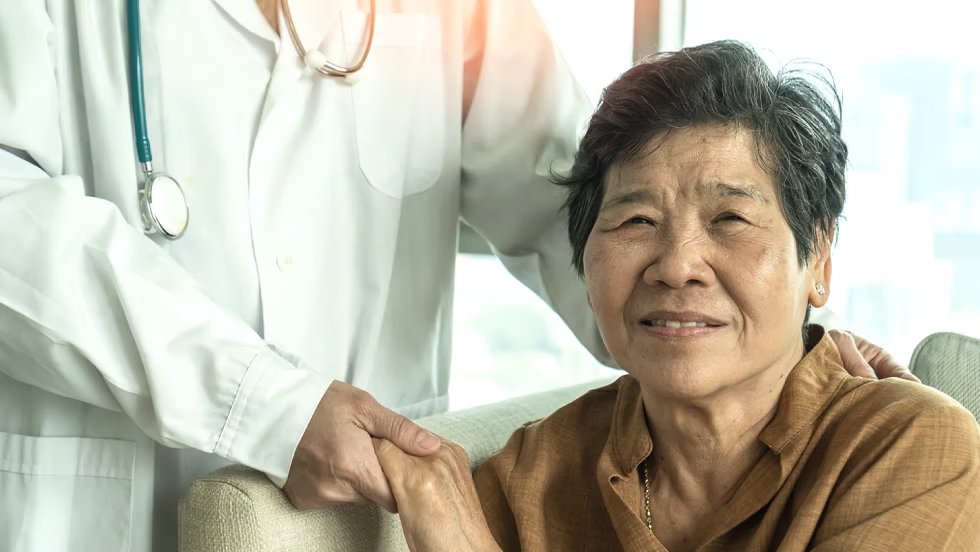
本人の常同行動に合わせて
スケジュールを作成する
前頭側頭型認知症の患者は常同行動を示すことが多いため、これを利用してスケジュールを組むのが効果的です。たとえば、デイサービスに通う時間は毎日同じにする、時間割やアラームを活用して生活リズムを維持するなど、規則正しい生活パターンを作るようにしましょう。
- ポイント
- スケジュールの急な変更は混乱を招くため避ける
食べ物は本人の見えない場所に保管する
前頭側頭型認知症の患者は食行動の異常を示すことがあります。過食や不適切なものを食べる行動を防ぐため、食べ物は患者の目に触れない場所に保管し、安全な食事環境を整えて誤嚥を予防しましょう。患者の状態をよく把握し、適切な量の食事を適切なタイミングで提供することが重要です。
- ポイント
- 甘い物へは過度な執着をみせる場合があるため注意する
周囲にあらかじめ声をかけておく
前頭側頭型認知症のケアでは、周囲の理解と協力が欠かせません。患者の行動が周囲に迷惑をかける可能性があるため、近隣の人々へ事前に状況を説明しておくことが大切です。たとえば、暴力を振るってしまったときや、万引きなどの行為があったときの対応方法を周囲の人や店舗にあらかじめ相談しておくことで、大きなトラブルを避けられます。
- ポイント
- 非常事態に備えて、緊急時の連絡先を関係者と共有しておく
認知症ケアに特化した施設を利用する
前頭側頭型認知症の場合、特有の症状に対応できる専門的なケアが必要な場合があります。そのため、グループホームなど認知症ケアに特化した少人数制の施設を優先的に検討することが重要です。デイサービスや短期入所、在宅サービスの利用も選択肢に入れておくとよいでしょう。
- ポイント
- 施設のスタッフと本人の特徴や対応方法を詳細に共有する
家族だけで抱え込まずに専門家と連携する
前頭側頭型認知症のケアは家族だけで抱え込まず、医療機関や介護サービスなどの専門家へ相談することが重要です。ケアマネージャーと連携して適切なケア方法を学び、医療機関と定期的に連絡を取り合う体制をつくることで、患者と介護者双方の負担を軽減できます。
- ポイント
- 早い段階で信頼できる相談先を探しておく
前頭側頭型認知症で利用可能な支援制度
前頭側頭型認知症は、比較的若い世代で発症することが多く、経済的な負担が大きくなる可能性があります。患者や家族の負担を軽減するためにも、以下のような支援制度を活用することが重要です。
指定難病医療費助成
前頭側頭型認知症は「前頭側頭葉変性症」として指定難病に認定されており、医療費助成制度の対象となります。申請には、主治医の診断書と必要書類を都道府県の窓口に提出します。審査を経て認定されると、所得に応じて医療費の自己負担額に上限が設定され、超過した分は支払う必要がありません。
介護保険サービス
前頭側頭型認知症は「初老期における認知症」として特定疾病に含まれるため、40〜64歳でも条件を満たせば介護保険サービスを利用することが可能です。市区町村の窓口で申請手続きを行い、要介護認定を受ければ、在宅介護や施設介護にかかる費用の一部を補助してもらえます。
その他の経済的支援
前頭側頭型認知症の患者は、精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。取得すると、税金の免除や減免、公共サービス料金の割引、公営住宅の優先入居などの支援を受けられます。
また、障害年金の受給も可能です。障害基礎年金や障害厚生年金の受給資格を満たせば、年金給付を受けられます。さらに、高額医療費制度を利用すれば、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に超過分の助成を受けられます。
ほかにも、傷病手当金など収入保障の制度もあり、これらを積極的に活用し、経済的負担の軽減を図ることが重要です。
前頭側頭型認知症を
正しく理解し、適切なケアを
前頭側頭型認知症は、認知症の多くを占めるアルツハイマー型とは異なり、人格変化や行動障害などの特有な症状が現れます。適切なケアを行い、患者の生活の質や家族の負担を抑えるためにも早期発見・早期対応が重要です。前頭側頭型認知症の患者や家族が利用可能なさまざまな支援制度もありますので活用しましょう。
認知症は一度発症すると治療が難しく、現在のところ根本的な治療法は確立されていません。そのため、早期からの適切なケアと予防が重要です。最新の研究では、認知機能を維持するための方法がいくつか明らかになっています。認知症予防の最新情報は、ぜひこちらをチェックしてみてください。



