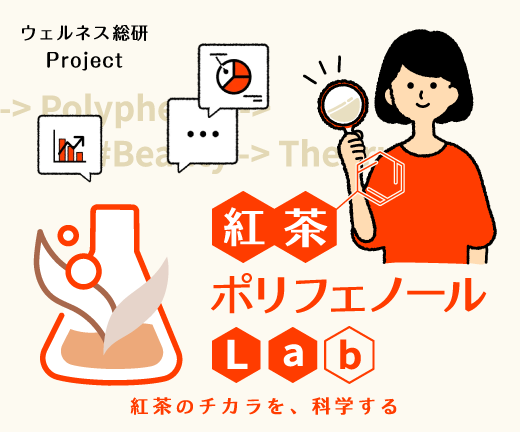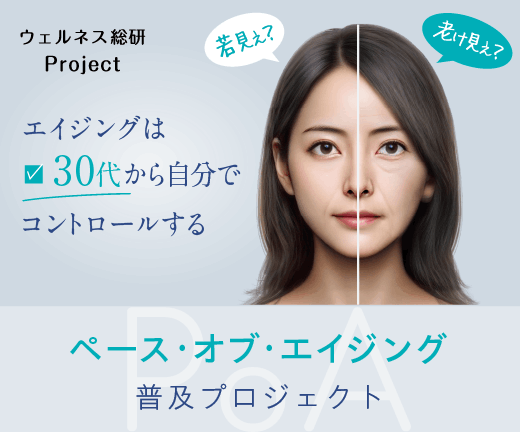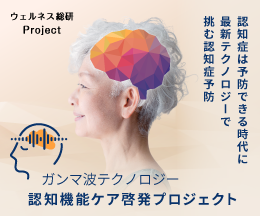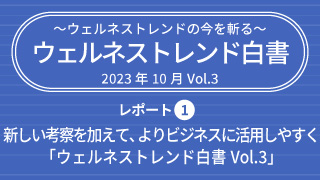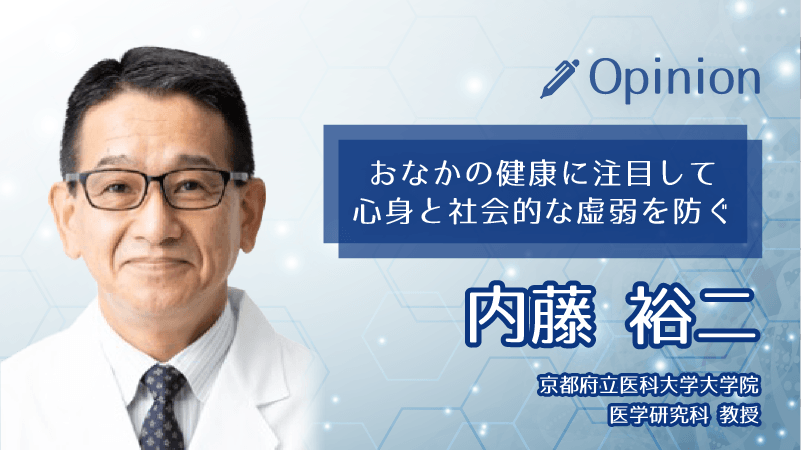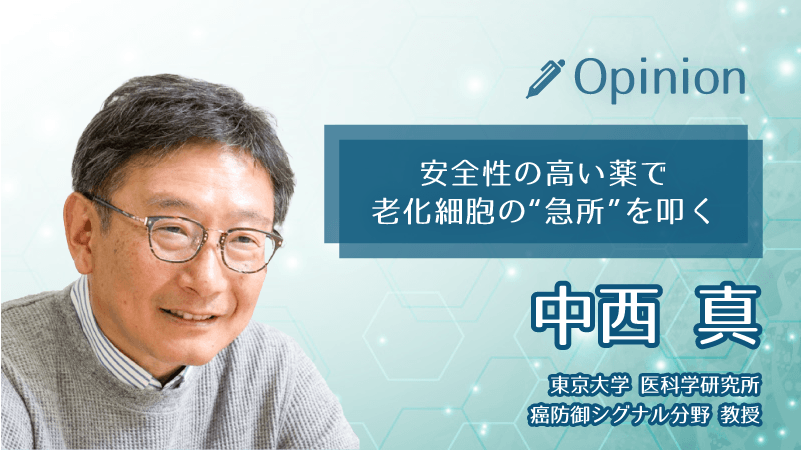咀嚼と脳電位の関係性を紐解く
自然科学研究機構共創戦略統括本部 特任准教授
坂本 貴和子氏に聞く
オーラルケアへの注目が集まる昨今、口腔に関する研究は、味覚や咀嚼、唾液、免疫、消化など、さまざまなテーマで研究が進んでいる。今回は、咀嚼と脳電位の関連に関する研究実績を有する坂本貴和子氏に登場いただき、これまでの成果について伺った。また同氏が所属する自然科学研究機構(National Institutes of Natural Sciences以下:NINS)共創戦略統括本部で進めている取り組みについてもお話を聞いた。
分野を横断した知見や信頼性の高いデータが研究の水準を底上げする
NINSは、国立天文台、核融合科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、分子科学研究所の5つの研究所と、機構直轄の2つのセンター(アストロバイオロジーセンター,生命創成探究センター)で構成される大学共同利用機関です。宇宙やエネルギー、物質、生命などに関わる自然科学分野の中核的研究拠点として、一つの大学や研究機関では維持・管理することが難しい大型装置をはじめとした最先端の研究機器を保有し、全国の大学や研究機関に所属する研究者へ共同利用・共同研究の機会を供しています。このシステムによってさまざまな分野に跨る研究者コミュニティ同士をつなぐとともに、革新的な最先端研究を遂行するために必要な知識と技術、研究活動の場を提供しています。
私の所属する共創戦略統括本部は、国内外の大学・研究機関との共同利用・共同研究とのさらなる推進に向け、情報発信・広報や研究者支援、産学連携など、さまざまな支援を行いながら、分野を横断した研究プラットフォームの整備や、分野の枠を超えた新分野創成に取り組んでいます。
研究者が研究を進めるなかで、自身の専門分野を深めていくことはとても大切なことですが、一方で、異分野の研究者と交流することによって、今まで想像しなかったような革新的なアイディアが創出されることもあります。通常は、異分野の研究者と出会い、交流を深める機会に恵まれることは少なく、知り合えたとしても互いの分野を知り合い、知見を深めあう機会はそうそう恵まれていないのが現状です。それは御多聞に洩れず、私のルーツである歯科業界でも同様に言えることでした。
歯科の世界では、「よく噛むことでとても良い効果が得られる」と信じられています。確かに日々の診療の中では、義歯やインプラント、詰め物などによって咀嚼機能を改善することで、ほぼ寝たきりだった人が自立歩行できるようになったり、認知機能が改善したりと、よく噛めるようにすることによる素晴らしい効果を実証するような症例がいくつも存在します。ですがそれらの効果はあくまで臨床医の主観による評価が多く、客観的な指標によって評価した研究は非常に少ないのが現状でした。つまり、咀嚼機能の改善によって具体的にどのような生理現象が生じ、さまざまな良い効果へとつながっているのかについて、再現性の高い実験系を用いた検証が十分に成されてきたとは言い難い状況だったのです。日本咀嚼学会が提唱する「咀嚼がもたらす良い効果」の中には、「リラックス効果」や「認知機能の改善」など、脳機能に影響を与えているとおぼしきものもあります。そこで私は、「咀嚼は脳機能に影響を与えているかもしれない」という仮説のもと、具体的にどのような影響があるのかについて調べるべく、さまざまな分野の研究者との連携のもと、とある実験を考案しました。実験を行う上で大切にしたのは「客観的指標によって再現性の高い実験とする」ことです。つまり私以外の誰が、いつ、世界のどの国で同じ実験を試みても、私の出す結果と同じ結果が出る実験である、ということです。しかしヒトの脳活動は非常に個人差が大きく、さらに被験者の人種や年齢、性差などによってどうしても多少のブレが生じます。世界のいつ、どこで、誰が同じ実験を遂行しても「A=B」の結果を得ることができたらそれこそ客観性や信憑性の高い成果と言えますが、できる限り、せめて「A≒B」とみなすことができる実験を練ることが、研究者として当然の姿勢であると私は考えています。
ニュートラルな脳活動を測定する難しさ
私が行ってきた研究は、咀嚼と、それに伴う脳の反応を読み解くものです。
私たち神経科学の研究者がヒト脳機能計測で知ろうとしていることをシンプルに言うと、脳の「いつ」「どこで」「どのような」反応があるか、これが知りたいのです。脳機能計測は大まかに言うと、①神経細胞の発火に伴う電気活動や神経線維の周囲に発生する磁場をダイレクトに計測する方法と、②脳の血の巡りをみる方法の2種類があります。いずれもメリット・デメリットがあり、自身が知りたい事象が一体何かによって実験機器を複合的に選択することが大切です。
私が咀嚼の実験で使用した脳波計(EEG)や光トポグラフィ(NIRS)は比較的安価であり、世界中の研究機関や病院に設置されています。一方で、脳磁場計測器(MEG)や機能的磁気共鳴画像装置(fMRI)は高価であり、実験用の装置を設置できる大学や研究機関もそう多くはないため、研究者の所属によっては気軽に利用することができないかもしれません。私が研究に脳波計を用いたのは、私の実験系と相性がよかったからというのもありますが、安価でどこでもある機械であるため、再現性を確認しやすいから、ということも理由の一つにあげられます。
咀嚼をはじめとした顎口腔領域の運動と脳機能測定は決して相性が良いとは言い難いものです。なぜかというと、脳と口はあまりに位置が近く、咀嚼に関連する筋肉の活動によって発生する電場、磁場がノイズとなり、脳反応が全てかき消されてしまうためです。つまり咀嚼の最中の脳活動を計測することはほぼ不可能ということになります。そこで私の研究では、咀嚼中の脳活動ではなく、咀嚼によって得られる脳への影響、つまり咀嚼のAfterEffectを確認することにしました。ここで用いたのが事象関連電位(EventRelated Potential)測定という計測手法です。事象関連電位は、末梢から入力されるさまざまな感覚を認知、判断、処理する過程に発生する脳活動を指します。脳活動一つ一つは微小で判別することはできませんが、加算平均法を用いることで描出することができます。
サイクリック動作としてのガム咀嚼が脳活動へ影響
2009年に発表した成果についてお話しすると、判断指標には事象関連電位の一つであるP300 Component(以下:P300)を用いました。これは、これまでとは異なる逸脱刺激が入力された時に発生する脳反応であり、刺激の認知、判断、処理を反映していると考えられています。例えば暗いまっすぐな道を運転していた時、突然横から自転車が飛び出してきた情報が視野に飛び込んできたとしましょう。その時みなさんは「お!」と反応し、できる限り早くブレーキを踏むと思います。この自転車の情報が視覚に入力されてから約300m秒後に脳に現れる大きな陽性波が、P300という脳波です。この脳波を「低い音(スタンダード刺激:提示確率80%)」と「高い音(逸脱刺激:提示確率20%)」で表現し、高い音が聴こえたらできるだけ早くボタンを押してもらう実験を行いました。この際の脳活動とボタン押しの反応時間を同時に計測しています。被験者は、実験の合間に5分間の休憩をとってもらうのですが、計4回の計測と合間の休憩3回をひとつの実験とし、この実験を日を跨いで計4回行いました。4回の実験では、間の休憩時間にそれぞれガムを噛んでもらう日、何もせずただぼーっと過ごす日、口に何も入れず顎の開閉運動(歯を嚙み合わせない)をする日、そして右手の人差し指でタッピング運動をする日、といった4パターンの行動を行ってもらい、それぞれの実験で得られた脳活動と反応時間を比較しました。
結果、休憩中にガムを噛んで過ごしたときは計測を重ねるごとに、脳の反応(P300の潜時)とボタン押しの反応時間が早くなることが判明しました。一方で、それ以外の休憩の過ごし方では、このような脳活動の活性化や反応時間の短縮は全く見られないどころか、いずれも計測を重ねるにつれ、P300の潜時もボタン押しの反応時間も遅くなりました。なぜ休憩時間にガムを噛んだだけでP300の潜時や反応時間が短縮したのでしょうか。
私たちが考えているのは、リズム動作に伴う脳の覚醒効果です。脳幹に位置する上行性網様体賦活系は、感覚刺激の入力を受けて大脳皮質に電位を送ることで覚醒状態を惹起します。また、上行性網様体賦活系の近傍には、中枢性パターンジェネレーターという、歩行や自転車漕ぎなど、無意識的に身体が動くサイクリック動作で活性化する部位があり、中枢性パターンジェネレーターの賦活化に伴い事象関連電位の潜時や振幅が変化することが先行研究によって確かめられています。今回の咀嚼もまた無意識的に持続可能なリズム動作と言えます。つまり咀嚼によって中枢性パターンジェネレーターが賦活化し、上行性網様体賦活系による覚醒状態が引き起こされたものと考えられます。以上の成果から言えることは、咀嚼は確かに脳活動へ何らかの影響を与えている、ということです。
運動準備電位と咀嚼の関わり
私たちが発表した2009年の別の成果では、咀嚼は刺激の認知、判断、処理に関わる部位に対して影響を与えている、というところまで判明しています。1つ目の成果で分かったのは、あくまで「咀嚼を行うことで、P300と反応時間に影響を与えた」ということのみでした。この実験だけでは、刺激の認知、判断、処理を行う部分に効いたのか、それともボタン押しに関わる運動を処理する過程に効いたのか判別することができません。そこでこの研究では、2種類の運動準備電位を測定し比較検討することで、咀嚼が脳に与える影響をさらに詳しく検証してみました。
運動準備電位には、大きく分けて①刺激始動性の運動に伴う運動準備電位と、②自発的な運動に伴う運動準備電位の2種類が存在します。まず始めに①について説明します。例えば100m走では、「用意」で準備して、「どん!」で速やかに運動を発現します。この運動が発生する2秒ほど前から、私たちの脳では大きな陰性の波が発生することが知られています。これを難しい言葉で「随伴性陰性変動(Contingen Negative Variation:CNV)」と呼びます。CNVは刺激の認知、判断、処理を行っている際の脳活動を反映していると考えられています。もう一つの②については、まずはゴルフやダーツなどの運動を想像してください。これらの動作は、誰かの指示なしに、自身のタイミングで運動を発現します。このような自発的な動作であっても、上記のCNVと同様、2秒ほど前から運動の準備に伴う大きな陰性波が発生します。これを難しい言葉で「運動関連脳電位(Movement Related CorticalPotential:MRCP)」と呼びます。MRCPはシンプルに運動に関わる脳活動を反映していると考えられています。これら2つの脳波は、互いにとてもよく似た波形をしていますが、発生のメカニズムが全く異なることが分かると思います。
CNVの計測は、P300の計測とよく似ています。2種類の音を使い、低い音が「用意」、高い音が「どん」です。高い音が聴こえたらできるだけ早くボタン押しをしてもらい、ボタン押しの手前の運動準備電位と、ボタン押しの反応速度を計4回計測します。計測の合間に休憩を計3回を挟み、休憩中にガムを噛む日と何もせずリラックスして過ごす日の、2日間にわたって実験を行いました。すると、休憩中にガムを噛んで過ごした日のCNVと反応時間は、何もしないで過ごした場合と比べてCNVの振幅は増大(活性化)し、反応時間も短縮しました。一方で休憩時に何もせず過ごした場合の運動準備電位は顕著に振幅が小さくなるとともに反応時間も延長しました。つまり、咀嚼にはCNVの発生にかかる脳領域へ影響を与えていることが示唆されたのです。
もうひとつの運動準備電位であるMRCPを計測する際は、被験者に自分のペースで指の伸展動作を行ってもらいました。ペース感覚は体感で約5秒の間隔を空け、自発的に指の伸展を行なってもらいます。この際の脳活動を計4回、間に3回の休憩を挟み、休憩中にガムを噛ませた日と何もせずリラックスした日の比較を行いました。すると、休憩時にガムを噛んでいた場合でもリラックスしていた場合でも、MRCPの振幅は変化がないどころか、次第に小さくなっていきました。
以上の結果からわかることは、「咀嚼は刺激の認知、判断、処理過程へ影響を与えるが、運動そのものに影響は与えない」ということです。
多角的な知見を生かして得た研究成果
私が実施してきた実験にはこれ以外も色々なものがありますが、これらは私の歯科医学の知識とアイディアだけでは実現できませんでした。神経内科学、生理学、スポーツ科学、心理学、精神科学など、実に多岐にわたる研究者が、本研究には関わっています。今回は詳細を割愛しますが、2015年の成果では、咀嚼が大脳皮質に存在する抑制系へ与える影響について述べています。咀嚼が脳に与える影響を客観的に評価することに成功したのは、現在のところ私の「ガム噛み3部作」しかないのではないでしょうか。今後はこれらの成果を遥かに凌駕するような、別の切り口からの革新的な成果が出てくると良いなと思います。その時がいつになるかわかりませんが、その研究の引用の中に私の成果が入る日を今からとても楽しみにしているのです。

坂本 貴和子(さかもと・きわこ)/Kiwako Sakamoto
東京歯科大学卒、総合研究大学院大学修了
博士(医学)
京都大学医学部附属病院歯科口腔外科学講座医局員、日本学術振興会特別研究員(PD)、生理学研究所 助教を経て現在に至る。
「FOOD STYLE 21」2024年12月号 この人に聞く より