04認知症コラム
MMSE(ミニメンタルステート検査)とは?
点数の計算方法やカットオフの基準、
長谷川式との違いを解説
2024.12.26

MMSE(ミニメンタルステート検査)とは、認知機能を客観的に評価するための簡易検査です。この記事では、MMSEの質問項目や採点基準、カットオフの点数、実施時・評価時の注意点を解説します。とくに身近な方に認知症が疑われる場合は、最後までご覧ください。
MMSEとは
MMSE(Mini-Mental State Examination、ミニメンタルステート検査)とは、認知機能を客観的に評価するための簡易テストです。質問式で、認知症の疑いがあるかどうかを調べるときに用いられます。
MMSEは11の質問から成る検査です。30点満点で評価し、23点以下のときには認知症の疑いがあると判断します。ただし、MMSEは症状が表れていない方を対象に病気を見つける目的で実施するスクリーニング検査のため、認知症かどうかを判断するものではありません。

MMSEは比較的安い費用で受けられる
MMSEの検査は、健康保険が適用されるため、比較的安価に受けられます。診療点数は80点で、健康保険が適用される場合は1割負担の方は80円、3割負担の方は240円です(※)。
MMSEは特別な機器や材料なしに実施できるため、診察費に含まれることもあります。また、一部の地域や指節では、無料でMMSEを受けられることもあるようです。
※令和6年度診療報酬改定後の費用
MMSEの費用は80円~240円程度
MMSE-JはMMSEの日本語版
MMSEはアメリカで開発された検査のため、日本の風土や文化にそぐわない質問や評価基準が含まれています。
日本の文化や言語に合わせて調整された検査が、MMSE-Jです。MMSE-JはMMSEの日本版で、日付や場所の質問が日本のカレンダーや地名に合わせて変更され、日本で暮らす方が回答やすいように工夫されています。
MMSEの具体的な実施方法
MMSEは11の質問に対して1~5点の点数が割り振られ、正答数を基に合計点を算出します。所要時間は通常10~15分程度です。特別な機器や環境を準備する必要はありません。評価用紙と筆記具、時計もしくは鍵、白紙の用紙があればいつでも実施できます。
MMSEの実施前に準備するもの
MMSEの評価用紙 鉛筆と消しゴム 時計または鍵 白紙の用紙
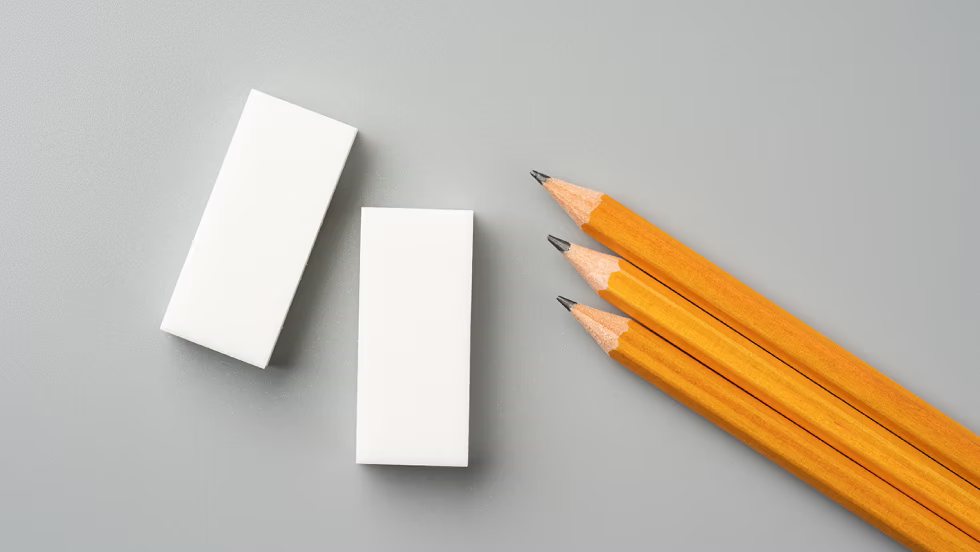
MMSEの質問項目と採点基準
MMSEは簡単な11の質問で構成されます。質問内容と採点基準について見ていきましょう。
| 質問項目 | 点数 | 内容 |
|---|---|---|
| 1.時間の見当識 | 5点 | 検査日の年月日や季節、曜日を問う |
| 2.場所の見当識 | 5点 | 検査が実施されている地方や都道府県、市区町村、施設名、階数を問う |
| 3.即時想起 | 3点 | 3つの単語を順に言い、被検者に復唱させる |
| 4.計算 | 5点 | 100から順に7つずつ引いた数を答えさせる |
| 5.遅延再生 | 3点 | 「3.即時想起」で言った単語を答えさせる |
| 6.物品呼称 | 2点 | 物品を見せ、名称を答えさせる |
| 7.文の復唱 | 1点 | 1つの文章を言い、被検者に復唱させる |
| 8.口頭指示 | 3点 | 口頭で指示を与え、指示通りに行動できるか確認する |
| 9.書字指示 | 1点 | 文章で指示を与え、指示通りに行動できるか確認する |
| 10.自発書字 | 1点 | 自由に文章を書かせる |
| 11.図形模写 | 1点 | 図形を見せ、書き写させる |
1.時間の見当識
MMSEでは最初に時間の見当識を問います。見当識(けんとうしき)とは、現在の時間や場所を把握することです。年月日や季節などの時間にかかわる5つの設問をし、1つの正答に付き1点を付与します。
- 例
- 「今日は何日ですか?」「今日は何曜日ですか?」「今は何月ですか?」と質問する
2.場所の見当識
次は場所の見当識を問う設問です。地域や施設名を尋ねることで、被検者が現在いる場所を正確に認識してるかを確認します。場所にかかわる5つの質問を実施し、1つの正答に付き1点を付与してください。
- 例
- 「ここはどこですか?」「この建物の名前は何ですか?」と質問する
3. 即時想起
即時想起は被験者の短期記憶を評価する設問です。3つの単語を1つにつき1秒かけてゆっくりと言い、すぐに被験者に繰り返してもらいます。覚えていた単語1つに付き1点を付与するため、最大3点です
3つの単語は「5.遅延再生」でも使うため、もし被験者が繰り返せないときはテスト者が最大6回まで復唱し、被験者がすべて言えるようにしておきます。
- 例
- 「りんご」「ペン」「時計」といった単語を提示し、正確に繰り返せるかを確認する
4.計算
100から7ずつ引いて答えさせる質問です。93、86、79、72、65と1つ正答するたびに1点を付与し、最大5点付与します。
被検者が答えに詰まったときは、「それから」と促し、続けられるようにサポートしてください。
5.遅延再生
「3.即時想起」の3つの単語に意識を向け、覚えているか尋ねる質問です。1つ正答するたびに1点を付与するため、すべて正答すると3点となります。
- 例
- 「先ほどの3つの単語を覚えていますか?」と尋ねる
6.物品呼称
物品を見せ、名称を答えてもらう質問です。時計もしくは鍵の1品と、鉛筆1本を見せ、名称を答えてもらいます。正解1つにつき1点、最大2点付与します。
- 例
- 被験者にペンや時計などの物品を見せ、「これは何ですか?」と尋ねる
7.文の復唱
簡単な文章を口頭で伝え、被検者に復唱してもらう設問です。被検者が聞き取りやすいように、ゆっくり、はっきり話すことが大切です。被験者が正確に復唱できたときは1点付与します。
- 例
- 「今日はとても良い天気です」といった簡単な文を提示し、繰り返せるか確認する
8.口頭指示
被験者に簡単な指示を口頭で与え、正確に実行できるかを確認する質問です。指示は3つの動作を含み、1つの動作を正確にすると1点、最大3点付与します。
- 例
- 紙を渡しながら「右手にこの紙を持ち、半分に折りたたんで、わたしにください」といった指示を出す
9.書字指示
文章で指示を与え、正確に実行できるかを確認する質問です。指示は1つの動作を含み、正確に実施したときは1点を付与します。
- 例
- 「この紙に名前を書いてください」といった書かれた指示を見せる
10.自発書字
被験者に簡単な文章を書かせる質問です。意味のある文章であれば何でも正答とし、1点を付与します。
名詞だけを書いたときは0点ですが、状態を示す四字熟語は1点です。被験者自身の理解度を問うため、テスト者は例文を挙げないようにしてください。
- 例
- 「簡単な文章を書いてください」と指示する
11.図形模写
2つの五角形が一部重なっている図形を見せ、正確に模写できるか評価する質問です。角が10あり、2つの五角形が重なっていたら正解と判断し、1点を付与します。
MMSEのカットオフの点数
MMSEの判断基準となるカットオフ値は、23と27です。点数によりどのように判断するのか解説します。
【28~30点】問題なし
MMSEの点数が28~30点の場合は、日常生活において認知機能の低下は見られず、とくに問題がないと判断されます。ただし、認知機能は変化するため、28点以上であっても定期的にチェックを実施することが重要です。
【24~27点】軽度認知障害の可能性あり
MMSEの点数が24~27点の場合は、軽度認知障害(MCI)の可能性があると判断することが一般的です。日常生活においても支障をきたす可能性があるため、早期に専門医の診断を受け、適切な対策を実施することが推奨されます。
【23点以下】認知症の疑いがある
MMSEの点数が23点以下の場合は認知症の可能性があると判断されます。日常生活においても困難が予想されるため、早期に専門医の診断を受け、適切な対策を実施することが必要です。
また、MMSEの点数を用いて、認知症の重症度を簡易的に判定することもあります。一般に21点以上は軽度、11~20点は中等度、10点以下は重度としますが、より正確かつ総合的に判断するためにも、MMSE以外のスケールも合わせて用いるようにしてください。
MMSEを実施する際は被験者への配慮が大切
MMSEを実施するときは、被検者への心理的配慮が非常に重要な意味を持ちます。落ち着いた気持ちで検査に臨んでもらうためにも、静かでくつろげる個室が望ましいでしょう。また、個室を選ぶことで、テスト者と被験者の信頼関係を築きやすくなるだけでなく、被験者のプライバシー保護にもつながります。
認知機能の問題を正確に判断するためにも、被検者が理解しやすい言葉を選ぶことも大切です。質問の意図がわからず、あるいはよく聞き取れずに回答できないケースをなくすためにも、ゆっくりと聞き取りやすく話し、必要に応じて繰り返し説明するようにしてください。
MMSEの評価を行う際の注意点
MMSEを用いて認知症の評価を行う際にはいくつか注意点があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

認知機能の低下以外の可能性も疑う
MMSEの点数が27点以下のときは軽度認知障害や認知症が疑われますが、それ以外の要因も考慮することが必要です。たとえば、うつ病や不安障害といった精神的な症状や、身体的な病気、薬の副作用によって認知機能が低下している可能性もあります。
点数だけで認知機能を判断するのではなく、必要に応じて他の検査や専門家の意見を取り入れて、総合的に評価するようにしてください。
確定検査ではないことを念頭におく
MMSEは認知機能のスクリーニング検査であり、確定診断のための検査ではありません。MMSEの結果だけで、認知症の診断を下すことは避けましょう。ほかの検査や専門医の診断と併用することが必要です。
また、スクリーニング検査であっても正確性が求められます。MMSEを実施するときは、周囲にカレンダーや時計などの回答のヒントになるものを置かないようにしてください。
MMSE以外の認知機能検査
認知機能を調べる検査方法や評価ツールは、MMSEだけではありません。よく使われる方法を紹介します。
改訂長谷川式簡易知能評価スケール
| MMSE | 改訂長谷川式 簡易知能評価スケール |
|---|---|
|
|
改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)は、日本の文化や言語に特化して設計された評価スケールです。記憶力や見当識、計算能力などの認知機能の各側面をバランスよく評価できます。
一方、MMSEはアメリカで開発された評価スケールです。改訂長谷川式簡易知能評価スケールと同じく質問式で実施されますが、質問によっては口頭では回答できず、記述が求められます。そのため、HDS-Rより詳細な評価が可能で、とくに認知機能の低下が疑われるときに有効なスケールと考えられています。
そのほかの認知症テスト
ほかにも、異なるアプローチで認知機能を評価するテストは下記右記のようなものが挙げられます。これらのテストを組み合わせることで、包括的かつ多角的な認知機能の評価が可能となります。
| テスト名 | 内容 |
|---|---|
| Mini-Cog | 3語の再生と時計描画を組み合わせた2分程度で実施できる簡易検査 |
| MoCA | 視空間・退行機能、記憶、注意力、抽象概念などの多様な認知機能を評価する10分程度の検査 |
| CADi2 | 認知症早期発見のための10項目から成るテストアプリ。トレーニングも実施できる |
| 認知症高齢者の日常生活自立度 | 高齢者の生活を観察し、認知状態を9段階で簡易的に判断する評価指標 |
複数のスケール・テストを用いて認知状態を把握しよう
MMSEはアメリカで開発された認知機能の低下を判断するスケールですが、日本の文化や言語に合わせて調整されたMMSE-Jを用いれば、日本国内でも認知症や軽度認知障害のスクリーニングに活用できます。HDS-Rと比べると質問が多様で、より多面的に判断できる点が特徴です。
しかし、あくまでもMMSEは評価スケールのひとつであり、MMSEだけで認知症や軽度認知障害とは診断できない点に注意しましょう。精神的な状態や病気、薬の影響なども想定されるため、他のスケールやテスト、医師の診断なども合わせて包括的に判断することが大切です。
認知症は一度発症すると根治が難しいといわれています。認知機能の評価や改善などについての最新研究を知ることで、認知症予防につなげていきましょう。



