04認知症コラム
認知症になりやすい人の口癖は?性格や生活習慣、対策も解説!
2024.05.09

認知症になりやすい人には傾向があることがわかってきています。特に、口癖には人の考え方や習慣が出やすいものです。この記事では、認知症になりやすい人の口癖や性格、生活習慣について紹介します。また、そのような口癖があらわれたときにおすすめの対策も紹介します。
認知症になりやすい人の口癖は?
認知症になりやすい人の口癖の例
「どうせできない」 「昔はよかった」 「もう疲れた」 「○○したらどうしよう」 「あの人はどうしようもない」 「誰もわかってくれない」
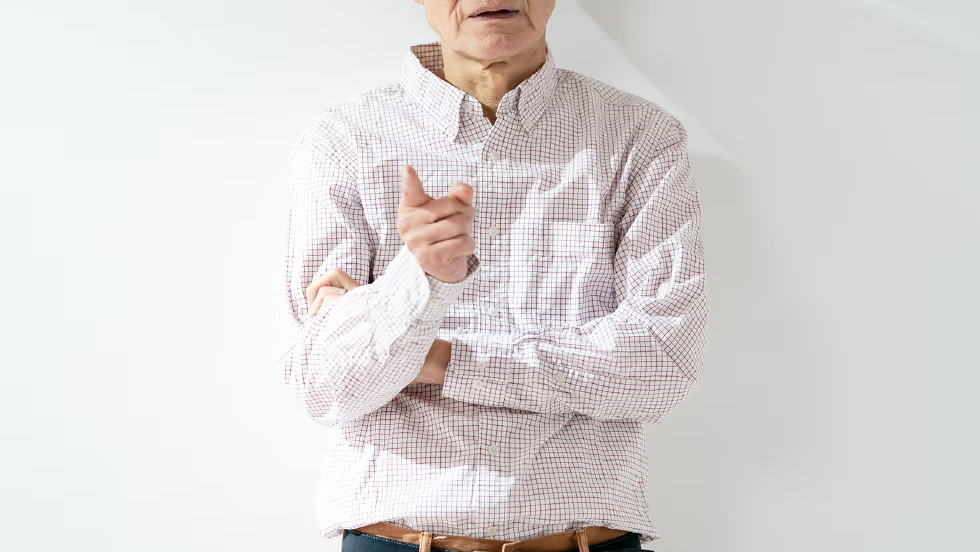
現在では認知症に関する研究が進み、認知症になりやすい人の性格に傾向があることが示唆されています。例えば、ネガティブ・心配性であることや、柔軟な考え方ができず頑固な人は認知症になりやすいとされ、上記のような口癖がみられるのです。
さらに、その性格が影響して社会との繋がりが減少した結果、脳への刺激が少なくなり、さらにストレスを溜めやすく、認知症を発症する可能性が高まります。口癖はあくまで目安なので、心配なことがあれば専門医に相談してみるのもよいでしょう。
認知症と口癖の関係
口癖はその人の性格を端的に表します。性格と認知症の発症リスクには関連性が示唆されており、海外の研究によると、心配性でネガティブな人や批判的な人は特にリスクが高いとされています。
これは、認知症がストレスと関係があると考えられているためです。人はストレスを感じると、ストレスホルモンである「コルチゾール」が分泌されます。コルチゾールは過剰に分泌されると全身の血流を悪化させることがあり、脳に酸素が届きにくくなってしまいます。
その結果として、ストレスは脳の機能を弱め、認知症になりやすくなるのです。
認知症になりやすい性格
性格が上記に当てはまる人は認知症になりやすいといわれています。その特徴から孤立しやすく、脳への刺激が少なくなりがちです。ストレスも感じやすいため注意が必要です。認知症になりやすい性格について詳しくみていきましょう。
気分が落ち込みやすい
気分が落ち込む「抑うつ状態」は、脳の働きを鈍らせます。さらに、精神的に落ち込むと、家に閉じこもりがちになり、じっとしてしまうことも増えるでしょう。すると、さらに脳への刺激が減り、認知症のリスクが高まります。
小さなことを気にする
小さなことを気にする神経質な傾向がある人は、些細なことでもストレスを感じやすいです。ストレスにさらされる時間が長く続いた結果、うつになってしまう場合もあるでしょう。前述したように、ストレスやうつは脳の働きを弱め、認知症が発症するリスクを高くします。
心配性である
前述したとおり、心配性な人はそうでない人と比べて認知症を発症するリスクが約2倍という研究結果が出ています。これは、心配性の人が不安感を抱きやすい特徴があることから、ストレスを感じている時間が長いことが原因と考えられます。
出典:Najar, Östling et.al.「Cognitive and physical activity and dementia」
人付き合いが苦手
人付き合いが苦手な人は自然と付き合いの範囲が狭くなり、会話が減少する傾向にあります。コミュニケーションが減ると脳への刺激が減り、脳が衰えやすいため注意が必要です。さらに、普段から関わる人が少ないため、認知症発症のサインに気づかれないケースもあるでしょう。
怒りっぽい
怒りっぽい人はストレスを感じやすい傾向にあります。さらに、その性質から社会的に孤立する可能性が高いでしょう。孤立してしまい、人との関わりが減ることで脳への刺激が減少し、結果的に認知症を発症する場合があります。
批判的である
他人に対して批判的であったり、皮肉を言ったりすることが多い人は、認知症を発症するリスクが約3倍にもなると報告されています。その原因として、批判的な人は自分の考えを曲げられず、ストレスにさらされる傾向にあることが考えられます。
出典:Neuvonen, Rusanen et.al.「Late-life cynical distrust, of incident dementia, and mortality in a population-based cohort」
認知症になりにくい性格
認知症になりやすい性格がある一方で、認知症になりにくい性格もあります。共通した特徴として、周囲から孤立しにくく、社会性が保たれやすい性格であることが挙げられます。
責任感がある
責任感がある人には、どんなことも根気よくやり遂げる力があります。自身の健康管理にも責任感を持って取り組み、健康的な生活習慣を続けられるでしょう。自然と認知症予防によいとされる運動習慣や食生活を生活に取り入れ、継続できる傾向にあります。
勤勉である
勤勉な人には活動的な人が多い傾向にあります。人の意見を素直に受け入れ新しいことに挑戦するため脳への刺激が多く、認知機能が維持されやすいでしょう。活動的で人の意見を素直に受け入れられる性格から、周囲の人との関係もうまくいく傾向にあります。
自制心がある
自制心がある人は、家族関係をはじめとして、周囲の人との良好な関係を築ける傾向にあります。社会的に孤立することが少なく、コミュニケーションが活発に行われるため、認知機能が期待できるでしょう。また、食事などの健康管理も行えるので、認知症のリスクを抑制できます。

認知症になりやすい人の生活習慣
生活習慣の乱れは認知症のリスクを増加させます。まずは、生活習慣を見直すことから始めましょう。認知症のリスクを抑えるために、気をつけるべき点を詳しく紹介します。
乱れた食生活
食生活が乱れていると認知症の発症リスクが高まるばかりか、生活習慣病の原因にもつながります。例えば、高血圧や糖尿病などの生活習慣病は血管に悪影響を与え、脳血管性認知症などを発症するリスクを高めるでしょう。
そのため、塩分が多い食事や、糖分が多い食事などは認知症の発症を早めてしまう可能性が高まります。そのほか、血管に悪影響を与えると考えられているトランス脂肪酸の摂りすぎにも注意が必要です。
過度な飲酒
飲酒は少量であれば、認知症予防になる可能性が示唆されていますが、過剰な飲酒では脳の萎縮を招きます。また、大量のアルコール摂取によるビタミンB1不足は「ウェルニッケ脳症」を招き、脳の機能低下にもつながるのです。
このように、アルコールによって引き起こされる認知症を「アルコール性認知症」と呼びます。長期間にわたるアルコールの乱用や過度な飲酒は、認知症のリスクが4.6倍にもなるとされています。
出典:厚生労働省「アルコールと認知症」
喫煙
喫煙者は非喫煙者と比較して、血管性認知症のリスクは約3倍も高いとされています。これは、喫煙によって血管の収縮が起こり、高血圧、脳梗塞、脳出血のリスクが高まるためです。
また、因果関係は明らかになっていませんが、喫煙者がアルツハイマー型認知症になるリスクは非喫煙者と比べて約2倍も高いとされています。喫煙は認知症だけでなく、がんや脳卒中、心筋梗塞などを発症する危険性も高めるため、できる限り禁煙を心がけましょう。
出典:日本健診財団「喫煙者は認知症になりやすい!?」
運動不足
認知症の中で最も多いアルツハイマー型認知症の原因の多くは、運動不足によるものだとする研究結果があります。運動不足は全身の血流の低下を招き、認知症の原因につながるためです。
さらに運動不足は、生活習慣病のリスクを高めます。加えて、筋肉量の低下に伴い行動範囲が狭まると、脳が刺激を受ける機会が減少するおそれがあるので注意しましょう。
睡眠不足
睡眠不足になると、アルツハイマー型認知症の原因として考えられるアミロイドβが脳内に蓄積しやすくなります。アミロイドβはタンパク質の一種で、蓄積すると脳の神経細胞を害するおそれのある物質です。
不眠症はアミロイドβの生成・蓄積を促進する可能性があることが示唆されています。また、不眠症による神経細胞の変性もアルツハイマー性認知症の発症リスクを高めると考えられているため注意が必要です。
出典:北村拓朗 鈴木雅明 鈴木秀明「睡眠と認知症」

認知症になりやすくなる病気
高血圧
高血圧は、特に血管性認知症のリスクを高める因子です。高血圧による動脈硬化は、脳梗塞や脳出血など脳血管障害の発症リスクを高めます。脳血管障害は脳に流れる血液を阻害するため、脳細胞に酸素や栄養が行き届きにくくなり、脳細胞に大きなダメージを与えるでしょう。
糖尿病
糖尿病の人は健常者と比較して、認知症になりやすいとされています。糖尿病はアミロイドβの排出を阻害し、認知症の原因の一つと考えられている老人斑(アミロイド班)の生成を促すのです。糖尿病は動脈硬化も引き起こすほか、認知症のリスクを高める悪影響の多い疾患です。
参照:羽生春夫「糖尿病と認知症―最新の知見」
肥満
肥満は糖尿病や高血圧にも大きく関わり、認知機能を低下させるおそれがあります。また、肥満者には脳の灰白質や海馬の容積の減少がみられることから、アルツハイマー型認知症との関連性が示唆されています。さらに、肥満者には運動習慣がないことも認知症のリスクを高めている一つの原因として考えられるでしょう。
出典:益崎裕章 岡本士毅「肥満症に伴う認知機能障害―脳科学基礎研究の動向」
慢性腎臓病
慢性腎臓病は、血管性認知症のリスクを高める疾患です。これは、腎臓病による尿素などの蓄積が認知機能低下に影響を与えているためだと考えられています。また、透析を受けている患者には、脳萎縮が同時にみられるケースも少なくありません。脳に流れる血液量の減少が脳萎縮の原因として考えられ、前頭葉と側頭葉の萎縮は遂行機能の低下を招きます。
出典:日本透析医会「慢性腎臓病における認知機能障害と脳萎縮」
歯周病
マウスによる実験結果によると、歯周病菌がアミロイドβを増加させる可能性が示唆されています。アミロイドβの増加によって認知症を発症するリスクが高まります。また、歯周病による口腔機能の低下によって咀嚼する機会が減少し、脳への刺激が減ることも認知症のリスクを高める一因として考えられるでしょう。
出典:日本歯科衛生士会「認知症の予防には歯周病予防対策を!」
認知症になりやすい人の口癖がみられたときの対策
認知症になりやすい人の口癖がみられ始めたら、認知症予防のための対策が必要なサインかもしれません。生活習慣を見直し、人との交流を持つような取り組みを心がけましょう。

食生活を見直す
食習慣を見直すことで、認知症の進行を抑制できる可能性があります。栄養バランスがよく、規則正しい食生活は認知機能低下のリスクを軽減させます。摂取カロリーや塩分、糖分を適切な量にすることで、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病を防ぐことにもつながるでしょう。過度な飲酒は控えてください。
- 食事のポイント
-
- バランスのよい食事を心がける
- さまざまな食品を摂取する
- 野菜・果物・魚などの抗酸化・抗炎症作用のある食品が含まれている食事が好ましい
出典:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」
運動習慣を取り入れる
認知症予防には運動習慣を取り入れることも大切です。特に有酸素運動は、認知症への効果が認められています。さらに有酸素運動は、脳の血流増加だけでなく、神経細胞の活性化や炎症の抑制、アミロイドβの排出を促す効果も期待できるでしょう。
また、運動はストレスの発散や睡眠の質の向上にも役立ちます。自分に合った方法を見つけて、継続して行うようにしてください。
- 運動のポイント
-
- 週3日以上の運動を、半年以上継続させる
- 1日30~40分の有酸素運動を行う
- 筋トレなどのメニューも組み合わせて行う
出典:佐藤正之「認知症に対する運動療法の効果とそのメカニズム」
睡眠の質を向上させる
しっかりと睡眠がとれていることも、認知機能の低下を抑制するのに効果的でしょう。十分な睡眠によって、アミロイドβの排出を促します。
一般的に睡眠時間は加齢とともに短くなる傾向があります。眠気がないのに寝床に長時間いることや昼寝をすることは、夜間の寝つきが悪くなり睡眠の質を低下させるため、避けましょう。
- 睡眠のポイント
-
- 目覚めたときに休まった感覚があることが大切
- 眠気がないのに寝床にいることは中途覚醒の増加の原因になるので避ける
- 昼は活動的に、夜はしっかり眠るといったメリハリをつける
出典:e-ヘルスネット「高齢者の睡眠」
社会活動をする
人と接する機会をつくり、認知機能を維持する活動をするのも予防する手段の一つです。人と接する機会をつくるには、ボランティアに参加する、教室に通うなどの方法があります。自分の趣味や特技、経験を活かせる活動内容だと参加へのハードルが低くなるでしょう。
そのほか、社会的な交流を保つには、友人を見つける、同窓会に顔を出すなどもおすすめです。
認知症になりやすい人に関するよくある質問
ここでは、認知症になりやすい条件に関してよくある質問をまとめています。認知症を予防したい方は、参考にしてみてください。
Q認知症になりやすい血液型はありますか?
近年、血液型によって病気のリスクに違いがある可能性が示されています。バーモント大学の研究によると、AB型の人が他の血液型に比べ、認知症リスクが高いことが示されています。ただあくまでも一部の研究結果であるため、すべての人に当てはまるかどうかを知るためには今後さらに研究が必要です。
出典:近藤雅雄「血液型と病気」
Q認知症のなりやすさに男女差はありますか?
男女差はあるとされています。認知症全体では男性が女性より1.6倍多いですが、アルツハイマー型認知症については女性の方が男性より1.4倍多いことが厚生労働省の統計によりわかっています。
Q認知症と歯周病に関連性はありますか?
研究により、歯周病菌がアミロイドβの生成・蓄積を促進させることがわかっています。アミロイドβが脳に蓄積すると、脳の神経細胞が傷つき、認知機能の低下・認知症を引き起こすとされています。
認知症になりやすい人の口癖が気になり始めたら早めに対策を
認知症になりやすい人の性格傾向はあります。上記で紹介したような口癖が多くみられるようになってきたら、認知症予防のための対策が必要なサインです。早めに生活習慣を見直し、人との交流を持つような取り組みをすることで、認知症の発症を遅らせ、抑える効果が期待できるでしょう。



