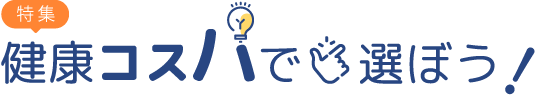「健康コスパ」を徹底比較豆腐編
「健康コスパ」で選ぶならどっち? 木綿豆腐VS絹ごし豆腐
TOFU
高たんぱく質、低カロリー、女性に
うれしい大豆イソフラボンも豊富
そのまま食べたり、潰して和えたり、煮込んだりなど、料理のアレンジもしやすく、手頃な価格で1年中手に入りやすい「豆腐」。
良質なたんぱく質を含み、低カロリー、脂質が少なく、ヘルシーなのが特徴です。また、生活習慣病や骨粗しょう症の予防、美肌などにも効果が期待できる大豆イソフラボンや、脂質代謝に関わるレシチン、脂肪の蓄積の予防や活性酸素を除去する働きのあるサポニンなど、健康に関わるさまざまな機能を持つ成分も数多く含んでいます。
- 健康コスパとは
- 健康を軸にしてコストパフォーマンスを見る、健康に特化した指標。食品にどのような栄養素がどのくらい含まれており、得られる価値やメリットがどのくらいあるのかを表しています。
そんな健康にも美容にもうれしい豆腐ですが、購入するとき、「木綿豆腐」を買いますか? 「絹ごし豆腐」を買いますか?
もちろんメニューによって使い分けることもあると思います。また好みもあるかもしれません。では、「健康コスパ」で比較してみるとどうなのでしょうか。
今回は「木綿豆腐」と「絹ごし豆腐」の「健康コスパ」「コスパ」「タイパ」「食品特性」を比較します。
製法の違いが健康コスパの差に
管理栄養士の浅野まみこさんに「健康コスパ」「コスパ」「タイパ」「食品特性」の4つの軸で、「木綿豆腐」と「絹ごし豆腐」を比較していただきました。
-
健康コスパ
-
木綿豆腐5
絹ごし豆腐4
木綿豆腐と絹ごし豆腐は、製法が異なるため、栄養面にも違いが生じます。木綿豆腐は大豆を茹でて絞った豆乳をにがり(凝固剤)で固めたものを型に入れ、圧力をかけて押し固めて作ります。一方絹ごし豆腐は、豆乳ににがり(凝固剤)を加えてそのまま固めます。
水分を抜いて凝縮して作る木綿豆腐は、たんぱく質やカルシウムなどの大豆本来の栄養素が多く含まれており、絹ごし豆腐に比べて、全体的に少しずつ栄養価が高くなっています。反対に水分量が多い絹ごし豆腐は、栄養価はやや下がりますが、カロリーが低く、カリウムが多いのが特徴です。
ふたつに栄養面での大きな差はありませんが、より多く栄養素を含んでいるという点では、木綿豆腐の方が、少しだけ健康コスパが高いといえます。

コスパ
-
木綿豆腐5
絹ごし豆腐5
どちらも年間を通して手頃な価格で販売されているので5に。
タイパ
-
木綿豆腐4
絹ごし豆腐5
絹ごし豆腐は、コンビニ等でも売られていることが多く、サラダや白和えなどの惣菜メニューも多数あり、より身近で購入しやすいといえます。また、ドレッシングやマヨネーズ、ケーキなどの調理にも使いやすく、手に入りやすさ、アレンジのしやすさという点で絹ごし豆腐は5の評価に。木綿豆腐は焼く、煮るなどの調理には適していますが、コンビニ等では扱っていない店舗もあるため4に。
食品特性
(軟らかさ)-
木綿豆腐3
絹ごし豆腐5
軟らかさという食品特性で比較すると、軟らかく、つるりとした喉ごしが特徴の絹ごし豆腐は5、しっかりした歯応えの木綿豆腐は3に。
木綿豆腐は、製造過程で水分を
しぼるため、栄養分が圧縮されます

今回は「木綿豆腐」と「絹ごし豆腐」を比較しました。どの項目においてもふたつの豆腐に大きな差はないものの、健康コスパで比較すると、「木綿豆腐」の方が少しだけ高いことがわかりました。
次回は「めかぶ」と「もずく」を徹底比較していきます。
 監修
監修

浅野まみこさん
管理栄養士
総合病院、女性クリニック、企業カウンセリングにて糖尿病の行動変容理論をベースに1万8千人以上の栄養相談を実施。その経験を生かし、現在は、健康経営サポート、レシピ開発、食のコンサルティングをはじめ講演、イベントなど多方面で活躍中。メディア、雑誌にも多数出演。具体的な食品を使った実践型栄養アドバイスをモットーに活動をしている。